





BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。
交響曲5番〜8番②
| 交響曲5、6番 | 交響曲7、8番 |
| 交響曲7番イ長調Op.92 | |
| ① | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1957年8月25日、ザルツブルク | |
| ORFEO C 710 081 B | |
| ② | |
 | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1958年4月17日、ベルリン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCG-2324/7 | |
| ③ | |
 | ニューヨーク・フィルハーモニック |
| 1962年11月25日、ニューヨーク | |
| LANNE LHC-7067 | |
| ④ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1970年9月6日、ルツェルン | |
| セヴン・シーズ(キング・レコード) KICC 2412 | |
| ⑤ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1972年8月30日、ザルツブルク | |
| sardana sacd-218/9 | |
| ⑥ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1972年9月10日〜18日、ウィーン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) F00G 29056/61 | |
| ⑦ | |
 | バイエルン放送交響楽団 |
| 1973年5月3、4日、ミュンヘン | |
| audite(キング・インターナショナル) audite 23.404 | |
| ⑧ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1975年3月16日、東京 | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCG-90491/7 | |
| ⑨ | |
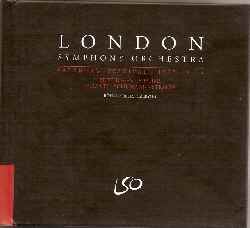 | ロンドン交響楽団 |
| 1977年8月10日、ザルツブルク | |
| ANDANTE 4CDsANDANTE 4983 | |
| ⑩ | |
 | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1977年10月8日、ベルリン | |
| METEOR MCD-012 | |
| ⑪ | |
 | ケルン放送交響楽団 |
| 1978年6月22日、ヴッパータール | |
| WEITBLICK SSS0176/0178-2 | |
| ⑫ | |
 | シュトゥットガルト放送交響楽団 |
| 1979年2月14日、シュトゥットガルト | |
| Papageno様個人所有音源 RCAA 74582 F-OT | |
| ⑬ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1980年6月17日、ウィーン | |
| CIN CIN CCCD 1009 | |
| ⑭ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1980年8月17日、ザルツブルク | |
| ORFEO ORFEO R 910151 | |
| ⑮ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1980年10月6日、東京 | |
| Altus ALT065 | |
| 1813年に書かれたこの第七は、ベートーヴェンの全交響曲中でも最も聴衆を熱狂させる力を持っており、演奏会においても全クラシック音楽中屈指の人気作品となっている。その最大の特徴は全編を支配するリズムの運動性。だからこそワーグナーはこの交響曲を”舞踏の聖化”と称したのである。因みにベートーヴェンは前年に書かれた本来の第七を第八と称し、本来第八であるべきこの交響曲を第七とした。そして、何れもリズムをコンセプトにしている。但し、第八が序奏なしのハイドン〜モーツァルト的様式をベースとした何処迄も愛らしい表現に徹しているのに対し、こちらは同じくハイドンやモーツァルトの『リンツ』、『プラハ』、39番といった序奏付き交響曲をベースにしながら、ダイナミックスの振幅の大きい、正にベートーヴェンならではの豪快な仕上りになっている点が特徴である。ベートーヴェン自身、第七を”大きな交響曲”、第八を”小さな交響曲”と呼んでいたという。 この交響曲は『ウェリントンの勝利(戦争交響曲)』や既に初演されていた第八と共に初演された。『ウェリントン』は今では楽聖の作品としては高い評価を受けている訳ではないが、交響詩を準備する革新性を持つ意欲作であり、矢張りベートーヴェンを語る上で忘れてはなるまい。何れにせよ、三者三様の魅力を持った大作を同時期に書き上げているところに、楽聖の創作の秘訣を見出す事が出来よう。 さて、第七はベートーヴェンならではの豪快な表現がたっぷり含まれている反面、『英雄』、第五、第九の様な理念は含まれておらず、『田園』の様に絶対音楽でありながら、標題性を兼ね備えているという訳でもなく、聴衆に要求する物が大きくないにも関わらず、圧倒的な演奏効果を誇る為、演奏会でもよく採り上げられ、録音も少なくない。 この交響曲で高い評価を受けているのはカルロス・クライバーだ。この天才指揮者ならではのリズムの躍動感、しなやかなメロディー・ライン、そして強靭でありながら軽快さを失わないダイナミックス等この交響曲の持つ音楽的魅力を余すところなく抽出しているとされるからである。 一方で、この交響曲に潜むバッカス的狂気を抽出しているという事で、メンゲルベルクやフルトヴェングラーらの激烈な演奏を支持する声もある。 DVD編にも書いたが、カール・ベームがその生涯で最も多く指揮したと思われるベートーヴェンの交響曲は他の多くの指揮者と同じくこの第七であった。録音に関しては、ベームの生前には②と⑥のみが知られていたが、その死後幾多の演奏が登場している。現在私が所有しているのは15種類(映像を入れると重複分を除いた18種類)である。 ①は2008年10月に突如陽の目を見たザルツブルク祝祭のライヴ。ベーシック音量は小さめなので、ヴォリュームは大きくした方が良い。音質自体は年代を考えれば上等の部類に属する。私はこれを聴く前、1950年代のライヴという事で幾つかのケースを想定していた。本当は先入観に縛られるのは良くないのだが、今迄聴いてきた演奏の経験が、どうしてもそうした事を想像させてしまうのだ。一つは質実剛健スタイル。基本はスタジオ録音風の全体の作りだが、より健康的で逞しく、隙のない造型、隅々迄充満した密度の濃い響きと気合が生み出すエネルギーはこの上ない充実感を齎す。もう一つは”爆裂系”スタイル。若干大味な側面を持ち、やたらと力瘤が入っているが、兎に角強烈で破壊神の如し。「指揮台のジキル博士とハイド氏」の”ハイド氏”的側面が前面に押し出された演奏。そして、ウィーン・フィルの演奏でよく聴かれる滲み出る様な美しさに溢れたスタイルなどである。この①は強いて言うならば、質実剛健スタイル。全体的完成度が高く、スタジオ録音風。勿論、3楽章後半や終楽章後半など、ライヴのベームならではの盛上がりを聴く事が出来る。こういう時のベームはともするとぶっきら棒になって、色気にやや乏しくなるのだが(その骨っぽさが”男の美学”に相通じるものがあり、好きな人も少なくない)、此処ではウィーン・フィルの奏でる旋律群の美しさに浸る事が出来る。それは内から滲み出る様な味わい深さがあり、魅了されずにはいられない。特にⅡ楽章が素晴らしい。”爆裂系”の演奏を期待した人は一寸ガッカリかも知れないが、力強さと美しさを併せ持ち、何とも言えないコクを感じさせる①が音楽的に高い水準にある事は疑い様がなく、矢張りベームならではの名演として一聴の価値がある。 ②はステレオ録音初期の名盤で、ガッチリとした構築性が武器になっている。特にリズムを強調している訳ではないし、強烈さをアピールしている訳でもないので、一見何の変哲もない演奏に思われる。しかし、こうしたオーソドックスなスタイルで”本格派の味”を堪能させてくれる点がこの演奏の良さである。ベルリン・フィルも力強く、密度が濃い。それ故に極めて音楽としての充実度の濃さを感じる。嘗てはこの交響曲の代表的名盤の一つであった事も当然と肯ける。 ③は2010年11月にH.M.様より頂戴したCD−R。ベームがニューヨーク・フィルに客演した貴重な記録だ。エア・チェックの為、音は拡がりに欠けるが、音質自体は1962年のエア・チェックの割に悪くは無い。或いは放送時期がもっと後の年代だったのかも知れない。演奏自体は殊更に個性的な側面は感じられないものの、構成感覚の見事さや力強さ、気迫の高まりなど充分にベームらしい魅力を湛えている。希少性などを考えても一度は聴いておいて損のない演奏であると言えるのだが、CD−Rでしか発売されていないというのが残念だ。それにしても、これを下さったH.M.様には何時もの事ながらひたすら感謝するばかりである。 ④は日頃メールで遣り取りしているH.M.様より贈って頂いた物である。此処には②の様な堅固な構築感はない。録音がややボケ気味である事も関係あるが、矢張り④はウィーン・フィルがパートナーという事も関係あるだろう。それでいて、造型の緩みは感じさせない。ウィーン・フィルの美しさと力強さは存分に発揮されている。これで録音がもう少し締まっていたら、物凄い聴き応えを感じ取る事が出来るに違いないと思わせる演奏である。そういう意味で、本拠のムジーク・フェラインザールでの演奏でない事が残念だ。しかし、ベームとウィーン・フィルが素晴らしい演奏を披露している事はピンボケ気味の録音からでも感じ取れる。その場にいたら圧倒されたであろうと思わせる量感を感じさせる強音部、Ⅱ楽章を筆頭とする旋律線の内容的な美しさ。ライヴのベームならではの要素を随所に聴く事が出来る。何時もの事ながら、H.M.様には心から感謝を捧げたい。 ⑤は2008年末にH.M.様より頂戴した全集収録直前のライヴCD−Rである。録音に関しては、金管やティンパニが遠いのが気に入らないが、弦と木管の素晴らしさがそうした不満を消し去ってくれるのが救いである。両端楽章やスケルツォなどの強奏部においては、微塵の隙も感じさせない熱気を感じさせ、旋律群においては溢れ出んばかりの味わいの豊かさがある。特にⅡ楽章はベーム〜ウィーン・フィルならではの他の追随を許さぬものを感じさせる感動的名演だ。全体的に、実際に聴いていたら、どれ程素晴らしい演奏だった事か、と思わせる。収録時間は短いものの、終演後の熱狂的な「ブラヴォー!」がその証となっている。これを下さったH.M.様には何とお礼を述べて良いやら、言葉が見当たらない。 ⑥は全集に含まれている演奏で、同じスタジオ録音ながら、嘗ての②と比べると、ベームの指揮は大らかなものになり、リズムや構築性よりはメロディー・ラインの伸びやかさや美しさが魅力になっている。これはウィーン・フィルが相手という事と無関係ではあるまい。特に2楽章の美しさが出色。勿論、力強さがない訳ではなく、終楽章の終盤の盛り上がりは流石という迫力を感じさせる。 ⑦は日頃メールの遣り取りをしているH.M.様より頂いたCD−Rと同一の演奏の正規盤である。ベームの指揮したバイエルン放送響との幾多のライヴはオルフェオ等から発売され、高い評価を受けているが、中でもブラームスの第一は無比のドライヴ感で知られている。何れにせよ、このヨッフムとクーベリックに鍛えられた名門とベームの相性はよく、それはこの⑦も変わらない。CD−Rではやや大味な面が目立っていたが、正規盤ではより音質が向上しただけでなく、アンサンブルの精度も高まり、粗さが軽減されている。何処迄も力強く、造型性は豊か、木管のメロディー・ラインの味わい深さと開放感も魅力で、全体的にみて極めて聴き応えがある。また、随所にライヴのベームならではの凄味が漂っているのも何と言っても魅力だ。特にⅠ楽章展開部後半やⅢ楽章のトリオ、そして終楽章の後半の破壊力は思わず絶句。ティンパニーや金管が暴れまくる。ベーム〜バイエルン放送響のライヴではブラームスの第一と双璧と言える強烈無比な表現が聴かれる。但し、CD−Rでは粗削りながらライヴのベームならではの破壊力を味わう演奏という感じだったのが、この⑦では②や⑥とそう遜色ない完成度の高さを示しつつ、其処にライヴのベームならではの気合の高まりが示されている事も忘れてはなるまい。78歳にしてこういう演奏が出来るなんて、矢張りベームは凄い。これはファンならずとも一聴の価値がある名演だ。 ⑧もまたH.M.様より贈って頂いた物である。伝説と化した1975年の来日公演の初日のライヴだ。この初日の演奏に関しては褒めている人間が少ない事もあり、私も大して期待はしていなかったのだが、だからこそ逆に予想以上に良く聴こえる。1楽章序奏の力強く悠然とした歩み。主部も若干緊張感を欠く部分はあるが、全体的にはライヴのベームならではの熱気があるし、力強い。コーダのホルン強奏など、目を見張るばかりだ。2楽章の美しく、ニュアンスに満ちた演奏もまたベームならではの感銘を与えてくれる。3楽章も特にトリオが印象的だ。ウィンナ・ホルンが深々とした余韻を感じさせるし、強奏部分の凄味は⑦にそうそうひけをとらない。尤も、此処まで凄くやる必要があるのかという人もいるだろうが。終楽章はやや落ちる。若しかすると、そのせいでこの演奏の印象度が低いのかも知れない。緊張力がやや弱い部分がある。ベームは元々第七の終楽章で、物凄い快速テンポを選択する事はないとはいえ、最初はあれっと思った。しかし、終盤に向けて次第に高揚していき、最後はテンポを速めるのではなく、寧ろ悠然と力強く締め括っているのが印象的だ。若干の不満を相殺して余りあるものがある。何時もの事ながら、私の様な人間に素晴らしい演奏の数々を贈って下さるH.M.様には心から感謝したい。 ⑨はベーム晩年のザルツブルク祝祭のライヴである。音質はあまり良くないが、ベームはこの交響曲をより大きくまとめている。特に1楽章の序奏が悠然とした趣を持っている。 ⑩はY.M.様より贈って頂いたコピーである。ベルリン・フィルがパートナーという事もあって、重厚かつ立派な響き、造型の隙のなさは流石とも言うべき全体的完成度の高さと充実感を齎してくれる。⑦みたいな如何にもライヴといった感じの荒っぽさはあまり感じないが、如何にも「モノが違う」といった印象を与えてくれる本格派の、言い換えるなら大人の名演と言える。これを下さったY.M.様には心の底から感謝を捧げたい。 ⑪はH.M.様より贈って頂いたCD−R(FKM FKM-CDR-47/8)を最初に聴いた。⑨同様スケールが大きく、重厚な演奏で、⑮を準備するものであるという事が出来るが、カルロス・クライバーの様に快速でかっ飛ばしていくスタイルとは異なる磐石の構えを貫きつつ、気合の高まりを感じさせる点が印象的だ。録音は決して良いとは言えないし、内容自体好き嫌いは分かれるかも知れないが、個人的にはベームならではの存在感を示した名演だと思う。これを下さったH.M.様には何とお礼を言って良いか、本当に言葉が見当たらない。 尚、2015年末にWEITBLICKから発売されたベーム〜ケルン放送響ライヴ集にもこの⑪が含まれていた。若干音質は良く、鮮明度や透明感、量感が増し、風格や内容の豊かさもより感じられる様に成った。今迄は販売ルートの限られたCD−Rしか無かった音源が普通のCD店やネット通販などで容易に入手出来る正規盤CDとして発売された事も誠に嬉しい限りだ。これを発売してくれたWEITBLICKにはよくぞ発売してくれた、と言いたい。 ⑫は2010年1月にPapageno様より送って頂いたエア・チェック。1979年7月30日にNHKがラジオで放送した物である。海外マイナー・レーベルから発売されているが、そちらは未聴。こちらの演奏に関してだが、84歳のベームの指揮に隙はなく、シュトゥットガルト放送響もチェリビダッケ時代に鍛えられた力量の確かさを示し、引き締まった演奏を繰り広げている。ライヴのベームに時折聴かれる爆発力というか、凄味はないが、音楽的に見て立派で充実度の濃い名演という事が出来るだろう。これを下さったPapageno様には心の底から感謝を捧げたい。 ⑬はY.M.様より贈って頂いたコピーである。⑮と同じ年の演奏であるにも関わらず、内容的には⑥に近い。録音は木管がやたらと大きく拾われており、やや金管やティンパニが遠い為、迫力が減じられている部分はなくはないが、内容的には充分楽しめる。Y.M.様には何とお礼を述べて良いやら、ひたすら感謝するばかりである。 ⑭は元々2010年1月にPapageno様より送って頂いたエア・チェックを持っていた。1980年12月12日にNHKがラジオ放送したものの記録だ。同じ年の演奏である⑬と⑮の内、内容は限りなく⑮に近い。リズム感よりスケールの大きさとウィーン・フィルの旋律群の歌い回しが印象付けられる演奏であり、聴き手によって好みが分かれるであろう。ただ、好き嫌いは別にして、こういう第7が演奏される事はそうそうないという事は確かである。私は⑮同様巨匠最晩年の貴重なモニュメントとして評価したい。これを下さったPapageno様にはひたすら感謝するのみである。 そして、2015年9月、ORFEOからこの⑭が発売。日本での発売元のキング・インターナショナルによればCD化のリクエストが多かったからだという。音質はPapageno様より送って頂いたエア・チェックでも充分満足出来る物だが、このORFEO盤では若干量感や透明感が増し、より臨場感を味わう事が出来る。特にⅡ楽章の美しさには思わず溜息が洩れ、終楽章後半の迫力には唸らされる。何はともあれ、巨匠最晩年の姿を伝える貴重なモニュメントが全国のCD店やネット等で容易に入手出来る様に成った事は誠に喜ばしい限りで、ORFEOには「よくぞ発売してくれた」と言いたい。 ⑮はベーム最後の来日時に昭和女子大人見記念講堂で行われたライヴであり、少年時代の私が強い印象を受けた演奏である。同じ日に行われた第二同様長い間CD化を待ち望んでいたが、両曲が1枚のCDに収録されて漸く発売された時には、本当に感慨深いものがあった。演奏そのものは、死を目前にした老巨匠が衰弱した肉体に気力を振り絞って立ち向かっていく様子がありありと伝わってくるのが逆に印象深い。正に朽ち倒れんとする巨木を目の当たりにしている心地がする。言い換えるならば、衰えはあるが、途方もなく大きな音楽が展開されている。もはや音楽的にみて一般的な名演の概念から外れた側面を持つ演奏であるという事は出来るが、一方で巨匠最晩年の姿を伝える感動的なモニュメントとして語り継がれるに相応しい演奏なのである。 何れにせよ、単に数が多いだけでなく、①〜⑮が各々存在意義を持つ演奏である事に間違いはない。 | |
| 交響曲8番ヘ長調Op.93 | |
| ① | |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1953年5月、ウィーン | |
| キング・レコード KICC 2302 | |
| ② | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1972年9月10日〜18日、ウィーン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) F00G 29056/61 | |
| ベートーヴェンがこの交響曲を完成させたのは1812年。歴史的にはナポレオンがロシア遠征に失敗した年として知られる。 私的にはゲーテと会見したり、「不滅の恋人」への手紙を綴ったりしているベートーヴェンだったが、創作ペースの落ち込みは彼の耳の病の進行ぶりを物語っていると同時に、経済的苦境も反映されている。彼の庇護者として有名だったロプコヴィッツ侯が劇場運営の失敗から破産して、ベートーヴェンへの年金が支給出来なくなってしまったのである。その為、彼は金策にも奔走しなければならず、創作どころではなかった。 そうした事もあって、1812年に完成したベートーヴェンの作品は僅かにこの交響曲とヴァイオリン・ソナタ10番のみであった。尤も、翌1813年も交響曲7番と『ウェリントンの勝利(戦争交響曲)』しか完成されておらず、人によってはこの時期のベートーヴェンがスランプに陥っていたと位置付けている。しかし、数が少ないとはいえ、何れも楽聖ならではの個性と存在感を持つ作品ばかりである事に変わりはない。 さて、完成された交響曲8番だが、これは第四以来久し振りのハイドン〜モーツァルト的様式に拠っている。しかし、此処にはベートーヴェンならではの独創性がたっぷり出ており、モーツァルト的様式を完全に我が物とした楽聖の姿が感じられる。第七の様なスケール感やダイナミックスの振幅はないが、リズムを前面に打ち出した作り等ハイドンやモーツァルトとは異なる、ベートーヴェンのオリジナリティーが存分に発揮されている。その好例として挙げられるのが2楽章。当時友人のメルツェルが開発中だったメトロノームを意識したこの愛らしい音楽こそ、本来陽性で冗談好きだったベートーヴェンの人間性が感じられるのである。 この交響曲で高い評価を受けているのはジョージ・セルだ。ハイドン〜モーツァルト様式をたっぷり踏まえつつ、リズムの独創性も確り出ており、それでいて決して機械的に流れない。知性と感情表現が見事な均衡を保っている名演なのである。 全集に含まれる②で、ベームはこの交響曲を大らかにまとめ上げており、その背後には矢張りモーツァルトへの揺るぎない愛情が感じられる。ウィーン・フィルもこの交響曲の持つモーツァルト的魅力をたっぷり引き出している。反面、優美な表情や様式美の魅力が濃い為、この交響曲におけるベートーヴェンの独創性、革新的側面はあまり感じられない。其処がベームらしいといえばベームらしい。この交響曲は『英雄』、第五、『田園』、第七、そして第九といったベートーヴェンの大作に比べると、指揮者によって極端な差が生じるという事が少ない。そうした中で、ベーム盤は確り独自の魅力と存在感を持っており、矢張りこの交響曲の代表的名盤の一つと言えるだろう。 ①は拙サイトを訪問して下さったY.M.様より頂いたコピーである。②程恰幅が大きく豊潤な味わいというものは感じないが、ベームのフォーマットはそう大きくは変わらない。何よりウィーン・フィルらしい美感がある。若干Ⅱ楽章のリズムがカッチリし過ぎていたり、Ⅲ楽章が速めのテンポの割に今一つ締まりが悪かったりする面はあるものの、充分魅力的な演奏である。録音も年代を考えれば、決して悪くはない。何れにせよ、長い間これを聴いてみたかったと考えていた私に、その機会を与えて下さったY.M.様にはひたすら感謝するばかりである。 | |
| 交響曲5、6番 | 交響曲7、8番 |