




BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。
交響曲35番〜41番(後期6大交響曲)①
| 交響曲35〜38番 | 交響曲39、40番 | 交響曲41番 |
| 交響曲35番ニ長調『ハフナー』K.385 | |
| ① | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1942年、ウィーン | |
| EMI SGR-8001 | |
| ② | |
 | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1951年4月9日、ベルリン | |
| TIM 220823-303 | |
| ③ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1957年8月25日、ザルツブルク | |
| ORFEO C 359 941 B | |
| ④ | |
 | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1959年10月1日〜3日、15日〜16日、ベルリン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) F00G 20003/14 | |
| ⑤ | |
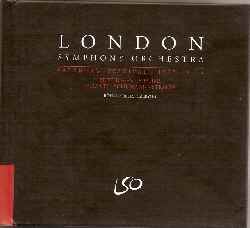 | ロンドン交響楽団 |
| 1973年8月5日、ザルツブルク | |
| ANDANTE 4CDsANDANTE-4983 | |
| ⑥ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1975年、ウィーン | |
| JOY CLASSICS JOYCD-9020 | |
| ⑦ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1980年6月27〜28日、ウィーン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) 3111-17 | |
| ⑧ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1980年8月30日、ザルツブルク | |
| ORFEO ORFEO R 891141 | |
| モーツァルトの交響曲中、とりわけ高い評価と人気を得て、幾多の巨匠から若手迄数多くの指揮者が演奏会で採り上げ、録音しているのは、この35番から始まる所謂”後期6大交響曲”である。これらはエジプトの大ピラミッド群宜しく、音楽史における不滅の文化遺産と称するべきものであり、正に人類の至宝に数えられよう。 この35番『ハフナー』は歌劇『後宮からの誘拐』K.384と同時期に書かれており、本格化したモーツァルトの魅力をたっぷりと味わう事が出来る。但し、これは本来交響曲として書かれたものではない。ハフナー家の祝典の為に作曲された6楽章からなるセレナードが原型である。新作交響曲の依頼を受けたモーツァルトだったが、『後宮』の作曲を中心に据えていた為、そちらに迄手が回らなかった。其処でセレナードから2つの楽章を削除し、楽器編成に手を加えて”新作交響曲”として発表したのである。言ってみれば”使い回し”な訳だが、交響曲として見事に完成されている事から、今ではこちらを採り上げる演奏家が圧倒的に多く、セレナードを採り上げる指揮者は少ない。交響曲ではないが、現在4楽章制で演奏されるクラシック音楽の代名詞であり、モーツァルト最大の人気作の一つとされる超有名なセレナード、『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』を思わせるものがある。 作品の規模はこれより前に書かれた33番や34番より大きいとはいえないが、内容の充実度が俄然高まっている点が、後期6大交響曲の一角を担う所以である。 交響曲全集を完成させ、師のワルターと共に20世紀最高のモーツァルト指揮者と評されるカール・ベームも、その特性をフルに発揮し、よく採り上げたのは、矢張りこの35番からという事になる。但し、この交響曲の持つ祝典的な華麗さを強調するものではない。寧ろ推進力溢れる筋肉質なスタイルとなっている。緩徐楽章の歌はあるが、全体を強固な一本の線が貫いている。それでいて、後味は如何にも爽快。そうした特徴は①〜④で味わう事が出来る。逆に言えば、既に①の時期にはベームの中でこの交響曲の演奏フォーマットが揺るぎないものになっていたという事だ。勿論、録音年代やオーケストラの音色の違い等があるから、①〜④が何から何迄同じという訳ではない。 ①はH.M.様より頂戴した戦時中のEMIへのスタジオ録音の一つである。録音は決して良くないが、同時期のブラームスなどに比べると、編成が小さい事もあり、内容的にはずっと楽しめる。多少量感に欠ける部分はあっても、推進力に満ち、爽快感に溢れる壮年時代のベームならではの名演となっている。随所に聴かれるウィーン・フィルならではの味がまた素晴らしい。特にⅡ楽章の美しさ、味わい深さは今尚充分に聴き手の心を捉えて放さないだろう。この演奏を下さったH.M.様には何とお礼を述べて良いか、本当に言葉が見当たらない。 ②と④はベルリン・フィルが相手という事もあり、共に筋肉質な響きと推進力が齎す爽快感に魅力を感じる。②は若干大味な部分はあるが、そうした不満を感じさせないだけの音楽的生命力を持っている。④はより堅固で完成度の高い仕上りが印象的だ。 ③はウィーン・フィルとのライヴという事で、管弦楽の美しさ、しなやかさを感じ取る事が出来る。ただ、録音が悪い事もあり、凝集力という点においては②や④に一歩譲る。 ⑤は晩年に入ってからのザルツブルク祝祭のライヴだが、ベームのフォーマットは①〜④と殆ど変わらない。ロンドン響も美しく、力強い演奏を繰り広げている。一方で、⑦や⑧を準備する風格も漂っており、充分存在を誇るに足る名演である。 ⑥は2009年8月にH.M.様より贈って頂いたCDである。DVDで発売されている映像と同一音源だが、音楽だけでも充分楽しめる名演である事に変わりは無く、聴き始めたら、その素晴らしさに溜息をつくばかりだ。晩年のベームならではのスケールの大きさと同時に活力の豊かさ、ウィーン・フィルの美感が聴き手を音楽の中に誘う。聴衆を伴っての収録だけに、臨場感もある。録音も外盤にしては上々の部類だ。元々公式に収録された音源だけに当然と言えば当然だが、演奏が素晴らしい上に、録音が或程度の水準を満たしていると、満足度はより高まる。これを下さったH.M.様には何時もの事ながら、何とお礼を述べて良いやら、言葉が見当たらない。 ⑦はベーム最晩年の録音であり、この演奏は巨匠の死後、追悼盤として発売された。此処には①〜④の様な堅密で、推進力に満ち、爽快感溢れる仕上りとは別の魅力が感じられる。音楽運びが落ち着いたものとなり、恰幅の大きい、そして極めて美しい演奏となっている。これはオケがウィーン・フィルという事と無関係ではない。壮年期のベームとは別種の音楽性の豊かさを湛えた⑦もまた、”モーツァルト指揮者”カール・ベームの魅力を後世に伝えるに足る名演だと言えよう。 ⑧は2008年11月にH.M.様より頂戴した米国のカール・ベーム・ファン・クラブのCD−R(WALL Wall 7008-9)。録音年代の割にモノラルというのが残念だが、流石に演奏は素晴らしい。嘗ての様な力強い響きや、推進力には欠けるものの、ニュアンスの豊かさ、包容力の大きさは内容的な手応えをたっぷりと感じさせてくれる。⑦同様、壮年時代とは異なる最晩年のベームならではのモーツァルトの魅力が味わえると言える。尚、同日に演奏された29番同様、この⑧もⅡ楽章の提示部が繰り返されており、ベームの『ハフナー』としてはレアなケースとなっている。何れにせよ、これを下さったH.M.様には心の底から感謝を捧げたい。 尚、⑧に関しては2014年10月にORFEOからCDが出た。H.M.様から頂いたCD−Rがモノラルだったのに対し、こちらはステレオ録音という事で、ザルツブルク祝祭小劇場の残響がよく捉えられており、ニュアンスの豊かさが増し、より臨場感が感じ取れる様に成った。尤も、残響が大きく成った分、時折前の音と次の音が混濁気味に成るのが若干残念ではあるが。何れにせよ、CD−Rのモノラル音源で聴くしか無かった演奏が、普通のCD店で容易に入手する事が出来る様に成ったのは誠に嬉しい限りであり、是非共一聴して欲しい。 | |
| 交響曲36ハ長調『リンツ』K.425 | |
| ① | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1950年9月、ウィーン | |
| ユニヴァーサル(DECCA) 476 154-4 | |
| ② | |
 | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1966年2月8日〜9日、11日〜14日、ベルリン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) F00G 20003/14 | |
| 音楽史上最大の天才、モーツァルト。彼の長所の一つとして、偉大なる先達の作風を見事な迄に自身に吸収し、昇華させる事が出来たという事が挙げられよう。この交響曲で天才はハイドンの長大な序奏付スタイルを導入している。全体の様式美にも優れ、オペラティックな素材が随所に聴かれる等、モーツァルトならではの魅力が満載だ。 ベームは晩年にウィーン・フィルを指揮して、モーツァルトの後期6大交響曲を録音していたが、結局この交響曲は録音される事なく巨匠は世を去ってしまった。ベームの晩年のモーツァルトは、壮年時代とは別種の魅力を感じさせただけに、残念であるが、私の所持する2種類の録音自体は各々素晴らしい魅力を持っている。 ①はオケがウィーン・フィルという事もあり、ガッチリした構成よりは寧ろ、自由度の高い演奏となっている。ラトルら現代の指揮者達が羨望の眼差しを向けるウィーン・フィルが”真”のウィーンを体現していた時代の響きに浸る事が出来る。 これと正反対と言えるのが②だ。こちらはベルリン・フィルという事もあり、より音楽的本質に専心した内容になっており、構成美が最大の魅力になっている。極めて充実度の濃い名演だ。 | |
| 交響曲38番ニ長調『プラハ』K.504 | |
| ① | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1954年11月、ウィーン | |
| ユニヴァーサル 00289 477 5296 | |
| ② | |
 | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1959年10月1日〜3日、15日〜16日、ベルリン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) F00G 20003/14 | |
| ③ | |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1979年3月10日、12日、ウィーン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) 3111-21 | |
| モーツァルトやハイドンはベートーヴェンとは異なり、自らの作品に番号を付けるという事はしなかった。1曲1曲自らの意思で、熟考を重ねたベートーヴェンとは異なり、モーツァルトやハイドンの時代、彼等の作品は他人からの作曲依頼を引き受けて書かれていたから、現在自分がどれだけの数の作品を書いているかなどという事は考えていなかった。その為、通常であれば存在しなければならない筈の37番の交響曲が欠けている。これはモーツァルトの死後、その交響曲が何度か整理される過程で、37番が彼の作ではないと判明したからである。さりとて、今更モーツァルトの交響曲の番号を整理し直す事は人々の混乱を招くだけだ。其処で37番が欠番になったのである。 さて、38番『プラハ』に関してであるが、これはモーツァルトが少年時代より慣れ親しんできた3楽章制の交響曲の集大成であり、数多いニ長調の交響曲の最後の作品という事で、一般的な評価も39、40、41番の所謂”モーツァルト3大交響曲”に匹敵する評価と人気を得ている。序奏は36番『リンツ』から更なる進化を遂げ、オペラの序曲を思わせる劇的性格を具えている。随所にオペラとリンクしている部分が見受けられ、特に終楽章は歌劇『フィガロの結婚』と密接な関連性がある。 ベームには現在3種類の『プラハ』の録音が存在するが、各々が素晴らしい存在意義を持っており、実演であまり採り上げなかったのが不思議な程だ。それでは演奏について語ろう。 ①はウィーン・フィルの美しさに魅力を感じる。その為、音楽の流れは緩みがないが、②の様に骨格のガッシリした強固な印象は受けない。録音のせいもある。しかし、推進力や力強さも充分に感じられ、ベームならではの存在感は示されている。 ②はほぼ同じ時期に録音された『ハフナー』や『ジュピター』同様、筋肉質の推進力溢れる名演で、何ともいえぬ爽快感がある。両端楽章のたたみかける様なコーダも含め、非常にドイツ的で男性的な逞しさを感じさせるモーツァルトである。勿論、オペラ指揮者としても『フィガロ』や『コシ』で幾多の伝説を刻んでいるベームだけに、劇的な部分の緊迫感もたっぷりある。しかも、様式の中に総てが見事に収められている。これは正に壮年時代のベームのモーツァルト演奏の典型であり、何度聴いても素晴らしい。 ③はベーム最晩年の録音という事で、緊張感や推進力よりは全体を大きく包み込む様な仕上りになっている。これも如何にも晩年のベームのモーツァルトの典型を示しているといえよう。序奏がモーツァルトというよりはベートーヴェン的重厚さを感じさせ、デモーニッシュな翳りを漂わせているのも、晩年のベームならではで、①や②とはまた別の魅力がある。 | |
| 交響曲35〜38番 | 交響曲39、40番 | 交響曲41番 |