




BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。
シャーロック・ホームズ②

世界的に人気を博したジェレミー・ブレット主演のTV版『シャーロック・ホームズの冒険』
|
ホームズの生還 1901年に推理小説史上最高傑作に推す人も少なくない長編『バスカヴィル家の犬』を発表したドイルだが、未だに世間的には既にホームズは死んだ事になっており、あくまで彼の生前の活躍をワトスンが思い出して発表したという体裁をとっていた。そんなドイルが1903年から1904年にかけて突然ホームズ譚を立て続けに発表したのだから、世界中が驚き、そして熱狂を以て迎えた。この時ストランド誌に掲載された13の短編を収録し、1905年に刊行されたのが『シャーロック・ホームズの生還』である。そして、この『生還』は今でも『冒険』と共に最も愛好されているホームズ譚を収録した短編集となっている。また、ドイルが集中的に短編を連載した最後の作品集でもある。以後、ドイルはホームズ譚を集中的に連載する事はせず、時折思い出した様に発表するに過ぎなかった。別の見方をするならば、創作力の枯渇を防ぎ、常に創作意欲を保ち、一作一作を大事に書き上げる為のドイルの英断とも言えるが。さて、それでは『生還』の内容について語ろう。先ずは「空家事件」。これこそは、世間的に既に死んだ事になっていた不世出の名探偵、シャーロック・ホームズが鮮烈なる戦列復帰を果たした作品である。冗談はさておき、『回想』に収録された「最後の事件」が発表されてから実に10年。ドイルは苦心しつつも、英雄の死後、ホームズ譚が今迄世に出なかった理由を最初に述べ(『バスカヴィル家の犬』を除き)、それからワトスンとホームズの劇的な再会を描く。これはホームズ譚屈指の名場面だ。勿論、詳細に検討すれば、矛盾はなくはない。しかし、そんな細かいところに突っ込みを入れるよりも、ホームズが生きていたという事自体が世界中を狂喜させた事は間違いない。そう、それが一番重要な事なのだ。復帰を飾る事件の相手がこれまたモリアーティ教授の残党で、効果満点。これはもう、推理小説としてどうとかいう作品ではない。寧ろ、ホームズが劇的復帰を果たした記念碑として永遠に記憶されるべき作品であると言えよう。 次は「ノーウッドの建築業者」。これは江戸川乱歩がトリッキーな内容を絶賛した事でも知られている。「空家事件」がホームズ久々の顔見世興行的作品だとすると、こちらは推理物としてのホームズ譚の魅力に溢れているのだ。謎の構成やホームズ譚ならではの芝居っ気たっぷりの演出効果も相俟って、正に読み応え充分の傑作に仕上がっている。 次は「踊る人形」。これは暗号解読に妙味があり、ドイル自身も気に入っていた作品の一つ。推理物としては勿論、人間ドラマにも一読の価値があるホームズ譚ならではの逸品だ。 次は「怪しい自転車乗り」。現代のストーカーに通じる内容だが、其処はホームズ譚。謎の構成は勿論、人間ドラマの面白さで魅せてしまう。そして、それが万人の共感を呼ぶのである。 次は「プライオリ・スクール」。これはドロシー・セイヤーズが激賞し、ドイル自身自作のベスト12編の一つに選んでいる。生徒の失踪事件に絡む人間ドラマがホームズによって明らかにされていく。 次は「ブラック・ピーター」。常に真相を極めんとするホームズの姿勢が真犯人を暴き出す。 次は「恐喝王ミルヴァートン」。これは推理物ではない。ホームズとワトスンの冒険譚といった趣がある。しかし、これはこれで充分読者を魅了する力を持っているところが、ホームズ譚の凄さであろう。 次は「6つのナポレオン胸像」。これは若しかすると『生還』の中では一番有名かも知れない。私もこれは「赤髪連盟」や「まだらの紐」などと共に小学生中学年の頃から知っていた。謎の構成、そして劇的演出効果。ホームズ譚の魅力が鮮やかに炸裂している。私が語る間でもなく、これは知っている人が少なくないのではなかろうか。 次は「3人の学生」。カンニングを題材にした作品だ。ホームズ譚の魅力が殺人事件だけに止まらない事件のヴァリエーションの豊富さにある事は疑い様がないが、それにしてもこの時代にこの着眼点。ヒューマニズム溢れる解決も含め、ドイルの非凡さを改めて思い知らされる。 次は「金縁の鼻眼鏡」。材料の多さや構成等推理物としての魅力に溢れた作品だ。 次は「スリー・クォーター失踪事件」。ケンブリッジ大学のラグビー部主将の失踪の謎をホームズが解き明かす。スポーツ万能のドイルならではの題材と言えるし、謎の構成や結末の意外性を含む人間ドラマにも魅力があり、敵役にも大物感があって読み応えがある。 次は「僧房荘園」。ホームズ譚ならではのヒューマニズムが読後の満足感を齎す佳品。 そして「第二の血痕」。実はドイルは前作を以て連載を打ち切りにする予定だった。しかし、その三ヵ月後にこれを発表している。その理由として、ドイルはワトスンの姿を借りて、既にホームズが世間から騒がれるのを嫌い、隠居して学究生活と養蜂に没頭しているが、短編集の最後を飾るに相応しい「第二の血痕」を公表する事をホームズ自身が許可したと書いている。国家の重要機密を扱った国際的事件はホームズ譚としては初めてではないが、何と言っても芝居っ気たっぷりの結末が爽やかな後味を残す。この人間味こそがホームズ譚の魅力なのだ。 ドイルは嘗てにそう見劣りしない作品群を此処に送り出した。人間ドラマに関してはより味が増したとすら言える。これこそ、単なる謎解きには終わらせないというドイルの文学者としての誇りと器量の大きさを物語っていよう。だからこそ、ホームズ譚が時を超えて愛され続けているのである。 恐怖の谷 1914年から1915年にかけて書かれた長編が『恐怖の谷』である。『緋色の研究』と同じく二部構成になっているが、『緋色の研究』の二部は悲恋文学とも称するべき内容であったのに対し、この『恐怖の谷』では一部、二部共に推理小説として成立し得る構成となっていて、ディクスン・カーの様にこれを長編の最高傑作とする人も少なからずいる。反面、数々の矛盾が指摘されている問題作でもある。例えば、「最後の事件」で初めて悪の帝王モリアーティ教授の名を知った筈のワトスンだが、この作品ではモリアーティ在世の事件という設定であり、ホームズとモリアーティの駆け引きが演じられている事。事件の年代自体も諸説ある。ただ、こんな事はホームズ譚ではよくある事だ。推理物としての面白さ、物語としての面白さが何時の間にかそうした細かいところなんてどうでも良いという気にさせてくれる。何より、マンネリに陥るどころか、構成面での新境地を切り開いたばかりでなく、ホームズならではの劇的演出が随所に効果を発揮している事を考えると、ドイルの凄さを改めて思い知る事が出来る。現代のサスペンス・ドラマなんてひどいものだ。マンネリな展開が多いし、ラストは決まって海沿いの崖若しくは山中の崖か港。ドイルは違う。常に異なる仕掛けや舞台、そして演出効果を考えている。常に格調の高さがあるところも他の追随を許さない。言い換えると、シェイクスピアの遺伝子を継承した推理小説なのだ。だからこそ、ホームズが千両役者足りえるのである。勿論、ドイルもネタに困って同じ素材を用いる事はある。しかし、異なる料理に仕上げる事が出来る点がこの人の非凡なところだ。そして、それをまざまざと見せ付けているのが『恐怖の谷』なのである。個人的にはホームズ譚の長編では『バスカヴィル家の犬』が最も好きだけれど、『恐怖の谷』の独特の印象はまた別の意味で忘れ難いものがある。シャーロック・ホームズ最後の挨拶 これ迄ドイルが世に送り出してきたホームズ譚の短編集は何れもほぼ一年に渉って集中的に連載された作品をまとめた物であった。しかし、この第4短編集『シャーロック・ホームズ最後の挨拶』は本来『回想』に含まれていた1893年の「ボール箱」と、1908年から1917年にかけてストランド誌で散発的に発表された短編8編を収録し、1917年に刊行している。公人としてより多忙になっていた上、自らの本分は歴史文学にあると考え続けてきたドイルにとって、幾ら自らの看板作品と世間が見なそうとも、流石にホームズ譚を連載し続ける意欲はなかった。しかし、ドイル自身、もはやシャーロキアンを無視する事は出来ず、定期的に短編を発表する事で、その熱狂に報いたのである。別の見方をすると、連載し続けるという事は極めてマンネリに陥り易い。それを避ける為にドイルが一作一作を慎重に書き上げる様になっていったとも考えられる。先ず最初に収録された「藤荘」。これは1908年9月と10月に発表された二部作である。第一部が「ジョン・スコット・エクルズ氏の不思議な体験」、第二部が「サン・ペドロの虎」となっている。多くの人が指摘する様にブードゥー教が絡んだ展開は『緋色の研究』を思い出させるものがあるし、怪奇性も初期の作品群を彷彿とさせるものがある。しかし、短編でありながら二部構成にする等、これ迄のホームズ譚には見られなかった要素等も盛り込まれ、ドイルがマンネリ化を恐れ、色々と頭を悩ませていたであろう事は容易に想像出来る。 次は「ボール箱」。これは既に述べた様に、本来は『回想』に収録される予定だったが、ドイル自身が内容が不道徳であるとして、削除したものである。しかし、それがどういう訳かこの『最後の挨拶』には収録されている。何れにせよ、1893年1月に発表されたこの短編は、一人の人間が嫉妬によって破滅に向かい、異常な行動をするという点において、確かに当時の他のホームズ譚の中にあっても生々しい。今では不倫絡みの殺人を題材にした推理小説はよくあるが、当時としては珍しい内容だったと思うし、ドイル自身の倫理観や正義感に相容れぬものがあった為、『回想』から削除したのであろう。当時は今と違って不倫は世間から白眼視されていた。では、何故『最後の挨拶』にはこの作品が収録されているのかと考えると、ドイル自身がうら若いジーン・レッキーとの不倫を経験したからではなかろうか。或いは、ストランド誌の愛読者達から何故「ボール箱」だけ短編集に収録されないのか、といった質問が相次いだのかも知れない。真相を語る事が出来るのはアーサー・コナン・ドイルその人しかいない。 次は「赤輪党」。これは1911年3月と4月、二部に分けて発表された短編である。第一部の序盤は何処となく「赤髪連盟」を思い出させるものがあるが、謎の下宿人の行動、秘密結社の存在等素材や構成面でのドイルの工夫が随所に感じられ、同じ様な仕上がりにはなっていない。後、個人的には「どうして此処で手を引かないんだい?何か得する事でもあるのか?」と尋ねるワトスンに、「何か得するって?いわば芸術の為の芸術さ。患者を治療する時には、君だって医療費の事なんて考えないで、病症を研究している訳だろう」と語るホームズの台詞が忘れ難い。此処にホームズの、そしてドイルの美学が集約されている。それが世界中のシャーロキアンを虜にするのである。 次は「ブルース・パーティントン設計書」。これは1908年12月に発表された。此処には久し振りにシャーロックの兄、マイクロフトが登場する。そして、相変わらず精力的に動き回る事の苦手な彼は、弟のシャーロックに事件解決を依頼する。それは英海軍の潜水艇の設計書が紛失したというものであり、国家の重要機密が外部に洩れる危機を孕んでいた。トリック物としての読み応え充分な逸品であり、エピローグでホームズが授かる栄誉を含め、当時の英王室を彷彿とさせる描写にも注目だ。 次は「瀕死の探偵」。これは1913年12月に発表された。恐らく『最後の挨拶』の中では最も有名な短編である。何と言っても、此処では”千両役者”ホームズの芝居と、ワトスンとの友情が見物だ。結果は分かっていても、何度でも読み返したくなる鮮やかさと微笑ましさがある。短いながら、発想の面白さ、演出、そしてヒューマニズム何れも具えたホームズ譚の魅力が詰まった逸品だ。 次は「フランシス・カーファクス姫の失踪」。これは1911年12月に発表された。推理物としての構成は勿論、ホームズ譚ならではの芝居っ気が何とも言えない魅力を醸し出している。 次は「悪魔の足」。これは1910年12月に発表された。ドイルのヒューマニズムが色濃く滲み出ている作品である。 そして「最後の挨拶」。これは1917年9月に発表された。珍しくワトスンによる口述ではなく、三人称によって書かれている事でも知られている。既に探偵業を引退して、養蜂家としてのんびり隠居暮しをしていたホームズだが、第一次世界大戦真っ只中の欧州の情勢が久々に彼の活躍を必要とする。英国首相自らの依頼という事で、ホームズも断れなかったのだという。推理物としては勿論、当時の情勢を随所に感じさせる描写、そしてホームズとワトスンとの不変の友情、相変わらず見事な芝居等流石の仕上がりになっている。ドイルはこの後も断続的にホームズ譚を発表していくが、何れもこの「最後の挨拶」より前の年代に扱った事件という設定になっており、事実上、この「最後の挨拶」がシャーロック・ホームズの人生において最後に扱った事件という事になる。そして、題名通り、この作品はホームズ譚の”カーテン・コール”と称するに相応しい内容となっている。 『最後の挨拶』は推理小説のベストを争う様な作品が少ない事もあり、短編集の中では次の『事件簿』と共に、地味な存在と見なされている。しかし、ひとたび目を通してみると、忽ちホームズ譚特有の魅力が読者の心を鷲掴みにする事は間違いない。長年執筆し続けてきたからと言って、作業やマンネリに陥ってはいない。常に新しい道を模索せんというドイルの姿勢が感じられる。決して駄作・凡作には終わらせていない。だからこそ、総てのホームズ譚が推理小説史上に残る至宝として崇め奉られてきたのである。逆に推理物というカテゴリーを越えた魅力がホームズ譚を”聖典化”させる要因となっている事も否定出来ない。それがホームズ譚の比類なき個性という事になるのだが。 シャーロック・ホームズの事件簿 ホームズ譚最後の短編集『事件簿』。これは『最後の挨拶』同様1921年から1927年にかけてストランド誌上で散発的に発表された短編12編を収録し、1927年に刊行したものである。先ず「高名の依頼人」。これは1925年2月と3月に発表された。ホームズ譚にしばしば登場する英王室絡みの事件。何処となく「瀕死の探偵」を思わせる仕掛けがあるが、物語の性質や展開が全然違うので、全体的には似て非なる作品に仕上がっている。 次は「白面の兵士」。これは1926年11月に発表された。ホームズ譚といえば、その殆どはワトスン博士が語り部であるが、ごく稀に著述者が異なる事がある。この作品は、ホームズが日頃ワトスンの記述に対してあれこれ言うものだから、「自分で書いて見給え」とワトスンに言われたホームズが自ら執筆するという内容になっている。ワトスンが記述すると、事件は謎に包まれ、展開は二転三転し、最後に霧が鮮やかに晴れるかの様な劇的効果がある。或意味文学的。しかし、此処ではホームズ自身が語っている為、内容は理知的であり、筋道が明確に示されている。だから、推理物としての面白味は後退している。その代わり、”超人”ホームズの頭の中や内面を具体的に垣間見せてくれるところが何より新鮮であり、それが何よりの魅力となっている。これはドイルからシャーロキアンへのファン・サービス的作品だと言えよう。 次は「マザリンの宝石」。これは1921年10月に発表された。「最後の挨拶」からほぼ四年振りとなる短編であり、「最後の挨拶」同様三人称による記述になっているところが面白い。その為、三人称の物語は一体誰が書いたという設定なのかという議論がシャーロキアンの間では成されているらしい。この作品では推理よりホームズ譚特有の芝居がより強い印象を残す。そして、この芝居に関してもシャーロキアンの間で色々と議論が交わされているらしい。それを此処で語ってしまっては元の子もないので、この辺で。 次は「三破風館」。これは1926年10月に発表された。一見クールなホームズだが、その根底にはヒューマニズムが流れている。そして、その「大岡裁き」的要素もまたホームズ譚の魅力なのである。また、女性に対しては常に紳士たれ、というホームズの美学が感じられる。ドイル自身の騎士道精神の表れであろう。 次は「吸血鬼」。これは私の所有する新潮社版ではストランド誌上で発表される事なく、短編集の為に書き下ろされたみたいな事が書いてあるが、Wikipediaでは1924年1月に発表されたと、ある。どちらが正しいのかはよく分からない。内容はワトスンの知己から持ち込まれた怪奇性のある事件だが、心理・精神の領域から切り込み、衝撃的な犯人を暴き出す佳品である。 次は「3人ガリデブ」。これは1925年1月に発表された。内容的には「赤髪連盟」の系譜に属する物語だが、同じ様な仕上がりにはなっていないところが流石である。また、股を撃たれたワトスンを心配し、「ワトスン君、やられたのじゃなかろうね?後生だから、そんな事はないと言ってくれ」と言い、更に犯人に対し「若しワトスン君を殺しでもしていてみろ、生きてこの部屋を出しはしなかったんだ」と叫ぶホームズの姿に、彼の人間味とワトスンとの熱い友情が感じ取れる。ドイルの創造の源泉は未だ枯渇していない。それどころか、素材の特異性や展開面での奇抜さは別にして、構成面での円熟、内容的な味わい深さは増している様にも思われる。 次は「ソア橋」。これは1922年2月と3月に発表された。人間の心理・精神状態に着目した作品で、トリックに新機軸を打ち出しているところもドイルの衰えぬ創作力を物語っている。 次は「這う人」。これは1923年3月に発表された。怪奇性のある人間の行動に潜む深層心理を飼い犬の行動から暴き出すホームズの手腕は相変わらず素晴らしい。 次は「獅子の鬣」。これは1926年12月に発表された。「白面の兵士」に続いて掲載されたホームズによる著述物である。此処では何と言っても真犯人の意外性に新機軸を打ち出している。次々と色々なアイディアを盛り込んでいくドイルには本当に驚嘆させられるばかりだ。そして、それはドイルの広汎な知識と豊富な経験を物語るものでもある。 次は「覆面の下宿人」。これは1927年2月に発表された。ホームズ自身が解決した事件ではなく、或女性が自分の身の上に起った惨劇についてホームズとワトスンに語るという内容である。ホームズ譚の中で特に短い作品だが、物語の特異性、そしてドイルならではの印象的な演出が読者に鮮烈な印象を残す。 次は「ショスコム荘」。これは1927年4月に発表された。時間軸としては『最後の挨拶』の「最後の挨拶」がホームズの手掛けた最後の事件という事になるが、ドイルが発表したホームズ譚の正真正銘の最後の作品がこれだ。「銀星号事件」以来の競馬絡み、しかもこの作品では英ダービーという至高のレースの断然人気馬に絡む物語になっている。推理物としては「銀星号事件」の方が断然面白い。しかし、この「ショスコム荘」の怪奇性や人間悲劇は充分に読者に忘れ難い印象を残すであろう。 そして「隠居絵具師」。これは1927年1月に発表された。此処ではホームズは他の事件を手掛ける為、ワトスンが代理として調査に赴く事になる。ホームズはワトスンの報告を聞いて助言するという按配である。其処から先は読んでからのお楽しみといったところ。如何にもホームズ譚らしい芝居っ気が冴え渡る作品だ。 空前絶後の名探偵、シャーロック・ホームズ。彼の活躍はこの短編集を以て終わった。しかし、その存在は推理小説というジャンルを世界的に根付かせ、幾多の模倣を生んだだけでなく、警察の実際の捜査にも少なからぬ影響を与えている。この『事件簿』における精神・心理面でのアプローチなどはプロファイリングへの道を切り開いていると言えるだろう。勿論、誇り高く、紳士的、変装上手で演技上手、ヴァイオリン上手、かつ人間味も垣間見せる一方で、薬物に手を出す等変人じみた面も持つ彼のキャラクターの魅力が傑出している事は言う間でもないし、謎の発想や構成、そして文学的情景描写や演出等が他の追随を許さぬホームズ像を大衆に広く根付かせた事も確かだ。一般的にはワトスンがドイルの分身と言われているけれど、ホームズもまたドイルの分身であった。ホームズの中に流れる騎士道精神や愛は正にドイルその人と重なり合って行く。だからこそ、ホームズが永遠のヒーローとして世界中で愛され、新たなシャーロキアンを生み出し続けているのだ。 その他ドイル作品 「アーサー・コナン・ドイル=シャーロック・ホームズ」のイメージは世界的に動かし難いものがあるが、既に何度も語っている様に、ドイルにとって、ホームズ譚はあくまで余興であり、彼の本分は歴史文学にあると自らは考えていた。その代表的な作品の一つは『マイカ・クラーク』であるが、日本では殆ど知られていない。私も読んだ事がない。翻訳本があるのかどうかさえ分からない。それだけホームズ譚の印象が強過ぎるという事だろう。他では『白衣の騎士団』等があるが、歴史ロマンのジャンルで一番有名なのは『勇将ジェラールの冒険』『勇将ジェラールの回想』であろう。特に英国では不世出の歴史的名馬、ブリガディアジェラード(ブリガディア・ジェラード)にその名が用いられている程の知名度を誇る。他にも、今尚世界的に知られているホームズ譚以外のドイル作品が幾つかある。例えば少年時代に大いに影響を受けたジュール・ヴェルヌを開祖とするSF小説の分野。恐竜のいる秘境を探検する『失われた世界(ロスト・ワールド)』はハリウッドで何度か映画化された程のSFアドヴェンチャーの傑作だし、他にも『マラコット深海』『毒ガス地帯』『霧の国』等が知られている。何れもドイルの見事な筆致でそれぞれの世界に誘ってくれる。 他では怪奇物やSF物を収録した幾つかの短編集。これは新潮社から三集迄出ているが、ドイルならではの筆致が印象的な作品が幾つもある。個人的には「魔女狩り」の時代の拷問の光景をドイルならではの想像力の世界で描いた『皮の漏斗』が特に忘れ難い。 何れもホームズ譚だけに止まらない作家アーサー・コナン・ドイルの魅力に溢れており、一読の価値がある。 |
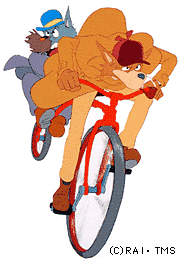
犬達が活躍する活劇色の濃いアニメ、宮崎 駿版『シャーロック・ホームズの冒険』