| 交響詩『ドン・ファン』作品20 |
 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1970年、ユニテル制作 |
| ドリームライフ DLVC-1172 |
2000人近い女性を口説いた伝説的人物、ドン・ファン。この色事師を題材にした作品はモリエール、プーシキン、バイロン、バーナード・ショーら多くの作家が手掛けている。音楽史においてはモーツァルトの『ドン・ジョヴァンニ』が有名だ。この原型となっているのは17世紀のスペインの劇作家モリーナによる物で、女性遍歴を重ねた挙句、地獄落ちするという結末は、多くの人々に強烈な印象を残した。モーツァルトも地獄落ちの場面をピークに据え、音楽史上類を見ないデモーニッシュな表現を生み出した。
リヒャルト・シュトラウスはモーツァルティアンとしても有名だったから、当然『ドン・ジョヴァンニ』は知っていたし、愛していただろう。実際彼は愛弟子のベームに、『ドン・ジョヴァンニ』一幕のフィナーレのレポレロが仮面を被った3人を招き入れ、仮面の三重唱が始まる直前のアダージョ2小節に対して、自らの楽劇3篇を差し出してもよいと思っていると語っている。
即ち、シュトラウスはモーツァルトに勝負を挑もうなどという僭越な考えは持ち合わせてはいなかった。比較される事は承知していただろうが、彼は歌劇ではなく交響詩という異なるジャンルで、異なるプロットを原案とし、神童とは異なる独創性を獲得したのである。
シュトラウスがインスピレーションを得たのは、ニコラウス・レーナウ(1802〜1850)の詩であった。既に欧州ではキリスト教に懐疑的な人物が出現し始めており、レーナウはドン・ファンが神によって罪を裁かれ、地獄に落ちるのではなく、自ら生きる気力を失って死を選ぶという結末にしている。それは様々な恋愛を楽しむというよりは、真実の愛を求めての遍歴であり、肉体的官能だけでは決して得られない理想の愛、永遠の愛であった。その絶望こそが彼に自ら死を選ばせる。そして、シュトラウスは正にそうしたドン・ファンの内面を抉り出したのである。一見派手な”快楽の嵐”は、理想の愛を求めんとひたすら生を駆け抜けていくドン・ファンであるが、その後に現れる憧憬に満ちた”女性的なるもの”でドン・ファンの真の胸の内が暴露されるのである。そして再び思いを満たさんと気力を漲らせるものの、最後は絶望の闇の中に消えていく。
大指揮者カール・ベームはリヒャルト・シュトラウスの愛弟子として、20世紀演奏史上その絶対的権威と称されてきた。そのベームによる『ドン・ファン』の映像がDVD化された。この事が何を意味するかは一寸した音楽好きなら理解出来るだろう。
シュトラウスはベームに自らの作品に関して一切の虚飾を捨て去る様に注文している。そして、ベームは師の要求に応えんと、外面的要素には目もくれず、ひたすら作品の本質を抉り抜いて来た。『ドン・ファン』も例外ではない。ベームの棒にかかると、この交響詩はドン・ファンの真情を伝えるものとなり、カラヤンの様な華麗さやショルティの派手さとは全然別の内面の充実度の濃さが魅力となる。そうした意味ではフルトヴェングラーと共通性があるが、フルトヴェングラーの様に全体的にデモーニッシュな風貌を具えている訳ではない。ベームは生を謳歌せんとする部分では寧ろ健康的である。各部分での真情が過不足なく、そして緩み無く再現され、クライマックスから絶望的な死に至る迄強固な芯が貫かれている。特に1957年に嘗ての手兵ドレスデン国立管を率いたモノラルは、音こそ今一つながら、ドン・ファンの真情がストレートに、そして生々しく伝わって来る。その他にもベームには複数の『ドン・ファン』が存在し、各々高い評価を得ている。ベルリン・フィル盤は音楽的完成度の高さが傑出しているし、1977年のウィーン・フィルとの来日公演のライヴも、宇野功芳氏などが「フルトヴェングラーに匹敵する唯一の演奏」と絶賛している。私はドレスデンとの1957年盤こそ空前絶後の『ドン・ファン』だと考えているが。まあ、CDに関しては「CD編」の方で述べているので、そちらを参照して頂きたい。
そのベームによる『ドン・ファン』の映像だ。期待するなという方が無理というものだろう。尚、このディスクには最初に作品解説があり、その後リハーサルが収録されている。リハーサルは例によってベームらしく音の調整に明け暮れている。強弱とか微妙なテンポのずれとか……。何故そうしなければならないのかは言わない。総てはベームの胸の内にある。彼は説明し過ぎて管弦楽をがんじがらめには決してしない。あくまでアンサンブルを整えるべく訓練しているといった趣がある。ベーム自身、訓練は厳格にしなければならないが、実際の演奏にあたっての花は残しておかなければならない、練習のし過ぎは不足と同様よくない、と述べているが、確かにその通りだ。細かく練習はするけれども、それは総てオーケストラの状態を万全に保つ為のもので、感情面での注文はない。これこそが実演でのベームの花と言えるもので、競馬の調教師や騎手同様、レース前に馬を万全の状態に持って行くのに似ている。ウィーン・フィルのメンバー達も心得たもので、苦笑しつつもベームの言う通りにしている。
そして本番。冒頭から気力が漲り、推進力に満ちた音楽が溢れ出す。それは外面的なものではなく、内から湧き上がる様な充実度の濃さがある。続く”女性的なるもの”のヴァイオリン・ソロの素朴な味わいも良い。ドン・ファンの第一主題も永遠の愛を求めんとするドン・ファンの真情に満ちている。中間、オーボエ、フルート、クラリネットらが次々と奏する憧憬に満ちた永遠の愛の姿もまた心に染み入る。微妙な表情の移り変わりに本当に味がある。就中、オーボエがやや古びた音を出しているのが特に印象に残る。耳に快く、美しい女性の姿を彷彿とさせるという事ではカラヤンだが、こういう心が滲み出てくる様なものは感じられない。この美しい音楽が静寂の中に消え入らんとして後、急激に盛り上がり、ホルンであまりに有名なドン・ファンの第二主題が出る所がまた素晴らしい。ウィンナ・ホルンに酔わされる。クライマックスの盛り上がりも1957年のドレスデン盤の様な物凄い生々しさはないが、重量級の破壊力があり、決闘のさなか、突如自らを剣で貫くドン・ファンの思いが浮かび上がる。その後の絶望感漂う死の描写もフルトヴェングラー程デモーニッシュではないが、死に行くドン・ファンの胸の内が伝わって来る。これがカラヤンやショルティ辺りだと、映像で死んでいくドン・ファンを観ている様な感じになる。尤も、カラヤンやショルティは外面的スタイルの中では傑出しているが。後はどちらのスタイルが好きかという個人の感性の領域だ。ただ、ベームがシュトラウスの愛弟子であり、信頼されていた事は忘れてはなるまい。
何れにせよ、見せかけだけの派手さや格好良さばかりを追求している様なシュトラウス演奏が増える中、こういう内容の充実を感じさせる演奏は誠に貴重で、個人的には矢張りベームのシュトラウスはモノが違う、と感じた。 |
| 交響詩『死と浄化(変容)』作品24 |
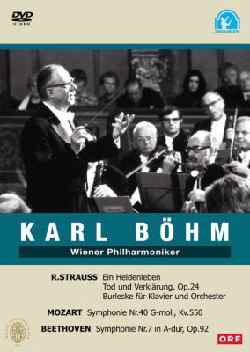 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1963年5月19日、ORF制作 |
| ドリームライフ DLVC-1211 |
ベームがR・シュトラウスの愛弟子であり、「音楽的遺言」を託された程信頼されていた事は彼を知る世代なら誰もが知っている。それ故、大指揮者カール・ベームといえば、R・シュトラウスの絶対的権威と見なされ、管弦楽曲も楽劇も大量の録音が遺されている。
しかし、こと映像に関する限り、そのラインナップに寂しさを感じていたのは私だけではあるまい。特に交響詩に関しては上記の『ドン・ファン』が存在するだけであった。
そうした私の思いが天に通じた訳ではないだろうが、2010年3月、漸く世に出たのが今回の『死と浄化(変容)』『英雄の生涯』『ブルレスケ』である。
尤も、嘗てこれらの映像はLDで出ていたらしい。また、『ブルレスケ』を除く二曲はCD化もされている。しかし、私にとっては初めて観る(聴く)映像だし、CDとDVDで音の具合が違うという事もしばしば体験しているので、今回も大いに期待を抱いてディスクを鑑賞した。
それは私の期待以上の出来だった。演奏の感想に関しては概ねCD編に書いた通りとはいえ、CDより量感のある音と成っており、充実度が増した。強奏部の熱気を帯びた、たたみかける様な推進力、その何物かに取り憑かれた様な異常な迫力が更に増し、ウィーン・フィルならではの旋律群の美しさや味わい深さもより楽しめる様に成った。元々素晴らしい演奏だったが、更に感動が増したのだ!
今この交響詩を演奏してこれだけの事をやれる指揮者とオーケストラがいるだろうか。作曲者の愛弟子だったベームと作曲者と強い繋がりのあったウィーン・フィルが深い愛情と熱い情熱を注いで一体と化したからこそ達成出来た演奏だという他はない。
これは20世紀のR・シュトラウス演奏を語る上で決して欠かす事の出来ない映像遺産だ。 |
| 交響詩『英雄の生涯』作品40 |
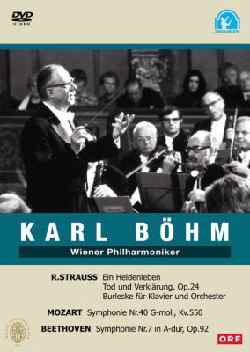 | ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1963年5月19日、ORF制作 |
| ドリームライフ DLVC-1211 |
音楽の都ウィーンに君臨し、世界中の音楽家やファン憧れの的であるウィーン・フィル。その栄光の歴史の中で、初めて「名誉指揮者」の称号を与えられた大指揮者カール・ベーム。定期公演を歴代最多の57回指揮しているところからも、巨匠にとってもウィーン・フィルにとっても互いに重要な存在であった事を示している。
中には特に最晩年のベーム〜ウィーン・フィルについて貶す連中がいる事は確かだ。ベーム没後、ウィーン・フィルの何人かのメンバーが「ベームは昔は偉大だったが、晩年は老いてテンポ感がおかしく成ってしまった。だから、俺達がフォローして名演にしてやっているんだ」という意味の事を語ったインタビューが雑誌に掲載された事もあった。尤も、彼らはベームは老いても自分達のお陰で名演に成っているという事を自慢したかったみたいなのだが。また、互いによく知っているからこそ、悪くも言えたのだ。逆に言えば、ベームも自らの体力の低下は心得ており、だからこそ、ウィーン・フィルを信頼して委ねる部分が増えたのだと言う事も出来る。
実際、音楽雑誌が大好きなベスト盤などの企画では、ベーム晩年の演奏が幾つも登場している。一方で、多くの人がベームの全盛期は1950年代と1960年代と評している中で、この時期は契約の都合もあってウィーン・フィルとの公式録音は多いとは言えず、その為に中にはベームはウィーン・フィルよりベルリン・フィルやドレスデン国立管を指揮した方が良いといった評価を与える人も少なからずいる。しかし、遺された公式盤だけでなく、死後世に出たこの時代のウィーン・フィルとの数々のライヴは、ベームとこのオーケストラとの特別な関係を改めて思い知らせてくれる。
2010年3月、世に出た1963年5月19日のコンツェルトハウスでのR・シュトラウス演奏会とインスブルック冬季五輪開会式典コンサートの映像は、正にその貴重な記録である。しかも、音だけでなく、映像が拝めるところがより時代観を鮮明にして、感慨深い。ベームが晩年と違い足早に登場すると、満場割れんばかりの拍手が巻き起こり、直ぐに演奏が始まらないところなどは、ベームの人気が晩年に高まった日本と違って、欧州ではフルトヴェングラー亡き後、既にしてカラヤンと共に中心的存在であったという事を証明している。
さて、話が長引いたので『英雄の生涯』の演奏について語ろう。これは『死と浄化(変容)』同様既にCDは聴いていて、その感想はCD編に書いているが、今回のDVDはより音質が向上。冒頭の量感からして違う。強靭で充実感を湛えた音が洪水の様に聴き手を呑み込んで行く。ヴァイオリン・ソロを担当するコンサート・マスターのヴィリー・ボスコフスキー(1909〜1991)の弾きっぷりが拝めるのも嬉しい。これにより、音だけを聴くより、音楽の説得力が増しているし、ウィーン・フィルの歴史の中でも輝かしい一つの時代に接しているという感慨が生れる。ライヴのベームならではの熾烈な迄に燃え上がる戦闘部分の迫力やウィーン・フィルならではの旋律群の美しさや味わい深さもCDより鮮明に伝えてくれる。更に、音が豊かに成った事で、CDで感じられた肌合いの粗さも軽減され、より完成度が高まっている点も見逃せない。
大作曲家の愛弟子カール・ベームがよく採り上げた交響詩といえば『ドン・ファン』『死と浄化』そしてこの『英雄の生涯』であり、その何れもDVD化された事はベーム・ファン、R・シュトラウス・ファン、そして総てのクラシック音楽ファンにとって非常に有難い事だ。三曲共発売を実現させてくれたドリームライフの努力に感謝したい。
それにしても、今回の様な記録を観てしまうと、ORFやその他の放送局にはまだ他にベームの素晴らしい宝が埋もれているのではないか、と期待してしまう。
何れにせよ、この『英雄の生涯』は永遠に語り継がれるに相応しい映像遺産である。 |
| 『(ピアノと管弦楽の為の)ブルレスケ』 |
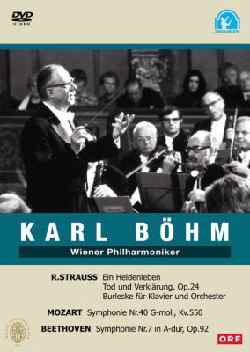 | ニキタ・マガロフ(ピアノ) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1963年5月19日、ORF制作 |
| ドリームライフ DLVC-1211 |
2010年3月、世に出たR・シュトラウスの愛弟子カール・ベームによる『英雄の生涯』『死と浄化(変容)』『ブルレスケ』。その中で、『英雄の生涯』と『死と浄化(変容)』はCD音源を所有していたので、音の違いは兎も角、初めて聴く演奏という訳ではなかったが、この『ブルレスケ』は私が今回初めて耳にした演奏である。
ベームには1957年のザルツブルク祝祭でグルダと協演した『ブルレスケ』のライヴCDが存在するが、今回はサンクト・ペテルブルク生れでスイスやフランスを拠点に活躍したニキタ・マガロフ(1912〜1992)がパートナーに迎えられている。マガロフといえばショパンやリストには定評があるが、R・シュトラウスのこの異色作への適合性には正直疑問を感じていた。
しかし、今回のこの映像を観る限り、グルダとは異なる魅力が存分に感じられ、充分世界的ピアニストとしての存在感は示されていると思う。グルダの様にジャズ的感覚を盛り込んだ洒落っ気とかがある訳ではないが、真正面にスコアと向き合い、ベーム〜ウィーン・フィルと真っ向勝負の掛け合いを演じているところは流石だ。兎に角この曲、R・シュトラウスにしてはそれ程編成が大きいとは言えないが、よく管弦楽が鳴り、特にティンパニが大活躍する為、協演するピアニストにとっては厄介である事は間違いない。マガロフは若干のミス・タッチなどものともせず、渾身の力を以てベーム〜ウィーン・フィルと互角に渡り合っている。グルダの様な面白さは感じないが、極めて聴き応えのある演奏が繰り広げられている。
ベーム〜ウィーン・フィルはマガロフのピアノを壊さない程度に気を使いつつも、単なる伴奏に終始せず、生々しい演奏を繰り広げている。特にティンパニは強烈至極。それでいて乱暴に成らず、音楽の流れが保たれているところが、流石ベーム〜ウィーン・フィルといったところだろう。
名曲というよりは、珍曲、異色作の部類に入ると思われる『ブルレスケ』だが、この映像は正にこの作品を鑑賞するのにうってつけの内容と歴史的価値を誇る文化遺産だと言えよう。 |





