





BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。
協奏曲②
| その① | その② |
| ピアノ協奏曲5番変ホ長調『皇帝』Op.73 | |
| ① | |
 | エトヴィン・フィッシャー(ピアノ) |
| ドレスデン国立管弦楽団 | |
| 1939年、ドレスデン | |
| TIM 220824-303 | |
| ② | |
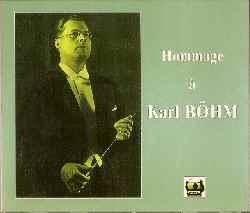 | エリー・ナイ(ピアノ) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1944年、ウィーン | |
| TAHRA TAH 444-446 | |
| ③ | |
 | コンラード・ハンゼン(ピアノ) |
| ベルリン放送交響楽団 | |
| 1952年4月10日、ベルリン | |
| musicaphon M 56845 | |
| ④ | |
 | エミール・ギレリス(ピアノ) |
| チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1971年8月8日、ザルツブルク | |
| ORFEO C 608 032 B | |
| ⑤ | |
 | マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1978年5月22〜24日、ウィーン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) F90G 50517/9 | |
| ⑥ | |
 | マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1978年5月28日、ウィーン | |
| FKM FKM-CDR-8 | |
| 1809年。この年は「傑作の森」の最後に当たるとされる。1803年のピアノ協奏曲3番から始まった「傑作の森」の最後の年を飾る名作がピアノ協奏曲5番、通称『皇帝』である。 余談だが、1809年といえば楽聖の大先輩ハイドンが亡くなった年であり、メンデルスゾーンが生まれた年でもある。 それはさておき、この5番は『皇帝』の通称が示す様に、当時としては類を見ない壮麗な響きを持った大協奏曲であった。ハイドンやモーツァルトは交響曲と協奏曲では異なる管弦楽編成による事が少なくなかったし、ベートーヴェン自身、第四では管弦楽とピアノの渾然一体化を目指したが故に、管弦楽の編成は交響曲に比べて控え目になっている。しかし、『皇帝』は交響曲を思わせる位編成の大きな管弦楽の活躍が目立つ。その威容が『皇帝』の通称を生んだ。逆に演奏効果が絶大なるが故に、協奏曲としての評価は人によって違う。4番と対を成す傑作とする人もいれば、バックハウスの様に4番を上位に見る人もいる。個人的には矢張りこの協奏曲、楽聖ならではの豊かな創造性が存分に発揮された傑作と考えている。冒頭からして、ベートーヴェンの個性が爆発している。主題の雄渾さも『英雄』に相通じるものがあるし、ヴァイオリン協奏曲の双生児的2〜3楽章も魅力に溢れ、一般的なベートーヴェンのイメージを象徴する曲の一つだと思う。 大指揮者カール・ベームは複数の『皇帝』を遺している。私が所有している6種類は何れも歴史にその名を残すピアニストと協演しているが、”黄金コンビ”と称されたバックハウスとの演奏がないのが残念だ。バックハウス自身、この協奏曲をあまり好んでおらず、あまり演奏しなかったと言われているが、クラウスやイッセルシュテットとのスタジオ録音や、カイルベルト、シューリヒト、コンヴィチュニーらとのライヴなどがある事を考えると、ベームとの協演の記録が残されていれば……と思ってしまう。 さて、先ず①である。これはドレスデン時代のベームの録音であり、生前から知られていたが、時代が古いだけに音質は3番、4番同様良くない。それだけでなく、オーケストラが目立つ曲故に逆にピアノを強調する事で管弦楽がピアノを圧倒しない様に配慮が為されている。その為、ベーム〜ドレスデン国立管からは3番や4番程の振幅の大きさや力強さが却って伝わって来ない。ピアノが完全に主役になり、オーケストラはサポートに回されてしまった感がある。ピアノはフィッシャー。彼は後にフルトヴェングラーと不朽の名盤を録音しているが、此処でも格調高く、そして味わい深い演奏を繰り広げている。ベームも立派な演奏を行っているという事は分かるのだが、先述の様にマイクの配置のせいか、とても指揮者とオーケストラを堪能出来る演奏とは言えない。 ②は伝説的女流ピアニスト、エリー・ナイとの協演である。1882年生まれの彼女はバックハウスより年長で、戦前のドイツを代表するベートーヴェン弾きの一人であったという。しかし、録音が少なかった事もあり、シュナーベルやバックハウス、そしてケンプらに比べ、世界的知名度という点では遥かに遅れをとっていた。しかし、近年再注目されつつある19世紀生まれの大ピアニストの一人である。因みにベームとナイの『皇帝』には1936年の録音もある様だが、私は持っていない。さて、②に戻ろう。これも戦時中の録音という事で、音質は良くない。しかし、①よりはオーケストラも堪能出来る仕上りになっている。ところが、逆にそのせいか所々ピアノが不鮮明になる。当時この大協奏曲を録音するのは、相当に無理があったという事だろうか。しかし、それでも随所に魅力溢れる演奏が展開されており、存在価値は充分にある。ナイのピアノは現代のピアニストの様な美音や華麗なテクニックとは無縁の、一音一音大地を踏みしめる様な悠然たる弾きっぷりを披露しているが、流石に録音が悪いので、細部のニュアンス迄はとても聴き取る事は出来ない。しかし、彼女が疑い様もなく19世紀の大家の一人であった事は窺い知る事が出来る。ベーム〜ウィーン・フィルも録音の悪さを超えた魅力を感じさせる。剛毅さは録音のせいもあり充分とはいえないが、旋律群の美しさは充分心に染み渡る。2楽章は正に音の古さを超えた感動がある。それにしても、この演奏、戦時中に行われている物とはとても思えない。正に演奏者全員が”音楽”に専念している。これが若しフルトヴェングラーだったなら、時代背景の鮮明な鬼気迫る演奏が展開されていた事だろう。逆に言えば、これは何時如何なる時も音楽に対して忠実だったベームの姿を知る事の出来る貴重なドキュメントでもある。 ③は2008年2月にH.M.様より頂いたコンラード・ハンゼン(1906〜2002)との協演を記録した物である。ハンゼンは今ではあまりその名を聞かなくなってしまったが、昔はベートーヴェン弾きとして高い評価を得ていたらしい。早速聴いてみると、録音年代の割に音が良い。ピアノは結構クリアーだし、管弦楽もよく響く。⑤と比べるのは酷だが、ソロと伴奏のバランスは良いし、充分聴き応えがある。若しかするとこれは放送録音なのかも知れない。ハンゼンのピアノはバックハウスやケンプみたいな如何にもドイツの巨匠といった感じはあまり受けないが、細部迄克明に、だれる事なく弾ききっているのは好感が持てる。豪快さや骨太さにやや欠ける面があるので、第4辺りは兎も角、『皇帝』ともなると、若干立体感に欠け、平板で軽い気がしないでもないが、聴き手を魅了する力は充分にある。しかし、何よりこの盤の聴きものはベームの指揮である。やや拡がりに欠ける録音とはいえ、強固な芯のある響きは壮年時代のベームならではで、やや美感に比重のかかりがちなピアノと好対照を成す。例えるなら、ピアノは女性的、伴奏は男性的。兎に角ベームは全体をガッチリと構築し、引き締めている。こういうベームに一番フィットするのはバックハウスだが、録音が存在しないのだからどうしようもない。何れにせよ、これは密度の濃い、充実した響きに身を委ねる事の出来る名演だ。H.M.様には心の底から感謝を捧げたい。 ④はバックハウス亡き後、ベームが度々共演したピアニストの一人、ギレリスとの演奏である。ギレリスは楷書の様にクリアーな音を奏でるという点では現代的なピアニストであると言えるが、音楽の本質に正面から切り込んでいく姿勢はバックハウスと相通じるものがあり、個人的にバックハウス亡き後ベームと最も相性の良いピアニストだと考えているが、どういう訳かベームはポリーニを気に入り、この若き天才との演奏会や録音を優先させていた。さて、④の演奏だが、音質自体は決して悪くはないと言える。しかし、ピアノと管弦楽のバランスが悪い。所々あまりにピアノが強く入り過ぎてしまっている。その為、①程ではないにせよ、オーケストラの音が遠くに霞んで聴こえる。その為に、この協奏曲の力強さが充分に伝わって来ない。 ⑤はピアノもオーケストラもたっぷり味わえる録音になっており、普通に鑑賞するならこれを推す。1楽章は内面の緊張感に欠けるのが残念だが、堂々たる威容は感じ取れる。しかし、この盤での聴き物は2楽章の美しさ、3楽章の愉悦にある。ポリーニは4番や3番に比べてより自分の持ち味を出しているが、その美麗なピアニズムが活かされているのが2楽章であり、若々しさが活かされているのが終楽章なのである。特に終楽章でのポリーニは忘我の境地にあるかの如く、時折唸り声を発するのが印象的だ。ベーム〜ウィーン・フィルもそうしたポリーニの表現を楽しみつつ、全体を大らかにまとめ、かつ確り引き締めている。 ⑥はH.M.様より贈って頂いたライヴCD−R。⑤と僅か数日の違いしかないだけに、演奏内容はよく似ている。録音はピアノに比重がかかっており、管弦楽は後一歩届いて来ないが、ポリーニの若々しい演奏と、ベームの力強く堂々たる老大家ならではの貫禄が違和感なく融け合っているのは流石としか言い様がない。録音がもう少し良ければ、⑤より良いかも知れない。これを下さったH.M.様には何とお礼を述べて良いやら、言葉が見当たらない。 何れにせよ、『皇帝』が3番や4番と比べて、遥かにピアノとオーケストラのバランスを含む録音条件や表現そのものに難しさのある曲だという事をベームの6種類の『皇帝』は物語っていると言える。 | |
| ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61 | |
| ① | |
 | マックス・シュトループ(ヴァイオリン) |
| ドレスデン国立管弦楽団 | |
| 1939年、ドレスデン | |
| TIM 220824-303 | |
| ② | |
 | クリスチャン・フェラス(ヴァイオリン) |
| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1951年11月18〜19日、ベルリン | |
| audite 95.590 | |
| ③ | |
 | クリスチャン・フェラス(ヴァイオリン) |
| フランクフルト(ヘッセン)放送交響楽団 | |
| 1952年、フランクフルト | |
| ORIGINALS SH 846 | |
| ④ | |
 | ユーディ・メニューイン(ヴァイオリン) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1958年3月18日、ミュンヘン | |
| GOLDEN−Melodram GM 4.0050 | |
| 「傑作の森」の中でも特に粒揃いの名曲が生み出されたとされる1806年に書かれたヴァイオリン協奏曲。現在メンデルスゾーンやブラームスと共に”3大ヴァイオリン協奏曲”と称されるこの名曲は、アン・デア・ウィーン劇場の首席ヴァイオリニストで、指揮者でもあったF・クレメント主催の音楽会の為に作曲された。彼は自筆譜に「ウィーン劇場首席ヴァイオリン奏者で宮廷劇場監督であるクレメントの為に、クレメンツァ(お情け)をもって、L.V.ベートーヴェン作曲す。1806年」と記している。彼とクレメントの親交を偲ばせる駄洒落に、ベートーヴェンの人間性を垣間見る事が出来る。 しかし、この協奏曲の初演は大失敗だった。当時の批評はクレメントのヴァイオリンは絶賛したが、ベートーヴェンの作品そのものには寧ろ冷淡だった。当時としてはあまりに1楽章が長大であった事が「退屈」と見なされる要因だった様だ。その為、この協奏曲はベートーヴェンの作品としては長い間演奏される事はなかった。失意の楽聖はこれをクレメントには献呈せず、親友だったシュテファン・フォン・ブロイニングに献呈する。因みに、楽聖はこれを名ピアニスト、クレメンティの依頼を受け、翌1807年にピアノ協奏曲に編曲している。このヴァイオリン協奏曲が現在の名声を獲得するのは、ずっと後に19世紀を代表する名ヴァイオリニスト、ヨアヒムが演奏してからの事だ。 さて、此処でも楽聖は様々な事を試みている。冒頭のティンパニが刻むリズム、ヴァイオリン独奏の導入部におけるカデンツァ的扱い。規模の巨大化は言う間でもないし、2〜3楽章の連結も当時の楽聖ならではの手法である。ピアノ協奏曲4番と共通の優美さを感じさせつつも、管弦楽はよりシンフォニックで雄弁で、後のピアノ協奏曲5番『皇帝』との共通性も併せ持つ。 カール・ベームの指揮した楽聖のヴァイオリン協奏曲は、生前にはドレスデン時代の①のみが知られていた。その死後、②〜④が登場したのである。個人的にはシュナイダーハンやオイストラフ、ボスコフスキー、それに比較的晩年に共演したズーカーマンやクレーメルとの演奏も聴いてみたいが、現時点ではないものねだりか。 ①はシュトループのヴァイオリンがやや粗削りな面があるが、男性的な力強さを持ったドレスデン時代のベームならではの演奏である。3曲のピアノ協奏曲同様録音は決して良くない。しかし、3番や4番同様管弦楽もそれなりに堪能出来る点が有難い。但し、この盤ではこの協奏曲の美しさよりは力強さが際立っているので、その辺りも評価を分ける事になろう。 ②はフルトヴェングラー在世中のベルリン・フィルが相手という事で、①以上の雄渾な演奏を想像していた。フルトヴェングラー〜シュナイダーハン〜ベルリン・フィルに匹敵する位の……。実際に聴いてみると、ライヴではなく放送用録音という事もあって、寧ろ節度をもって演奏されており、フェラスのヴァイオリンも若干18歳とは思えない知性と品格を感じさせる。終楽章は1950年代のベームらしい活力溢れる音楽作りが為されているが。録音は年代を考えれば決して悪くない。尚、この盤ではどういう訳か2楽章の出だしが欠けている。マスター・テープ自体がそうなのかは分からないが、非常に気になる。全体的には名演と呼べる演奏だと思うのだが、この部分を聴く度、ガックリする。尚、嘗てはTAHRA TAH 448で出ていたこの演奏、2011年10月にauditeから出た95.590は若干音質が向上しているが、二楽章冒頭の音欠けはこちらも変わらない。 ③はH.M.様より頂いたCDである。ソリストがフェラス、しかも時期的に近いという事もあって、全体的な印象としてはそう極端には違わない。録音は管弦楽に関する限り、②に比べて強奏部がやや不鮮明かつ届かないが、ヴァイオリン・ソロは③の方がより鮮明に拾われている。そうした事もあって、③は②よりフェラスの独奏が楽しめる。表情の付け方やテンポの動かし方も②よりロマンティック。遅いところは遅く、速いところは速く。伸縮自在といった感じになっている。但し、カデンツァはこの③より②の方がいい。ベームの指揮も、フェラスの音楽と違和感なく結び付いている。これこそオペラで培われた呼吸の妙という奴だろう。因みに、フランクフルト放送響は、戦後、ベームを始め、フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュ、シューリヒトら錚々たるメンバーを客演指揮者に迎えているが、この③ではそうしたドイツ・オーストリアが大量に大指揮者を輩出していた時代の空気というものが感じられる気がする。何れにせよ、音の悪さを超えて楽しませてくれる要素を多く湛えたこの③を下さったH.M.様には心の底より感謝するばかりである。 ④はフルトヴェングラーとの幾多の共演で知られ、”神童”と呼ばれたメニューインとの演奏である。此処ではウィーン・フィルがパートナーという事もあって、剛と柔がよく出ており、ベームの指揮自体はこれが最高だと言える。しかし、問題なのはメニューインとの呼吸が今一つ合っていない事だ。ベームは全体を確りまとめようとしているのに対し、メニューインは随所で独自の表現を試みようとしている為、時折造型のバランスが崩れる。ベームとメニューインは後にフリッチャイ協会の幹部(ディースカウとメニューインが設立、ベームは名誉会長)になっており、親交もあったが、音楽家としては異質であったと言わざるを得ない。しかし、共にライヴならではの魅力に溢れている為、個人的には実はこれが一番気に入っている。 | |
| ピアノ、ヴァイオリン、チェロの為の三重協奏曲ハ長調Op.56 | |
 | トリオ・ディ・トリエステ(ピアノ&ヴァイオリン&チェロ) |
| ウィーン交響楽団 | |
| 1954年3月11日、ウィーン | |
| ARCHIPEL ARPCD 0277 | |
| 楽聖が1803年から1804年にかけて作曲したとされるこの作品、今となっては作曲動機は不明である。しかし、ピアノ・パートが簡潔な内容である事から楽聖のパトロンの一人、ルドルフ大公の為に書かれたのではないかと推測されている。ルドルフ大公と言えば、楽聖が1811年に作曲したピアノ三重奏曲『大公』を献呈した人として夙に有名だ。こちらは、楽聖自身がピアノを受け持った事もあり、今でも室内音楽の傑作として広く愛されている。一方で、この三重協奏曲の評価は必ずしも高いとは言えないし、トップランクの人気レパートリーとなっている訳ではない。大公を気遣ってピアノを中心としたトリオの活躍が目立ち、楽聖の協奏曲としては管弦楽はかなり控え目で、あくまでトリオの補強と見なす向きが少なくないという事が挙げられようが、主題そのものも楽聖にしてはあまりメリハリがきいていないという事にも原因があろう。その為、楽聖ならではの構築感にやや乏しいのだ。要するに起伏の激しい楽聖らしさが希薄。常になだらか。しかし、だからこそ谷間に人知れずひっそりと咲く百合の花みたいな魅力がある。それはハイドンやモーツァルトの協奏交響曲みたいな古典的様式美とはまた別の世界だ。一方、2楽章と3楽章を切れ目なく演奏する様にしているところなどは後年の楽聖を準備する。とはいえ、楽聖の作品としては大きな演奏効果をあまり期待出来ない作品という事もあり、名盤はあまり多くはない。その中ではリヒテル(ピアノ)、オイストラフ(ヴァイオリン)、ロストロポーヴィチ(チェロ)のトリオによるカラヤン指揮ベルリン・フィル盤やアンダ(ピアノ)、シュナイダーハン(ヴァイオリン)、フルニエ(チェロ)のトリオによるフリッチャイ指揮ベルリン放送交響楽団盤などが比較的有名どころではなかろうか。 さて、ベームだが、このCDはこれ迄も私に色々なベームの録音を下さったH.M.様より新たに頂いた物である。同曲異演が少なくないベームであるが、この曲に関してはこの録音が唯一の音源だ。従って、既にそれだけで史料的価値がある。演奏そのものも録音が古い割には悪くないと思う。曲が曲だけにトリオ・ディ・トリエステの活躍が目立つ演奏である事は確かだが、トリオを確りサポートしつつ、全体の造型を引き締めているところにベームらしさを感じる。トリオ・ディ・トリエステは嘗てDGなどへの録音でも知られ、国際コンクールにその名を留める伝説的トリオ。レコード録音等の為に急遽組んだ豪華トリオの様に、時に異質の表現がぶつかり合うというのとは別の、息のあった演奏が魅力だ。古い録音ながら楽聖の”青春”の響きを引き出していると思う。そういう訳で、これはベームだけではなく、往年の名トリオを聴く事が出来るという点においても貴重な録音であると言えるし、またそれだけの価値を具えた演奏である事は確かだ。H.M.様には何時もの事ながら、心から感謝を捧げたい。 | |
| その① | その② |