





BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。
協奏曲①
| その① | その② |
| ピアノ協奏曲1番ハ長調Op.15 | |
 | フリードリッヒ・グルダ(ピアノ) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1951年、ウィーン | |
| DECCA 476 154-4 | |
| 音楽史上最大の風雲児、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。楽聖が一躍ウィーンで注目される様になったのはピアニストとしての比類なき個性であった。そして、彼の作曲の原点もまた、ピアノ音楽にある。既に初期のソナタにおいても4楽章制を導入する等、楽聖が一早くモーツァルトやハイドンとは異なる道を歩み始めたのはピアノ音楽であった。その楽聖がピアノ協奏曲を書き上げるのは1795年。彼はこの時2曲のピアノ協奏曲を書いている。第一と第二である。しかし、第一は1800年に改訂が行われている為、現在の研究家達は第二を最初のピアノ協奏曲とし、第一を実質第二として扱っている。ベートーヴェンが作品につけた順番は必ずしも完成順とは限らない事はよく知られているが、後世の研究家や演奏家、聴き手にとっては困った話だ。 さて、ベートーヴェンは尊敬するモーツァルト同様手掛けたジャンル総てに不朽の名作を遺していると言って過言ではないが、ピアノ協奏曲においても3、4、5番の3曲は今尚世界中で盛んに演奏される名曲中の名曲の地位を確立している。これに対し、1番や2番は実演でも録音でも採り上げられる機会が少ない。しかし、野望に燃える音楽青年ベートーヴェンが交響曲同様偉大なるモーツァルトやハイドンが確立した協奏曲の様式や表現に変革を齎そうとした事は充分に窺い知る事が出来る。特に第一は演奏時間だけをみれば第三や第四に匹敵する規模を具えている。尤も、当時のモーツァルトやハイドンの様式に慣れきっていた聴衆からすれば、第二はともかく、第一はやや冗長に過ぎたかも知れないが。逆に言えば、第三以降程ではないにせよ、第一にも楽聖の個性は既に現れているという見方も出来る。 大指揮者カール・ベームが当時若手の気鋭だったフリードリヒ・グルダを独奏に迎えたこの第一は、ベートーヴェンのピアノ協奏曲としては今一つ地味な存在と見なされがちなこの作品の代表的名盤の一つとして、長年親しまれてきた。カルロス・クライバーやマゼールと同じ1930年生まれのグルダはこの時21歳。後には”女傑”アルゲリッチの師として、またジャズ・ピアニストや作曲家等マルチな活躍を見せる鬼才として知られる事になる。此処では後に個性的表現で知られる様になるグルダとは別の溌剌とした若々しさ、瑞々しさが魅力になっており、青年ベートーヴェンの協奏曲に相応しい表現に思われる。ベームは若き気鋭のピアノを楽しみつつ、小細工なしの音楽的本質に根差した演奏を展開している。但し、録音が古いので、ニュアンスの豊かさには今一つ欠ける部分がある。勿論、今尚この協奏曲の代表的名盤の一つとして通用する内容である事は間違いない。 | |
| ピアノ協奏曲3番ハ短調Op.37 | |
| ① | |
 | ルブカ・コレッサ(ピアノ) |
| ドレスデン国立管弦楽団 | |
| 1939年、ドレスデン | |
| TIM 220824-303 | |
| ② | |
 | ヴィルヘルム・バックハウス(ピアノ) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1950年9月、ウィーン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) F30L-20170 | |
| ③ | |
 | エドゥアルド・デル・プエロ(ピアノ) |
| RAIトリノ交響楽団 | |
| 1952年5月8日、トリノ | |
| ARCHIPEL ARPCD 0444 | |
| ④ | |
 | マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1977年11月10〜12日、ウィーン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) F90G 50517/9 | |
| 楽聖は交響曲において第三『英雄』でその強烈な個性を開花させたと言われているが、ピアノ協奏曲においては同じく第三が”飛躍”を遂げた作品と見なされている。ベートーヴェン特有の強固な響きが随所に聴かれ、内面的な力強さと密度の濃さが充実した手応えを感じさせる。この協奏曲は1800年に書かれたという説と1803年に書かれたという説があるが、今では後者を採る向きが少なくない。内容的に見て、私も1803年説を採りたい。管弦楽を含む様々な表現がそれを自ずと実証している様に思える。因みに1803年といえばロマン・ロランが「傑作の森」と呼んだ楽聖中期の作品群が始まるとされる年である。この年にはヴァイオリン・ソナタの傑作『クロイツェル』が書かれている。そして、翌年には『英雄』が誕生するのである。 話が逸れた。話を戻そう。さて、楽聖唯一の短調によるピアノ協奏曲という事も、この第三が独特の魅力を感じさせる所以であろう。そうした事もあって、第一や第二とは異なり、演奏会でもしばしば採り上げられるし、録音も少なくない。 カール・ベームとヴィルヘルム・バックハウスという20世紀演奏史における”黄金コンビ”による②は数あるこの曲の録音の中でも未だに最高と評価する向きの少なくない不滅の歴史的名盤である。バックハウスもベームも小細工なしの真剣勝負といった趣の演奏を展開しているが、音楽的感覚に共通性が多々ある二人だけに一体感は比類がなく、その剛毅さと彫りの深さは正に他の追随を許さないものがある。録音は古いが、正にこの曲の模範的名演という事が出来よう。 ①は録音が相当に古いが、演奏そのものは悪くない。ベームは当時の手兵ドレスデン国立管と底力を感じさせる演奏を繰り広げているし、コレッサのピアノも情熱を感じさせる。 ④はDVDでも発売されたが、晩年の巨匠が特に可愛がっていた天才ポリーニとの共演である。ポリーニの若々しく、美麗なピアノがバックハウスとは別の魅力を感じさせ、音楽的手応えという事では②の存在感には及ばないものの、青年ベートーヴェンの姿が浮かび上がってくる。ベームはそうしたポリーニのピアノを楽しみつつ、全体を大きくまとめ、かつ引き締めている。録音はこれが最上である事は言う間でもなく、それが2楽章の美しさを際立たせている。 ③は2010年1月に陽の目を見たトリノ放送交響楽団と表記される事もあるRAIトリノ響(1994年以降はRAI国立交響楽団)との演奏会のライヴである。イタリアというと、「音楽=オペラ」というお国柄、ミラノ・スカラ座やナポリ・サン・カルロ劇場の様に世界的に名の知られたオペラハウスは幾つかあるが、コンサート・オーケストラと成るとこのRAIトリノ響を筆頭に、そこそこの知名度といったところだろう。しかし、この交響楽団がコンサート・オーケストラとしてはイタリアの筆頭格であり、ベームだけでなく、フルトヴェングラーやカラヤンら幾多の大物が客演している名門である事は忘れては成るまい。謎なのはピアノのデル・プエロ。日本のサイトでは何も判らなかったので(Googleで10件の検索結果が出たが、全部この③の紹介のみ)、海外のサイトを含めて調べてみると、何と147,000件の検索結果が表示された。どうやら海外ではかなり名の通ったピアニストの様だ。幾つかのサイトを閲覧してみると、1905年生まれ1986年没のスペインのピアニストらしく、フィリップスなどに幾つかの録音を遺している他、You Tubeではベートーヴェンのソナタ『ワルトシュタイン』のⅠ楽章やグラナドスの『ゴイェスカス』を演奏するデル・プエロの姿に接する事が出来る。スペイン物とベートーヴェンに定評があったらしい。そして、この③でもデル・プエロは技術面でも感情面でも確かな力量を示している。最初は「デル・プエロって誰?」という感じで、殆どベームの指揮にしか関心が無かった私にとって、それはいい意味で予想外の演奏だった。ベーム〜RAIトリノ響に関しては、若干管弦楽が離れ気味の録音ではあるものの、両端楽章ではこの時期のベームならではの剛毅さや気合の高まりが感じられ、緩徐楽章では感情の豊かさを感じさせる音楽が繰り広げられており、聴き応えは充分にある。オケもベームの指揮に応え、ドイツ的な響きを作り出していて、期待通りの名演と称して良かろう。日本ではレアなデル・プエロのピアノを含め、一度は聴いておいて損はない。 ①〜④各々魅力を持っている為、個人的には皆聴いて損はないと思う。②の存在感が大きい事は確かだが。 | |
| ピアノ協奏曲4番ト長調Op.58 | |
| ① | |
 | ワルター・ギーゼキング(ピアノ) |
| ドレスデン国立管弦楽団 | |
| 1939年、ドレスデン | |
| TIM 220824-303 | |
| ② | |
 | ヴィルヘルム・バックハウス(ピアノ) |
| RIAS(ベルリン放送)交響楽団 | |
| 1950年10月9日、ベルリン | |
| audite(キング・インターナショナル) audite 95.610 | |
| ③ | |
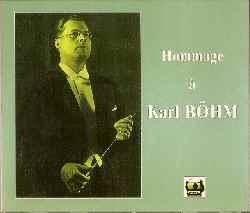 | ブランカ・ムスリン(ピアノ) |
| シュトゥットガルト放送交響楽団 | |
| 1951年、シュトゥットガルト | |
| TAHRA TAH 444-446 | |
| ④ | |
 | ヴィルヘルム・バックハウス(ピアノ) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1965年、ザルツブルク(?) | |
| MADRIGAL MADR-202 | |
| ⑤ | |
 | マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1976年6月25日、ウィーン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) F90G 50517/9 | |
| 1806年は「傑作の森」の中にあっても、特に粒揃いの作品が生み出された年とされる。交響曲4番、ヴァイオリン協奏曲、歌劇『レオノーレ』(第二版、序曲は『レオノーレ3番』)、弦楽四重奏曲7〜9番『ラズモフスキー1〜3番』等正に錚々たる顔触れといったところだが、このピアノ協奏曲4番も決して忘れる事の出来ない傑作である。 ベートーヴェンというと、交響曲『英雄』や第五の様に、重厚さや激烈さを秘めた作品をイメージする者が少なくない。しかし、彼が尊敬するモーツァルトとはまた別の優しさや美しさに満ちた作品を数多く遺している事も確かである。1806年に書かれた交響曲4番、ヴァイオリン協奏曲、そしてこのピアノ協奏曲や『ラズモフスキー』等にはそうしたベートーヴェンのもう一つの面が顕著である。これには楽聖の恋愛事情も関係あると見なされる。ベートーヴェンは旧知の貴族、ブルンスビック家の娘で、未亡人となっていたヨゼフィーヌに当時入れ込んでいたという。嘗てはこの年にベートーヴェンはヨゼフィーヌの姉、テレーゼと婚約した事から作品にその影響が反映されていると言われていたが、今では楽聖がこの時期ヨゼフィーヌに思いを寄せていた事が判明し、婚約説は否定されている。 相手がテレーゼだったにせよ、ヨゼフィーヌだったにせよ、ベートーヴェンが女性美に通じる優しさや美しさを持つ作品を書いた事だけは確かな事である。勿論、ベートーヴェンはベートーヴェンだ。単に優美なだけの作品は書いていない。主題の提示方法、展開手法、表現手法何れも彼ならではの独創性を盛り込んでいる。正に創造力が爆発している。だからこそ、この時期の作品群が「傑作の森」と称されるのである。 ベートーヴェンが他のジャンルに先駆けてピアノ音楽において新たな側面を切り拓いていった事は既に書いた。実際、ソナタにおいては前年の1805年に23番『熱情』が書かれている。このソナタではダイナミックスの表現手法や主題の呈示方法以外にも展開面で注目すべき点が多々ある。2楽章と3楽章を切れ目なく演奏するスタイルもその一つであろう。そして、このアイディアはピアノ協奏曲4番にも生かされているし、『皇帝』やヴァイオリン協奏曲、そして第五や『田園』といった交響曲にも用いられている。 勿論、ピアノ協奏曲4番の魅力はそれだけではない。主題をピアノが軽やかに始め、弦がこれに呼応。この出だしもハイドンやモーツァルトが確立した序奏付きの協奏曲の様式から抜け出すものだし、従来の協奏曲に比べ、よりピアノと管弦楽のハーモニーの融合が図られている。この発想をより壮麗な表現にしたものが『皇帝』であると見なす事も出来る。美しい緩徐楽章が置かれる事の多かった2楽章の扱いも特徴的だ。ベートーヴェンはこの楽章に1楽章と3楽章を連結する為の間奏曲的役割を持たせた。それ故、例えばモーツァルトの協奏曲の様に、聴き手を魅了する美しさとは別種の、一見渋い、それでいて印象的な音楽になっている。1楽章や3楽章が軽快さや優美さだけではないベートーヴェンならではの逞しい生命力を感じさせる部分を有している事は言う間でもない。全体的な様式の均衡美も確り踏まえており、正に『皇帝』と共にピアノ協奏曲史上屈指の傑作であり、人気作となっている。 ”鍵盤の獅子王”と謳われ、20世紀最大のベートーヴェン弾きと称されるヴィルヘルム・バックハウス。この不世出の巨匠がとりわけ繰り返し演奏し続けた協奏曲はベートーヴェンの4番、ブラームスの2番、そしてモーツァルトの27番であった。何れも表面的で煌びやかな演奏効果とは縁を切った作品であるという事が出来るが、それが虚飾を嫌い、音楽的本質をひたすら追求せんとする孤高の巨匠の理想に合致しているからだと思われる。事実、バックハウスは演奏効果の大きい『皇帝』は高く評価していない。 この大ピアニストが親友カール・ベームと組んでザルツブルクやウィーンで繰り広げたこれらの協奏曲の演奏は当時の欧州音楽界最高の呼び物であり、伝説と化している。この”黄金コンビ”による4番は21世紀を迎えて漸くDVDが発売され、オールド・ファンに舌鼓を打たせたが、CDでは両巨匠の死後から歳月の経過した外盤による②と④が存在する。 音質の面においても、巨匠同士の共演がカラー映像で拝めるという点においても、またより演奏が長年の共演で練り上げられているという点においてもDVDが個人的に最高の4番である事は確かだが、②も流石に”黄金コンビ”というところは見せており、存在意義は充分にある。録音はDVDに比べて劣るとはいえ、録音年代を考えれば充分鑑賞度の高さがあり、バックハウスもベームも揺るぎない確信に満ちた演奏を繰り広げている。互いに虚飾を一切排した真摯な音作りだが、その手応えの充実感は半端ではなく、正に”本物の味”を堪能させてくれる。他にも書いたが、バックハウスとベームはその音楽性に共通点を多々抱えている為、互いに妥協を許さぬ厳しい姿勢を貫きながら、それが自然と一体となっているところが凄い。ライヴならではの情熱の高まりも素晴しい。バックハウスはクレメンス・クラウスやイッセルシュテットとこの協奏曲の優れたスタジオ録音を遺しているし、DVDではクナッパーツブッシュとの個性的な演奏も遺されている。しかし、これも他にも書いたが、バックハウスとベームが組んだ時、水魚の交わりを思わせる比類なき結合が聴かれる。尚、この②、TAHRA盤とaudite盤が出ており、極端な違いはないが、微妙に音質が良いという事で、ジャケットや商品番号はこちらを掲載しておく。 ④はY.M.様より2007年末に送って頂いたコピーである。此処にはバックハウス〜ベーム〜ウィーン・フィルという正に当時の欧州音楽界最高と謳われた顔合わせが実現している。ただ、録音は非常に悪い。常にノイズが耳につくし、微妙に音が破損しているし、音量レヴェルが不安定な個所がある。尤も、そんな録音の悪さを超えた素晴らしさが味わえる演奏である事に変わりはなく、伊達に伝説を刻んだ顔合わせではないという事を実証している。若し録音が良ければ、決定盤として急浮上しても、寧ろ当然と思わせるだけのものがある。これを下さったY.M.様には心から感謝を捧げたい。 ①はベームの生前から既に知られていたドレスデン時代のスタジオ録音である。録音が古い事は確かだが、20世紀最高のモーツァルトの大家と謳われたギーゼキングのピアニズムの片鱗は味わえる。ベームとドレスデン国立管の演奏も割とダイナミックスの振幅が大きく、録音年代の割にはオーケストラ、ピアノ共に鑑賞に耐え得る。今でもこの曲の名盤の一つとして十分に通用する内容だと思う。 ③は女流ピアニスト、ムスリンと組んだ演奏である。聴く前は「ムスリンて誰ぞや」という感じだったが、聴いてみると悪くない。調べてみると、彼女は1919年(1920年生れとしているケースも多々ある)8月6日生れ、1975年1月1日没。ユーゴ出身でコルトーの弟子だったそうだ。これも録音年代が古いので、音質は決して良好とは言えないが、ムスリンのピアノは節度を保ちつつ、ロマンティックな味わいを時折垣間見せる。ベームの指揮もそれに呼応し、録音の割には豊かなニュアンスを聴かせる。美しさも力強さも充分に感じられ、ムスリンを知らなかった私にとって、これは予想外の名演であったと言える。 しかしながら、①〜④は演奏自体は素晴らしいのだが、録音が悪いのが残念な事であった。其処へ行くと、⑤は水際立って音が好い。これは録音年代を考えれば当然と言えば当然だ。大指揮者カール・ベームがバックハウス亡き後、最も好んで共演したピアニストといえばポリーニであった。バックハウスと組んでいた頃のベームは、虚飾を排した音楽の本質に正面から切り込んでいく様な精進的厳しさを持っていたが、当時若き気鋭だったポリーニの超美麗な響きと現代的な技巧が晩年の巨匠を魅了したのだろうか。兎に角ベームはポリーニを可愛がり、公私共に親しかった。その大指揮者と若き天才ピアニストによるベートーヴェンの協奏曲全集第一弾の録音となったのがこれである。因みに結局全集はベームが世を去った為、ヨッフムが1番と2番を代理で指揮して完成させている。それはさておき、当時カラヤンと共に指揮界の横綱だったベームがポリーニと組んだ事は、当時の演奏界や音楽ファンの間で大変な話題になった。内容そのものは若さに溢れ、美麗なポリーニのピアノを、ベーム〜ウィーン・フィルが大きく包み込む感じに仕上がっている。どちらかと言えばベームと組んだ時のポリーニは全体の支配はベームに委ね、細部において控え目ながら自己主張を行うといった感がある。逆に言えば、この時期のポリーニにとって、ベートーヴェンはまだ開拓中だったという事もある。結果、ベームがこの協奏曲において長年親友バックハウスと積み重ねてきた経験値が反映されている様に思われる。但し、此処にはバックハウスの時の様な凛とした威厳は感じない。ベームはポリーニのピアノを楽しみながら、余裕たっぷりに全体をまとめている。 何れにせよ、①〜⑤皆それぞれに魅力に溢れ、この協奏曲の素晴らしさを味わわせてくれる事に間違いはない。 | |
| その① | その② |