




BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。
私の所有盤
〜バックハウス
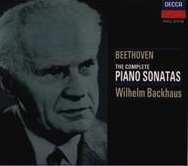
| 独奏曲 | 協奏曲他 |
|
①(CD)『バッハ・リサイタル』 ユニヴァーサル UCCD-9167 ②(CD)『ハイドン・リサイタル』 ユニヴァーサル UCCD-9170 ③(CD)『モーツァルト・リサイタル(旧盤)』 ユニヴァーサル UCCD-9176 ④(CD)『モーツァルト・リサイタル(新盤)』 ユニヴァーサル UCCD-7023 ⑤(CD)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集(旧盤) ポリドール(現ユニヴァーサル) POCL-3471/8 ⑥(CD)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集(新盤) ポリドール(現ユニヴァーサル) POCL-4731/8 ⑦(CD)ベートーヴェン:ディアベッリの主題による33の変奏曲 ユニヴァーサル UCCD-9173 ⑧(CD)シューベルト:楽興の時他 ユニヴァーサル UCCD-9174 ⑨(CD)『ブラームス・リサイタル』 ユニヴァーサル UCCD-9169 ⑩(CD)『バックハウス〜カーネギー・ホール・リサイタル』 ユニヴァーサル UCCD-9183 ⑪(CD)『バックハウス〜ライヴ・アット・カーネギー・ホール』 キングインターナショナル(Profil) KICC 859 ⑫(CD)『バックハウス〜ボン・ベートーヴェン・ハレ・ライヴ』 Ica ICAC5555 ⑬(CD)『バックハウス〜1966年ザルツブルク・リサイタル』 キングインターナショナル(ORFEO) KICC 858 ⑭(CD)『バックハウス〜最後のザルツブルク・リサイタル』 キングインターナショナル(ORFEO) KICC 857 ⑮(CD)『バックハウス〜最後の演奏会』 ユニヴァーサル UCCD-9185/6 ライプツィヒに生まれたヴィルヘルム・バックハウスは母親にピアノの手ほどきを受け、7歳の時ライプツィヒ音楽院に入学。1897年よりフランクフルトで大ピアニスト、オイゲン・ダルベール(1864〜1932)に師事。因みにダルベールはリストの弟子、リストはカール・ツェルニーの弟子、そしてツェルニーはベートーヴェンの弟子だから、バックハウスはベートーヴェン直系の弟子という事に成る。 1900年にデビュー、1905年にはルビンシテイン音楽コンクールでバルトークを破って優勝。バルトークはピアニストの道を断念し、作曲家として歩む事に成る。若き日のバックハウスは「鍵盤の獅子王」と称され、卓越した技巧で人気を博し、1909年には世界初の協奏曲録音も行っている。一方で、即物的で型にはまり過ぎているとしてフルトヴェングラーはバックハウスをあまり高く評価していなかったし、若き日のホロヴィッツもバックハウスやケンプを形式的過ぎるとして評価せず、またバックハウスの愛用するベーゼンドルファー社のピアノも気に食わず、スタインウェイに走るきっかけと成った。 1930年、バックハウスはスイスのルガーノに移住するが、やがてナチスが台頭する様に成ると、ヒトラーがバックハウスのファンだった事から、しばしばナチスの宣伝に利用され、戦後暫くはアメリカ公演の妨げと成った。 1946年、スイスに帰化したバックハウスは、デッカ専属として数多くの録音を行った他、各地でリサイタルを行ったりベームやクナッパーツブッシュといった著名指揮者との協演を重ねたりして、ケンプと共にドイツのピアニストの柱石として世界的に巨大な存在感を誇る様に成る。また、年を取る毎にレパートリーを絞り込む様に成り、技巧より内容を重視、あくまで作品本位で去私の姿勢を厳格な迄に貫くバックハウスは多くの音楽家やファンから尊敬を捧げられる様に成った。日本では吉田秀和や宇野功芳といった著名評論家達がバックハウスをしばしば称賛しているし、若き日の小澤も欧州で聴いた演奏家の中で最も印象的だった人物としてバックハウスの名を挙げている。 私がバックハウスの名を知ったのは小学生の時。大指揮者カール・ベームの自伝『回想のロンド』でベームと協演するバックハウスの写真が掲載されている他、第二次世界大戦中、ベームの息子カールハインツがスイスに疎開した時、既にスイスに移住していたバックハウスがその生活を援助してくれたという一文が掲載されており、この時からベームと関わりの深いピアニストとして注目する様に成った。 その後、様々の文献を目にして、その演奏を聴いてみたいと思い、中学生の時にベートーヴェンの6大ソナタ(⑥の新全集から『月光』『悲愴』『熱情』『ワルトシュタイン』『告別』『テンペスト』)のLPを購入。その偉大さに打たれた。更に、大学の頃、LPからCDへと時代が変わりつつある中、ベームとの協奏曲の録音を一通り購入し、私にとってバックハウスは生涯揺るぎなき最高の大ピアニストと成った。 それでは、私が現在所有するバックハウスのディスクについて語る事にしよう。 ①には1956年録音のバッハ:イギリス組曲第6番ニ短調BWV811、フランス組曲第5番ト長調BWV816、前奏曲とフーガト長調BWV860、前奏曲とフーガト長調BWV884が収められている。 バックハウスはライヴァルのケンプが若い頃からバッハ演奏に定評があったのに対し、それ程多く演奏して来たという訳ではなく、録音も少ない。しかし、ドイツ・オーストリアの音楽家の多くは造型を重んじる為、多くの音楽形式を網羅しているバッハの作品は何よりの模範であり、バックハウスもバッハを重視していた事は間違いないだろう。 その事はこのディスクでも充分感じ取れる。先ずバックハウスがバロック的、チェンバロ的な古式ゆかしいタッチで演奏している事に驚かされる。名前を伏せてこれを聴かせたら、バックハウスが弾いていると答える人はそう多くはないだろう。しかし、曲想を的確に描き分けて行く所や、身の引き締まる様な隙のない構成感、それに時折タッチがごつごつと武骨な感じに成る所などは矢張りバックハウスならではと言う事も出来る。バッハ演奏を語る上で、必要不可欠とは思わないが、一度は聴いておいて損はない名演だと思う。 ②には1958年録音のハイドン:ピアノ・ソナタ第52番変ホ長調Hob. XVI:52、ピアノ・ソナタ第48番ハ長調Hob. XVI:48、幻想曲ハ長調Hob. XVII:4、アンダンテ・コン・ヴァリアツィオーニ ヘ短調Hob. XVII:6、ピアノ・ソナタ第34番ホ短調Hob. XVI:34が収められている。 ハイドンは60曲以上のピアノ・ソナタを書いているが、同じ古典派のモーツァルトやベートーヴェンに比べて、現在では積極的に採り上げるピアニストは決して多くはなく、人気も高くはない。これはそんなハイドンのピアノ・ソナタやピアノ小品を聴く事が出来る貴重なディスクの一つである。 ハイドンに温厚さや優雅さを求める人には少々硬派で禁欲的な演奏ではあるが、小細工抜きで作品に切り込んで行くからこそ、ハイドンの構成の巧みさや曲想の変化が明確に捉えられ、内から滲み出る様な感情の豊かさが懐の深さを感じさせ、聴き応えのある演奏と成っている。一度は聴いておいて損はない。 ③には1955年録音のモーツァルト:幻想曲ハ長調K.475、ピアノ・ソナタ14番K.457、ピアノ・ソナタ10番K.330、ロンド イ短調K.511が収められている。 今ではバックハウスのモーツァルトのピアノ独奏曲というと、④がレコード・アカデミー賞を受賞したという事もあってしばしば再販が繰り返されているのに対し、③はモノラルという事や、④に比べると、ややラインナップが寂しいという事もあってか、やや影が薄い。私自身、④を先に購入して、大分経ってからこの③を購入している。尚、④に含まれる『トルコ行進曲付』は③と同じ1955年録音なので、LP時代には③の中に含まれていたのかも知れないが、当時の私はピアニストに関しては殆ど無知だったので、実際はどうだったのか不明である。 聴いてみると、④に比べて録音やラインナップの点で不利な点は否めないが、演奏自体はバックハウスならではの一見サラリと弾き流している様でいて、様式感、旋律の透明な美しさ、快活な部分での品格の高さと生命力の豊かさ、味わい深さなどが過不足なくあり、④にそうそうひけを取らない魅力を感じる。バックハウスによるモーツァルトのピアノ独奏曲を語る時、④だけでなく、③も一度は聴いておいて損はない名盤だと思う。 ④には1955年録音のピアノ・ソナタ11番K.331『トルコ行進曲付』、1961年録音のピアノ・ソナタ12番K.332(300K)とピアノ・ソナタ10番K.330(300h)、1966年録音のピアノ・ソナタ4番K.282(189g)とピアノ・ソナタ5番K.283(189h)とロンド イ短調K.511のモーツァルト作品が収められている。尚、K.331のみ③と同じ1955年録音なので、元々は③に含まれていたものを、④が発売される際に人気作という事で収録する運びと成ったのだろう。当時を知らないので、実際はどうだったのか不明だが。 さて、④について話を進めると、バックハウスといえば、厳格な風貌にぴったりのベートーヴェンやブラームスの評価が高く、モーツァルトは向かないと考える人もいるが、ベーム〜ウィーン・フィルと協奏曲27番で不滅の名演を成し遂げているし、ソナタも実演でしばしば採り上げるなど、バックハウス自身モーツァルトを重要な作曲家の一人と見做していた事は間違いあるまい。ただ、採り上げる作品に偏りがあった事は否定出来ないし、彼より後に出現したギーゼキングやハスキル、リリー・クラウスやアニー・フィッシャーらがモーツァルト弾きとしての名声を確立して行った事もバックハウスのモーツァルトを疑問視する人が少なからずいる理由の一つと成っている。 従って、この盤が1969年のレコード・アカデミー賞を受賞した当時、驚いた人は結構いたであろうし、今ではこれがレコード・アカデミー賞を受賞した事すら知らない人もいるに違いない。しかし、実際に聴いてみると、確かにそれだけの事はあると納得する人も少なからずいるのではないだろうか。バックハウス持ち前の構成感の強さはモーツァルトに定評があるベームやクレンペラー、或いはセルといった指揮者達と相通じるものがあるし、一見速目のテンポで素っ気なく弾いている様でいて、少々硬派ながら何処か懐かしさを感じさせる響きと内から滲み出る味わい深さがモーツァルトの魅力を充分に伝えてくれる。バックハウスのファンは勿論、モーツァルティアンにとっても一度は聴いておいて損はない名盤の一つだと思う。 ⑤には1950年から1954年にかけてのモノラル録音によるベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集が収められている。 シュナーベルやケンプと並び”20世紀3大ベートーヴェン弾き”と称されたヴィルヘルム・バックハウス。その不滅の金字塔として、今尚聖典視する向きも少なからず存在するのがこの⑤や⑥である。近年はステレオ録音という事もあって、⑥の新全集を支持する向きが増えている様だが、モノラル録音ながら、内容的には⑤の旧全集の方が好きだという人も少なからずいる。個人的には⑤⑥夫々に良さがあり、そう簡単に優劣はつけられない。 音はステレオ録音の⑥の方が量感や透明感がより感じられる事は確かだが、⑥が29番を除く31曲を録音するのに11年程かかっているのに対し、⑤は4年程で完成されており、全集としての統一感はこちらの方があると思う。シュナーベルの様にテンポが大きく伸縮したり、ケンプの様にダイナミックスの振幅が大きく成ったりするという事はなく、思い入れたっぷりといった感じよりは寧ろ禁欲的な迄に去私の姿勢を貫き、厳しく造型を鍛え上げている小細工抜きの正攻法による演奏という点は新旧両全集共に変わらないが、推進力が生み出す緊張感や剛毅さ、技巧の安定感はこの⑤の方が感じられる。或意味、楽譜のみを拠り所として造型と内容の両立を目指したというシュナーベルがまだロマン派的表現を残していたのに対し、バックハウスはシュナーベルが唱えた模範的な演奏に到達したと言えるだろう。そして、ピアニスト自身の主義主張を排し、作品本位の姿勢を貫きつつ、他の追随を許さぬ造型の立派さと内容の充実を感じさせるのがバックハウスならではの偉大さであり、個性なのだ。 勿論、今尚ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集を語る上で、必聴である。 ⑥には1958年から1969年にかけてのステレオ録音によるベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集が収められている。但し、29番はバックハウスが亡くなった為、再録音が行われず、⑤の1952年録音のモノラル音源が用いられている。 全集としての統一感や推進力、剛毅さ、技巧の安定感は⑤の方が感じられるが、⑥はモノラルからステレオに変わった事で、より響きの立体感や透明感が感じられる様に成り、シンフォニックな構築感やスケールの大きさ、彫りの深さ、味わい深さ、美しさなどが増しており、内容の魅力は⑤と甲乙つけ難い。 ベートーヴェンの偉大さ、バックハウスの偉大さに触れる事の出来るベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集の最高峰として、今尚⑤と共に必聴と言えるだろう。 ⑦には1954年録音の『ディアベッリの主題による33の変奏曲ハ長調作品120』が収められている。 ベートーヴェンが最後のピアノ・ソナタである32番の後に書き上げたピアノ独奏用のこの超大作は或意味Ⅱ楽章制のピアノ・ソナタ32番のⅡ楽章で用いられた長大な変奏曲の発想を更に推し進めたものと見なす事も出来るが、その半面、変奏が多い為、全曲を散漫に陥らずに演奏する事は決して容易ではない。 バックハウス盤は⑤の序に録音された物で、今尚作品の代表的名盤と目されている。コンセプトは⑤と同じく、小細工抜きで作品をストレートに掘り下げており、各変奏の特色を過不足なく捉えつつ、決して散漫に陥る事なく全曲が強い構築感によって纏め上げられている。勿論、作品を語る上で必聴盤だ。 ⑧には1955年録音のシューベルト:楽興の時D.780(作品94)とシューマン:森の情景作品82が収められている。 バックハウスと言えば、ベートーヴェンやブラームスがその厳しい風貌に相応しく、ハイドンやモーツァルト、シューベルトやシューマンといった所は向かないと考える向きがあるが、録音はそれ程多くはなくても、ライヴではしばしば採り上げており、バックハウスがベートーヴェンやブラームスだけでなく、幅広くドイツ・オーストリア系の作曲家や作品に取り組んで来た事は間違いない。 それはあくまで虚飾を排し、楽譜のみを拠り所とした、構成感の強い硬派な演奏であると言える半面、虚心に作品に向き合っているからこそ、各々の作品の本質や作曲家毎の特色が鮮明に成り、バックハウスの懐の深さを感じさせる。即ち、シューベルトでは穏やかで味わい深い歌心、シューマンでは繊細な感情が大袈裟ではなく、バックハウス持ち前の引き締まった造型の中で、さり気なく示されている。作品を語る上で、一度は聴いておいて損はない名演と言えるだろう。 ⑨には1956年録音のブラームス:6つの小品作品118、奇想曲ロ短調作品76の2、間奏曲変ホ長調作品117の1、ラプソディー ロ短調作品79の1、間奏曲ホ長調作品116の6、間奏曲ホ短調作品119の2、間奏曲ハ長調作品119の3が収められている。 バックハウスと言えば、ベートーヴェンと並び、ブラームスに定評があるが、そのイメージは殆ど2曲の協奏曲によって培われたと言ってよく、独奏曲に関してはベートーヴェン程繰り返し演奏会で採り上げた訳でもなければ、録音も多いという訳ではない。これはそんなバックハウスが演奏するブラームスの独奏曲を纏めた貴重な録音である。 バックハウスは如何にもこの人らしく、ひたすら真摯に作品に向き合い、構成感の強さ、響きの立体感、スケールの大きさ、旋律の味わい深さを引き出しており、いささか武骨な面も含めて、これぞ真正のブラームスといった内容に仕上げており、各々の作品を語る上で必聴の名演である。 ⑩には1954年3月30日録音のベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番ハ短調作品13『悲愴』、第17番ニ短調作品31の2『テンペスト』、第26番変ホ長調作品81a『告別』、第25番ト長調作品79『郭公』、第32番ハ短調作品111とアンコールとして演奏されたシューベルト:即興曲変イ長調D.935の2(作品142の2)、シューマン:幻想小曲集作品12から第3曲『何故に?』、リスト編/シューベルト:ウィーンの夜会第6番イ長調S.427の6、ブラームス:間奏曲ハ長調作品119の3が収められている。 バックハウスは1912年にニューヨークでダムロッシュ〜ニューヨーク・フィルと演奏したベートーヴェンの『皇帝』が「神業」と大絶賛を博して以降、第一次世界大戦を挟んでしばしばアメリカで公演を行っていたが、第二次世界大戦後はナチス協力者として扱われ、暫くは入国禁止の措置が取られていた。そして、漸く入国禁止が解け、カーネギー・ホールで行われた記念碑的なリサイタルを収録した物がこのディスクである。 バックハウスは基本的には小細工抜きで作品に切り込むタイプだが、親友のベーム同様、時折作品を踏み外さぬ様にしつつ、微妙な変化を試みており、それが独特の味わいを生んでいる。その事はライヴでより顕著であり、此処でもバックハウス持ち前の構築感を損なわず、それでいて微妙に移り変わる感興が何とも言えない魅力と成っている。久々のアメリカ公演に臨むバックハウスの内に秘められた情熱の高まりも感じられ、その演奏を待ち望んだ聴衆の感動も伝わって来る。特別な意義のある公演の記録だけに、バックハウスのファンにとっては必聴だと思うし、ピアノ独奏曲が好きな人にとっては一度は聴いておいて損はないディスクだと思う。 ⑪には1956年4月11日録音のベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調 op.27-2『月光』、ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 op.106『ハンマークラヴィーア』、アンコールとして演奏されたシューベルト:即興曲 変ロ長調 op.142-2、ショパン:練習曲第14番 へ短調 op.25-2、シューマン:予言の鳥 op.82-7、モーツァルト:ピアノ・ソナタ第11番 K.331〜終楽章(トルコ行進曲)が収められている。 これもカーネギー・ホールにおけるリサイタルのライヴだが、この中で先ず目が行くのは『ハンマークラヴィーア』であろう。このソナタは40分前後という規模の大きさは勿論、当時のピアノの性能の極限とも称される難度の高さでも知られており、リストやクララ・シューマンが出現する迄、弾きこなせる人がいなかったとされる程だが、ベートーヴェンが特に器楽や室内楽で内面的な世界に踏み込んだ時期の作品という事もあり、ややとっつきにくい所がある為、人気作とは言い難い。そうした中、⑤の旧全集に含まれるバックハウスの演奏は、この大ソナタの真価を伝える正統派の名演とされて来た。一方で、⑥の新全集では唯一録音が行われないまま、バックハウスが世を去ってしまい、⑤の音源がそのまま用いられる事に成った。逆に言えば、この大ソナタが最晩年のバックハウスに強いる負担が大きかった為、中々録音に踏み切れなかったという事だろう。 そのバックハウスが録り直しのきくスタジオ録音ではなく、ライヴの一発勝負でこの大ソナタを演奏している。ベートーヴェンのピアノ・ソナタのファンやバックハウスのファンで、これに興味をそそられぬ者はおるまい。演奏そのものも期待に違わぬ出来で、バックハウスならではのシンフォニックな構成感、ライヴならではの推進力、緊張感、感興の微妙な揺れ動きなど、正に抜群の聴き応え。『月光』もバックハウスならではの名演だし、アンコールに至る迄バックハウスの魅力が振り撒かれ、誰もが知っているモーツァルトの『トルコ行進曲付』終楽章で最後を飾るという心憎さに聴衆は興奮の坩堝。バックハウスのカーネギー・ホールでのリサイタルのライヴといえば、昔から⑩が有名だったが、この⑪も一度は聴いておいて損はない御馳走揃いだ。 ⑫には1959年9月24日にボンのベートーヴェン・ハレで行われたシューベルト:即興曲変ロ長調D935の3(Op.142-3)、ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第6番ヘ長調 Op.10-2、ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調 Op.106『ハンマークラヴィーア』のライヴが収められている。 モノラル録音ではあるが、音質は比較的良い方で、3曲何れも楽しめる。特に『ハンマークラヴィーア』はベートーヴェン生誕の地ボンでの演奏という事もあり、バックハウス自身特別な思いを抱いて臨んだという事が伝わって来る。バックハウスのファンにとっては必聴、そうでない人にとってもバックハウスの偉大さに触れる事が出来るディスクの一つとして、一度は聴いておいて損はない。 ⑬には1966年7月30日録音のJ.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第2巻〜前奏曲とフーガ第24番ロ短調BWV.893、前奏曲とフーガ第15番ト長調BWV.884、モーツァルト:ピアノ・ソナタ第5番ト長調K.283、モーツァルト:ピアノ・ソナタ第11番イ長調K.331『トルコ行進曲付き』、ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調Op.57『熱情』、ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第32番ハ短調Op.111が収められている。 これはバックハウス最晩年のザルツブルク祝祭リサイタルの一つを記録した物だが、この時既に82歳のバックハウスは、ベートーヴェンの『熱情』とピアノ・ソナタ32番を立て続けに配するなど、年齢からすると信じ難い重量級のプログラムで臨んでいる。演奏自体も素晴らしい。1950年代に聴かれた剛毅さや推進力は流石に後退しているものの、立体感、構成感、スケール、飾り気のない美しさ、内容の彫りの深さ、そしてライヴならではの感興の豊かさ、気合の高まり。特に『熱情』の凄みとこれに続く為に聴く前は懸念していた32番の深みはバックハウス以外には不可能な演奏とさえ思われる。矢張りバックハウスのファンのみならず、ピアノ音楽を愛する人にとっても必聴の記録だと思う。 ⑭には1968年8月10日録音のベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第12番変イ長調Op.26、ピアノ・ソナタ第14番嬰ハ短調Op.27-2『月光』、ピアノ・ソナタ第17番ニ短調Op.31-2『テンペスト』、ピアノ・ソナタ第26番変ホ長調Op.81a『告別』が収められている。 これはバックハウス最後のザルツブルク祝祭リサイタルの記録である。バックハウスはこの後、8月18日にベーム〜ウィーン・フィルとブラームスのピアノ協奏曲2番も演奏しており、84歳という高齢にも関わらず、1週間程の間にリサイタルと協奏曲公演をこなすバックハウスには吉田秀和氏ではないが、本当に頭が下がる。 内容はオール・ベートーヴェン・プログラムで、しかも最後の曲目が『告別』というのが暗示的だ。演奏そのものは虚飾を排して作品の本質を抉るバックハウスならではの物だと言える一方、最晩年の穏やかで澄み切った境地にも触れる事が出来、流石の聴き応え。勿論、バックハウスのファンにとっては必聴のディスクであろう。 ⑮には1969年6月26日のベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第21番ハ長調作品53『ワルトシュタイン』、シューベルト:楽興の時D.780(作品94)、モーツァルト:ピアノ・ソナタ第11番イ長調K.331『トルコ行進曲付き』、シューベルト:即興曲変イ長調D.935の2(作品142の2)、 6月28日のベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調作品31の3から(第1〜3楽章)、シューマン:幻想小曲集作品12から第1曲『夕べに』、シューマン:幻想小曲集作品12から第3曲『何故に?』、シューベルト:即興曲変イ長調D.935の2(作品142の2)のライヴ録音が収められている。 これはオーストリアのケルンテン州フェルトキルヒェン郡にある町オシアッハの修道院教会で行われたバックハウス最後の演奏会の記録である。バックハウス程の大ピアニストが何故小さな町でリサイタルを開いたかといえば、この年より開催された「ケルンテンの夏音楽祭」のこけら落しに招かれたからである。また、そうした事情があったから、こうした小さな町でのリサイタルの記録が残される事に成った。 先ず6月26日のリサイタルの記録だが、バックハウスが今迄歩んで来た音楽人生を反映させたかの様な味わい深さと澄み切った境地が印象的。ミスタッチが所々散見されるが、それを忘れさせる位聴き手を音楽に引き込んで行く。 続く6月28日のリサイタルはバックハウスが途中で心臓発作に見舞われた為、演奏を中断するも、プログラムを変更して最後迄弾き通したという逸話で名高い。それだけに、聴く前から特別な思いを抱かない訳にはいかない記録である。此処にはバックハウスがベートーヴェンのピアノ・ソナタ18番を3楽章迄で中断し、その後終楽章は演奏せず、プログラムを変更して臨む様子が克明に記録されている。特に中断後のシューベルトとシューマンは、恐らく気分が優れなかったにも関わらず、味わい深く、澄んだ音楽を展開するバックハウスの偉大さに感じ入るより他はない。この後、7月5日にバックハウスが世を去るとは当時誰も思わなかったであろう。 バックハウスの「白鳥の歌」としてバックハウスのファンにとって必聴のディスクであると同時に、20世紀演奏史に残る伝説的公演の記録の一つとして、クラシック音楽ファンを自認する人にとって一度は聴いておいて損はないディスクだと思う。 |
| 独奏曲 | 協奏曲他 |