




BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。
私の所有盤
〜その他のヴァイオリニスト
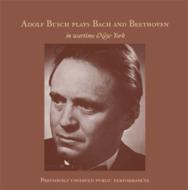
|
ヨアヒム 〜私の所有盤〜 ・(CD)ブラームス:ハンガリー舞曲1&2番他 ピアニスト不詳 Podium POL-1053 これはクーレンカンプ〜ベーム〜ベルリン・フィルによるシューマン:ヴァイオリン協奏曲の余白に収められている演奏で、1903年8月27日録音のブラームス:ハンガリー舞曲1番及び2番、それにヨアヒム:ロマンスといったラインナップ。ピアニストは不詳である。 これは、音が貧弱で史料の域を出ないと見る向きと、1903年録音の割にはそれなりに楽しめる向きとに聴き手の見解が分かれそうだ。個人的にはヨアヒムの録音が残っているという事だけでも、その価値は高いと思うが、流石19世紀を代表する大家の一人と思わせるロマンや技巧もそこそこ感じられるので、ヴァイオリニストの歴史を語るという意味においては必聴と言えると思う。 ティボー 〜私の所有盤〜 ①(CD)『ティボー&コルトー/フランス音楽作品集』 コルトー(P)他 Andromeda ANDRCD5138 ②(CD)『パブロ・カザルス/ポートレイト』 カザルス(Vc)他 Membran 232768 ①にはコルトーのピアノ伴奏で録音されたフランク:ヴァイオリン・ソナタ(1929年)、ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ(1929年)、フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ第1番(1927年)、フォーレ:『ドリー』Op.56から『子守歌』(1944年)、 ショーソン:ヴァイオリン、ピアノ、弦楽四重奏のための協奏曲ニ長調Op.21(1931年、弦楽四重奏はVnがイスナール、ヴルフマン、Vaがブランパン、Vcがアイゼンベルク)、 ボーナス・トラックとして”ティボー・イン・フランクフルト”と題し、1953年4月29日のサン・サーンス:ヴァイオリン協奏曲1番、ロンド・カプリチオーソOp.28(以上はガリエラ〜ヘッセン放送響の伴奏)、4月30日のサン・サーンス:ハバネラOp.83、モーツァルト:ロンドKv.378(以上はマリヌス・フリプセのピアノ伴奏)が収められている。 ジャック・ティボーと言えば、女流ピアニストのマルグリット・ロン(1874〜1966)と共同で1943年に創始したロン・ティボー国際コンクールにその名を留めるフランスの世界的ヴァイオリニストだが、特にフランスの世界的ピアニスト、アルフレッド・コルトーとのデュオ、これにスペインの世界的チェリスト、パブロ・カザルスを加えたトリオの活動は20世紀前半における伝説的な組合せとして語り継がれている。 そして、①にはティボーとコルトーの黄金デュオによるフランス音楽の名演が纏められている。録音が古いので、聴き易いとは言い難いが、品格の高さ、感情表現の豊かさは今では得難い古き佳き時代の香りを湛えているし、お国物という事もあって、作品に強い説得力を与えている。ボーナス・トラックは1953年のライヴという事で、若干録音が良い事もあり、よりティボーのヴァイオリンの表現の幅を感じ取る事が出来る。余談だが、ティボーはこの演奏会から4か月程後の9月1日、1949年に夭折したジネット・ヌヴーと同じくエールフランスの墜落事故により愛器の1720年製ストラディヴァリウスと共に亡くなっている。そうした意味においては最晩年のティボーの史料としての価値も高く、クラシック音楽ファンなら一度は聴いておいて損はないディスクだと思う。 ②には1926年録音のシューベルト:ピアノ三重奏曲1番(ピアノ:コルトー、ヴァイオリン:ティボー)が収められている。録音が古い事は確かだが、伝説のカザルス・トリオの史料の一つとして、一度は聴いておいて損はない。 エルマン 〜私の所有盤〜 ・(CD)『ミッシャ・エルマン名演集』 ロンドンPO他 Membran 600480 これは激安BOXで有名なMembranから2018年秋に発売された10枚組で、 1枚目には1954年と1956年にボールト〜ロンドン・フィルと録音したチャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲とヴィエニャフスキ:ヴァイオリン協奏曲2番、 2枚目には1956年にショルティ〜ロンドン・フィルと録音したベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲、 3枚目には1955年にジョセフ・シーガー(P)と録音したベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ5番『春』&『クロイツェル』、 4枚目には1955年にクリップス〜新交響楽団と録音したモーツァルト:ヴァイオリン協奏曲4番&5番、 5枚目には1956年と1961年にシーガー(P)と録音したブラームス:ヴァイオリン・ソナタ全曲、 6枚目にはドラティ〜ハリウッドボウル管とのメンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲1948年ライヴと1956年にシーガー(P)と録音したコルンゴルト:組曲『空騒ぎ』、 7枚目には1956年録音のブルッフ:ヴァイオリン協奏曲1番(ボールト〜ロンドン・フィル)&2番(フィストゥラーリ〜ロンドン・フィル)、 8枚目には1955年にシーガー(P)と録音したグリーグ:ヴァイオリン・ソナタ1番&3番、 9枚目には1955年と1956年にシーガー(P)と録音したヴィターリ/シャルリエ編:シャコンヌ ト短調、ヘンデル:ヴァイオリン・ソナタ第4番 Op.1-13、フランク:ヴァイオリン・ソナタ イ長調、 10枚目にはモントゥー〜サンフランシスコ響とのラロ:スペイン交響曲1950年ライヴ、ドラティ〜ハリウッドボウル管とのチャイコフスキー:憂鬱なセレナード1948年ライヴ、オーマンディ〜ハリウッドボウル管とのチャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲1947年ライヴ、1913年に不世出のテノール歌手カルーソー、パーシー・カーン(P)と録音したペルキヴァル・ベネディクト・カーン:アヴェ・マリア、マスネ:悲歌が収められている。 エルマンはミルシテインやオイストラフ、スターンらと同じくウクライナ出身で、同じレオポルド・アウアー門下の後輩ハイフェッツやミルシテインが超絶的技巧で一世を風靡したのに対し、豊かさや美しさ、ロマン派的感情表現で一時代を築き、その響きは”エルマン・トーン”と称された。 録音は1906年より行い、1950年代に入る迄ヴィクターの専属として活躍。1954年よりデッカに移籍し、更に1958年には米ヴァンガードに移籍し、最晩年に至っている。 このBOXはエルマンのデッカへの録音を中心に幾つかのライヴと初期のカルーソーとの録音が収められているが、現在エルマンの録音の多くは市場に出回っていないので、或程度彼の録音が纏められているという意味においては、誠に貴重であると言える。 それでは、演奏について語ろう。エルマンの最盛期は1920年代とされ、晩年にはやや衰えが見られる様に成ったとされるが、ヴィオラやチェロを思わせる中音・低音の豊かさ、高音の美しさなど、”エルマン・トーン”と称された響きの魅力は充分に感じられる。時に勿体つけた様な所やもたつき加減に成る所はあるが、感情表現も古き佳き時代のロマンを感じさせ、独特の魅力がある。個人的にはクライスラーとオイストラフの中間座標にあるスタイルだと思う。また、デッカへのスタジオ録音は音質も悪くなく、ボールトや若きショルティ、クリップスらの指揮する管弦楽も楽しめるし、ヴァイオリン・ソナタでピアノを受け持つシーガーも無難な出来だ。 一方で、カルーソーとの録音や、ライヴに関しては音質にやや不満が残る。特にライヴではスタジオ録音よりテンポの伸縮や感情の起伏が感じられるし、モントゥーやオーマンディ、ドラティらの指揮する管弦楽も悪くないだけに、惜しい。特にオーマンディとのチャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲はもう少し音が良ければ、オーマンディが後に録音したオイストラフ盤やスターン盤に勝るとも劣らぬ評価を得ていたかも知れない。 という訳で、このBOXはエルマン・ファンのみならず、ヴァイオリニストの歴史を語る上で一度は聴いておいて損はない内容だと思う。 A・ブッシュ 〜私の所有盤〜 ・(CD)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲他 ニューヨークPO他 Music And Arts CD-1183 此処には1943年録音のバッハ:ヴァイオリン協奏曲1番(ピアノ:ルーカス・フォス、A・ブッシュはブッシュ・チェンバープレイヤーズを弾き振り)、1942年2月8日にカーネギー・ホールで行われたベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲(F・ブッシュ〜ニューヨーク・フィル)のライヴ、1942年2月21日の放送用録音であるベートーヴェンのロマンス1番&2番(ウォーレンスタイン〜WOR放送響)が収められている。 このディスクで何と言っても注目すべきは兄のフリッツとのカーネギー・ホールでのベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲のライヴであろう。アドルフのヴァイオリンはライヴという事もあってか、時に力瘤が入り過ぎて粗く成る所はあるが、生命力の強さ、味わい深さは20世紀前半を代表する名ヴァイオリニストならではと言えるし、兄フリッツの指揮がこれまた端正な造型と逞しい表現力で高い説得力を与えており、特に終楽章はこの協奏曲の代表的名演の一つとして今でも充分通用する。 ブッシュ自身が弾き振りをしているバッハは、ダイナミックスの振幅が大きく、またⅡ楽章ではロマン派的表現が聴かれるなど、純正バッハ党からすれば規格外の演奏と言えると思うが、個人的にはその人間味の豊かさに捨て難い魅力を感じる。録音が古い為、ピアノによる通奏低音は聴き取り辛いが、個人的にはバロックの通奏低音と言えばチェンバロのイメージが強い為、ピアノが目立たない事は却って有難い。ウォーレンスタインとのベートーヴェンのロマンス2曲も悪くなく、ディスク全体として、一度は聴いておいて損はないと思う。 尚、アドルフ・ブッシュと言えば、ブッシュ四重奏団の活動や、アドルフが見出し、後には娘婿と成ったルドルフ・ゼルキンとのデュオが有名だが、それらの録音は現在の所、未聴である。 シゲティ 〜私の所有盤〜 ・(CD)『ブルーノ・ワルター・エディション』 ニューヨークPO他 SONY S70891C 此処には1947年録音のベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲(ワルター〜ニューヨーク・フィル)が収められている(カップリングは1945年録音のミルシテインとのメンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲)。ワルターは1932年にシゲティの独奏、ブリティッシュ響の管弦楽、1961年にはフランチェスカッティの独奏、コロンビア響の管弦楽でこの協奏曲を録音しているが、今回のBOXではシゲティとの1947年の録音が選ばれている。 ハンガリー出身のシゲティは技巧で聴き手を感嘆させるタイプでもなければ、量感で聴き手を圧倒するタイプでもなく、美音で聴き手を魅了するタイプでもない。彼が20世紀前半を代表する名ヴァイオリニストとして称えられたのは、作品に対する真摯な態度、高潔な精神性という事に成るだろう。従って、このディスクでもシゲティのヴァイオリン独奏に関しては賛否が分かれる。個人的には技巧面の粗さや、量感の乏しい、皺枯れた響きがしないでもないが、人間性がそれを補って余りあると思う。 また、この盤ではワルターが指揮しているという事も大きな魅力だ。基本テンポは速目だが、旋律群はワルターならではの人間味溢れる歌心を充分感じさせるし、強奏部は柔らかみを湛えつつも、豪快な力強さも感じさせ、造型性も豊かで、シゲティのヴァイオリンを大きく包み込んで行く。録音も年代を考えれば上々の部類で、この協奏曲の代表的名盤の一つとして今でも充分通用すると思うので、一度は聴いておいて損はない。 クーレンカンプ 〜私の所有盤〜 ①(CD)『フルトヴェングラー〜ザ・レガシー』 ベルリンPO他 Membran 233110 ②(CD)シューマン:ヴァイオリン協奏曲他 ベルリンPO他 Podium POL-1053 ゲオルク・クーレンカンプはブレーメンに生まれ、1916年にはブレーメン・フィルのコンサート・マスターに就任している。1925年からは後進の指導にも力を注ぎ始めるが、彼の活動の中で最も有名なのはE・フィッシャー(P)とマイナルディ(Vc)とのトリオと、②に収められているシューマン:ヴァイオリン協奏曲の初演である。何れにせよ、生前はドイツを代表するヴァイオリニストであったクーレンカンプだが、録音が少ないせいか、今では名のみ高く、彼の演奏を聴いた事があるという人は減りつつある。それでは、私の所有ディスクについて触れる事にしよう。 ①には1943年録音のシベリウス:ヴァイオリン協奏曲(フルトヴェングラー〜ベルリン・フィル)が収められている。これは録音は古いし、北欧的とは言いかねるが、クーレンカンプもフルトヴェングラーも造型を重んじつつ、ドイツ・ロマン派的濃厚な語り口で聴き手に忘れ難い印象を残す為、今でも知る人ぞ知る名盤として独特の存在感を誇っている。個人的には作品を語る上で是非とも一度は聴いておくべき演奏という気がする。 ②には1937年11月26日にナチス主催により行われたシューマン:ヴァイオリン協奏曲(ベーム〜ベルリン・フィル)の世界初演のライヴと1935年録音のシューマン:12のピアノ小品から「夕べの歌」(ヴァイオリン版:イッセルシュテット〜ベルリン・フィル)が収められている。先ず協奏曲に関して、クーレンカンプはヒトラーが好んだヴァイオリニストという事もあって、歴史的な世界初演を委ねられる事に成ったらしいが、ナチス主催という事に反発してフルトヴェングラーが指揮を断った為、ベームにお鉢が回って来たらしい。聴いてみると、録音はノイズが多いし、管弦楽が今一つ遠いし、Ⅱ楽章では放送局の人らしい話し声が入っているし、決して聴き易いとは言えないが、クーレンカンプのヴァイオリンは比較的よく拾われていて、鮮度の高さ、造型の明確さ、その中で繰り広げられる「これぞ、ドイツ・ロマン派」と言いたく成る感情表現は独特の存在感があり、現在の耳で聴いても聴き応えは充分。ベーム〜ベルリン・フィルも弱音部は細部のニュアンスが聴き取り辛いが、造型性や力強さなど、流石ベームと思わせる魅力があり、史料的価値だけにとどまらない聴き応えがある。放送局のアナウンスやクーレンカンプのインタビューがおまけで入っているのはご愛嬌。因みに、この歴史的初演後、クーレンカンプはテレフンケンにスタジオ録音も行っているが、ベームはEMI系のエレクトローラ所属だった為、イッセルシュテットが指揮を受け持つ事に成った(これは現在の所、未聴)。そのイッセルシュテットとの「夕べの歌」は3分程の短い曲だが、クーレンカンプはロマンティックでありながら、造型も明確にして流石と思わせるし、イッセルシュテット〜ベルリン・フィルもスタジオ録音という事もあって、協奏曲でのベーム〜ベルリン・フィルよりは聴き易い。しかし、個人的にこのディスクで一番不満なのは、1枚なのに4000円程もする事。歴史的価値や分厚いブックレットが同梱に成っているという事を考慮に入れても、別にSACDという訳でもないのに高過ぎる。それ故、普通の値段であれば必聴盤としていただろうが、この値段では興味のある人はどうぞとしか言えないのが残念。 ダーメン 〜私の所有盤〜 ・(CD)『カール・ベーム独EMI録音集』 ドレスデン国立O他 ワーナー(旧EMI) 9029588672 ヤン・ダーメンは1920年からベルリン・フィル、1924年からドレスデン国立管、1948年からコンセルトヘボウ管のコンサート・マスターを歴任しているが、此処では彼がドレスデン時代に当時総監督だったベームの指揮で1938年に録音したモーツァルト:ヴァイオリン協奏曲5番『トルコ風』が収められている。 録音は年代を考えれば比較的鑑賞度が高く、ダーメンの独奏はロマンティックで味わい深く、古き佳き時代の香りを感じさせるし、ベーム〜ドレスデンは優れた様式感や味わい深さで充分作品の魅力を伝えてくれる。一度は聴いておいて損はない。 シュトループ 〜私の所有盤〜 ・(CD)『カール・ベーム〜マエストロ・デサント』 ドレスデン国立O他 TIM 220824-303 此処にはシュトループがSP時代の1939年にベーム〜ドレスデン国立管と録音したベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲が収められている。ドイツのマインツ生まれのマックス・シュトループは1921年にシュトゥットガルト歌劇場、1922年にドレスデン国立管、1928年にベルリン国立歌劇場のコンサート・マスターに就任。シュトループ四重奏団や”女帝”エリー・ナイ、ルートヴィヒ・ヘルシャーとのトリオの活動でも知られ、指導者としても活躍。今ではあまり知名度が高いとは言えないが、この録音が行われた当時、ドイツでは比較的有名なヴァイオリニストの一人であった。また、そうであればこそ、この録音で独奏に起用されているのである。 シュトループは技巧の高さや磨き抜かれた美しい響きよりは内容重視のタイプだった様で、このディスクでも粗さが感じられる一方で、力強さや中身の濃さ、スケールの大きさが感じられる。シゲティの様な高潔な精神性を湛えているという訳ではないが、今では得難い古き佳きドイツの姿を伝えていると言えるのではなかろうか。ベーム〜ドレスデンも男性的な力強さに溢れる演奏を繰り広げており、録音の古さを超えた聴き応えがある。一度は聴いておいて損はない演奏だと思う。 フランチェスカッティ 〜私の所有盤〜 ①(CD)『ブルーノ・ワルター・エディション』 コロンビアSO他 SONY S70891C ②(CD)『ブリティッシュ・ミュージック・コレクション』 フィラデルフィアO他 SONY 88883737182 ①には1958年録音のモーツァルト:ヴァイオリン協奏曲3番&4番(ワルター〜コロンビア響)と1959年録音のブラームス:二重協奏曲(チェロ:フルニエ、ワルター〜コロンビア響)が収められている。 フランチェスカッティはフランスのマルセイユ出身だが、その名が示す通りイタリア系である。彼にヴァイオリンを教えた父フォルトゥナートは音楽史上最高のヴァイオリニスト、パガニーニの弟子カミッロ・シヴォリを師に持つヴァイオリニストだったから、ジノは、パガニーニの曾孫弟子という事に成る。そして、彼はパガニーニを得意とする技巧派として活躍。勿論、イタリア系らしく旋律を歌心たっぷりに演奏するのも彼の武器であった。一方で、パリではティボーと出会い、フランスの伝統的奏法も学んでいる。 勿論、このディスクでもフランチェスカッティは技巧の安定感と美音と歌心溢れる旋律群で聴き手を魅了する。モーツァルトの協奏曲2曲に関しては、ワルターが指揮をしているという事もあって、未だに最高の名演と評価する向きもある位だ。ブラームスはワルターが全体を大らかに、そして豊かに演奏する中、フランチェスカッティとフルニエが大指揮者に従いつつも、各々の持ち味を充分に発揮しており、それが魅力と成っている。勿論、何れも一度は聴いておいて損はない。 尚、先述の如く、フランチェスカッティはパガニーニを得意としていた他、カサドシュとのデュオやワルターとのベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲の録音なども有名だが、これらは現在の所未聴である。 ②には1959年にオーマンディ:フィラデルフィア管と録音したウォルトン:ヴァイオリン協奏曲が収められている。この作品を作曲者に依頼し、初演も行ったハイフェッツを始め、他は聴いた事がないので、何とも言えない部分はあるが、フランチェスカッティは旋律群の美しさや味わい深さ、技巧の高さ、何れも申し分なく、協奏曲には定評のあるオーマンディ〜フィラデルフィア管が伴奏を務めているのも魅力で、この協奏曲を語る上で一度は聴いておいて損はないと思う。 ゴールドベルク 〜私の所有盤〜 ・(CD)『リリー・クラウス/パーロフォン、デュクレテ・トムソン、ディスコフィル・フランセ録音全集』 L・クラウス(P)他 WARNER ERATO 2564624223 此処には1937年から1939年にかけて録音されたモーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ24、33、34、35、39、36、41番と1936年から1937年にかけて録音されたベートーヴェン:ヴァイオリンソナタ2、5、6、9、10番、1939年に録音されたハイドン:ピアノ三重奏曲40、43、45番が収められている。これは20世紀を代表する女流ピアニスト、リリー・クラウスの激安31枚組BOXに含まれる演奏で、ピアノは当然リリー・クラウス。ハイドンの三重奏曲に関してはアントニー・ピーニがチェロを受け持っている。 ポーランド出身のゴールドベルクは12歳でワルシャワ・デビューし、センセーションを巻き起こし、1925年に16歳にしてドレスデン・フィルのコンサート・マスターに就任。1929年にはフルトヴェングラーの熱望により、20歳にしてベルリン・フィルのコンサート・マスターに就任している。また、ヒンデミットやフォイアマンとの弦楽三重奏やリリー・クラウスとのデュオによる活動でも有名に成る。しかし、ナチスの台頭により、1934年にベルリン・フィル退団に追い込まれ、1938年にソリストとしてニューヨーク・デビュー。戦時中はアジア演奏旅行中にジャワ島で日本軍に抑留されるが(リリー・クラウスも家族もろともジャワ島で軟禁されている)、戦後1953年に米国に帰化し、ヴァイオリニスト、指揮者、教育者として幅広い活動を展開して行く。 何れにせよ、このBOXでは当時評判と成ったリリー・クラウスとのデュオを聴く事が出来る。ゴールドベルクは作品に対して真摯に向き合いつつ、愛情を込めて演奏しており、古い録音ながら当時評判と成った艶のある美しい響きの一端も味わえる。 リリー・クラウスのピアノも古い録音ながら真摯に作品に向き合いつつ、愛情を込めて演奏しており、また日頃デュオを組んでいる強みで、コンビネーションもバッチリだ。何れも一度は聴いておいて損はない。 ボスコフスキー 〜私の所有盤〜 ・(CD)『リリー・クラウス/パーロフォン、デュクレテ・トムソン、ディスコフィル・フランセ録音全集』 L・クラウス(P)他 WARNER ERATO 2564624223 此処には1954年から1955年にかけて録音されたモーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ1、12、17〜22、24〜30、32〜43番、1954年に録音されたモーツァルト:ピアノ三重奏曲K.254、442、496、502、542、548、564番、1955年に録音されたモーツァルト:ピアノ協奏曲9、20番、1955年に録音されたベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ全集、1957年に録音されたシューベルト:ヴァイオリンとピアノの為のソナチネ1〜3番が収められている。 リリー・クラウスのBOXという事で、ピアノは当然リリー・クラウス。三重奏曲ではニコラウス・ヒューブナーがチェロを務め、協奏曲ではボスコフスキーがウィーン・コンツェルトハウス室内管を指揮している。尚、指揮者としてのボスコフスキーは指揮者編に記載する事にして、此処では割愛する。 ボスコフスキーはウィーンのヴァイオリニストの系譜を受け継ぐ一人であるが、ウィーンのヴァイオリニストの系譜には1881年から1938年迄ウィーン・フィルの第一コンサート・マスターとして君臨したアルノルト・ロゼのヴィヴラートを抑制して純音楽的な高潔な美を体現する系譜と、ウィーン・フィルの入団試験に落とされるもヴィヴラートをたっぷりかけ、甘美な音色によるロマンティックな表現で世界的名声を博したクライスラーの系譜があり、ボスコフスキーは後者に属するとされる。 ボスコフスキーは1933年にウィーン・フィル入団、1939年にコンサート・マスターと成り、そして1949年には退団したシュナイダーハンの後任として第一コンサート・マスターに就任。以後、定年を迎える1970年迄その職にあった。ロゼの系譜を受け継ぎ、若くしてソリストとして歩み始めたシュナイダーハンと、あくまでウィーン・フィルに在籍しつつ、ソロや室内楽、指揮などの活動に取り組んだボスコフスキー。共にそれなりの分量の録音が遺されている事は、ウィーンを愛する私にとっては有難い。 それはさておき、このBOXでのボスコフスキーの演奏だが、同じBOXに収録されているゴールドベルクがシュナイダーハンに近いヴィヴラートを控え目にしたスタイルなのに対し、ヴィヴラートをたっぷりとかけ、旋律を甘美にかつ豊かに歌わせているのがボスコフスキーらしい。但し、ヴィヴラートに関してはロゼの系譜とクライスラーの系譜という違いはあるが、その他の要素に関してはシュナイダーハン同様ウィーンのヴァイオリニスト共通の伝統も感じる。 ゴールドベルクの頃に比べて(尤も、ゴールドベルクとボスコフスキーは同じ1909年生まれだが)録音が良く成っている事も魅力で、ボスコフスキーのヴァイオリンだけでなく、リリー・クラウスのピアノも透明な美しさや感情の豊かさがより感じられる。名コンビとして知られたゴールドベルクとのデュオは勿論、このボスコフスキーとのデュオによる一連の録音も一度は聴いておいて損はない。 リッチ 〜私の所有盤〜 ①(CD)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ニューヨークPO他 LANNE LHC-7064 ②(CD)『アンセルメ/フランス音楽集』 スイス・ロマンドO他 ユニヴァーサル 4807898 ③(CD)『アンセルメ/ロシア音楽集』 スイス・ロマンドO他 ユニヴァーサル 4820377 ①には1962年録音のメンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲(ベーム〜ニューヨーク・フィル)が収められている。 エア・チェック音源で、音声信号の歪みがあるなど、お世辞にも聴き易い録音とは言い難いが、リッチのヴァイオリンはイタリア系らしい情熱と旋律群の美しい響きと歌心が魅力的。ベームはこの時期の巨匠らしい構築性の高さと逞しさすら感じさせる男性的な響きが独特の豪快さを齎しており、メジャー・レーベルからの発売を是非とも実現して欲しい演奏だ。勿論、一度は聴いておいて損はない。 ②にはアンセルメ〜スイス・ロマンド管と1959年に録音したラヴェル:ツィガーヌとラロ:スペイン交響曲が収められている。 ③にはアンセルメ〜スイス・ロマンド管と1966年に録音したチャイコフスキー:管弦楽組曲3番&4番『モーツァルティアーナ』、1958年録音のプロコフィエフ:ヴァイオリン協奏曲1番&2番が収められている。 ②と③はリッチならではの情熱と美的感覚に加えて、アンセルメ〜スイス・ロマンド管ならではの知的なアプローチと透明感及び色彩感溢れる響きが上品な仕上りを齎しており、何れも一度は聴いておいて損はない。 ヴァルガ 〜私の所有盤〜 ①(CD)『フリッチャイ/DG録音全集1』 ベルリンPO他 DG 4792691 ②(CD)『フリッチャイ・コンダクツ・バルトーク』 RIASSO他 Audite AU21407 ①には1950年録音のバルトーク:ヴァイオリン協奏曲2番(フリッチャイ〜ベルリン・フィル)が、②には1951年録音のバルトーク・ヴァイオリン協奏曲2番(フリッチャイ〜RIAS響)が収められている。ティボール・ヴァルガ国際ヴァイオリン・コンクールにその名を留めるハンガリーの名ヴァイオリニスト、ヴァルガとハンガリー出身の名指揮者フリッチャイによるハンガリーを代表する作曲家バルトークの作品という事で、①②何れも高い価値を持っている。各々の特徴を挙げるとすると、①はスタジオ録音という事や、管弦楽がベルリン・フィルという事で、音楽的完成度の高さに優れ、②はライヴならではの自由さや情熱の高まりが聴かれると言えるのではなかろうか。バルトークへの尊敬の念や愛情がひしひしと伝わって来るのは①②共通である。という訳で、共にバルトークを語る上で必聴盤だと思う。 コーガン 〜私の所有盤〜 ①(CD)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲他 ベルリン放送SO他 日本コロムビア COCO-73297 ②(CD)『ショスタコーヴィチの芸術/第二集』 ソ連国立SO他 Venezia CDVE00513 ①にはマゼール〜ベルリン放送響と1974年に録音したメンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲とブルッフ:ヴァイオリン協奏曲1番が収められている。 コーガンはミルシテイン、オイストラフ、スターンらに続くウクライナ出身の大ヴァイオリニストである。1936年、12歳の時に旧ソ連を訪れたティボーやシゲティに絶賛され、1941年に公式デビューを飾った当初は「魔神と契約した天才」と称される程だったという。妻はウクライナ出身の大ピアニスト、エミール・ギレリスの妹でヴァイオリニストのエリザヴェータ。息子パヴェルはヴァイオリニストから指揮者に転向して活躍。娘のニーナもヴァイオリニストとして活躍している。 コーガンは卓越した技巧と内容の豊かさを併せ持ち、今尚懐かしむファンが少なくないが、このディスクはそんなコーガンの代表的な録音の一つとして親しまれている。響きも技巧も冴え渡り、正に銘刀の切れ味といった感じだが、決して技巧一辺倒ではなく、微妙に移り変わる表情や呼吸の妙などに充分感情面の豊かさも感じられる。しかも、決して曲芸や感情過多に陥らない格調の高さがある。 マゼール〜ベルリン放送響の伴奏は録音が若干抑え気味の上、輪郭線がやや不鮮明なのが残念だが、豊かな演奏を繰り広げ、コーガンの微妙な変化にもさり気なく対応している所は流石で、作品全体を高い水準で纏めている。これらの協奏曲を語る上で、一度は聴いておいて損のないディスクである。ただ、個人的にはこのコンビでチャイコフスキーの協奏曲を聴いてみたかった(シルヴェストリ〜パリ音楽院管との録音はあるが未聴)。 ②には1960年にコンドラシン〜モスクワ・フィルと行ったショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲1番のライヴが収められている。録音は今一つながら、コーガンの技巧の冴えと内容の豊かさは充分感じ取れるし、コンドラシンは如何にもこの人らしい真摯にして過不足のない表現で作品の魅力を引き出している。一度は聴いておいて損はない名演だ。 スーク 〜私の所有盤〜 ①(CD)ブラームス:二重協奏曲 チェコPO他 日本コロムビア COCQ-84802 ②(CD)チャイコフスキー:ピアノ三重奏曲『偉大なる芸術家の思い出の為に』 スーク・トリオ 日本コロムビア COCO-73128 ①には1963年録音のブラームス:二重協奏曲(チェロ:ナヴァラ、アンチェル〜チェコ・フィル)が収められている。 所謂ドイツ的・オーストリア的な重厚で構築感の強い演奏ではないが、造型性は豊かだし、独奏陣も指揮者も節度のあるスタイルで、品格の高さを感じさせ、一度は聴いておいて損のない好演に仕上がっていると思う。 ②には1976年録音のチャイコフスキー:ピアノ三重奏曲『偉大なる芸術家の思い出の為に』(スーク・トリオ)が収められている。 私はこの作品のディスクでは他に1950年録音のルービンシュタイン〜ハイフェッツ〜ピアティゴルスキーという超豪華布陣による演奏を持っているが、それは正に異なる個性を持つ大家同士の協演に仕上がっているのに対し、こちらはチームとしての一体感が何と言っても魅力に成っている。知情意のバランスが取れており、作品を語る上で必聴盤と言えるのではあるまいか。 アッカルド 〜私の所有盤〜 ①(CD)モーツァルト:フルート四重奏曲全集 ランパル他 SONY SICC-30108 ②(CD)パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲全集他 ロンドンPO他 DG 463754 ①は1986年録音のモーツァルト:フルート四重奏曲全集である。フルートにランパル、ヴァイオリンにスターン、チェロにロストロポーヴィチ、それにアッカルドのヴィオラという超豪華布陣による録音で当時は大いに話題と成った。 これはあくまでランパルのフルートが主役の録音だが、スターンやロストロポーヴィチがそうした中で各々の特色を控え目ながら打ち出しているのに対し、アッカルドはヴィオラという事もあって、サポートに徹している感がある。作品を語る上で一度は聴いておいて損のないディスクである事は確かだ。 ②には1975年から1976年にかけてデュトワ〜ロンドン・フィルと録音したパガニーニ:ヴァイオリン協奏曲全集(1番〜6番)と1975年から1977年にかけて録音された24の奇想曲(カプリース) op.1、ヴァイオリンと管弦楽のためのソナタ『タ・プリマヴェッラ』op.30、マエストーサ・ソナタ・センティメンターレ、ウェイグルの主題による変奏曲付きソナタ、ロッシーニの『シンデレラ』のアリアによる序奏と変奏、魔女たちの踊り op.8、ナポレオン・ソナタ、ロッシーニの『タンクレディ』のアリアによる序奏と変奏、無窮道 op.11、パイジェッロの『わが心はうつろになりて』による変奏曲、驚異の二重奏 op.20、『ゴッド・セイヴ・ザ・キング』による変奏曲 op.9が収められている。元々は単発で協奏曲1番と2番のカップリング(ユニヴァーサル UCCG-5130)を持っているのみだったが、ワゴンセールでこのBOXが特価で売られていたのを見て、購入。 音楽史上最高最大のヴァイオリニストとされるパガニーニは同時代や後世の作曲家に大きな影響を与えた事でも知られているが、録音を行う演奏家は思いの外少ない。そうした中、アッカルドはデビュー当時”パガニーニの再来”と絶賛され、またパガニーニをレパートリーの中心に据え、スペシャリストとして知られている。ただ、パガニーニが正に時代の覇者として圧倒的な存在感と人気を誇ったのに対し、アッカルドはクライスラーやハイフェッツ、オイストラフなどの過去の大家やパールマン、クレーメル、ムターなどの現役スターの影に隠れてしまっている感がある。 ②を聴くと、アッカルドが難しい箇所もサラリと弾きこなす卓越した技巧とイタリア人らしい美的感覚の持ち主である事は明らかだが、若しかするとパガニーニのスペシャリストというイメージが強く成り過ぎて、他の作曲家の作品の演奏に関する評価が今一つなのかも知れない。①と②以外聴いた事がないので、こういう書き方しか出来ないが。何れにせよ、②はアッカルドの協奏曲や独奏曲における技巧の高さやイタリア的歌心は勿論、協奏曲におけるデュトワの指揮も豊かな色彩感と明晰な表現でアッカルドの独奏に劣らず高い水準を示しており、パガニーニを語る上で必聴のBOXである事は確かだと思う。 ズーカーマン(ズッカーマン) 〜私の所有盤〜 ①(CD)『スターン・プレイズ・モーツァルト』 イギリス室内O他 SONY 88765429342 ②(CD)『パールマン録音集』 ニューヨークPO他 SONY 88765438882 ③(CD)『デュトワ/ベルリオーズ・マスターワークス』 モントリオールSO他 DECCA 4785577 ④(CD)『ブリティッシュ・ミュージック・コレクション』 ロンドンPO他 SONY 88883737182 ⑤(CD)『スラットキン/エルガー作品集』 セントルイスSO他 SONY 88883737202 ①には1973年録音のモーツァルト:2台のヴァイオリンの為のコンチェルトーネK.190(Vn1:スターン、バレンボイム〜イギリス室内管)、1971年録音のモーツァルト:協奏交響曲K.364(Vn:スターン、バレンボイム〜イギリス室内管)が収められている。尚、協奏交響曲ではズーカーマンはヴィオラを受け持っている。 ②には1980年録音のヴィヴァルディ:3つのヴァイオリンのための協奏曲ヘ長調RV.551(ヴァイオリン:スターン及びパールマン、メータ〜ニューヨーク・フィル)、 1990年録音のモーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための二重奏曲第1番&第2番(ヴァイオリン:パールマン)、ルクレール:ソナタ へ長調 Op.3-4(ヴァイオリン:パールマン)、 1978年録音のベートーヴェン:セレナード Op.8、ドホナーニ:弦楽三重奏曲『セレナード』 Op.10(ヴァイオリン:パールマン、チェロ:リン・ハレル)が収められている。これらの内、ズーカーマンはモーツァルトの二重奏曲2曲とベートーヴェン及びドホナーニの『セレナード』に関してはヴィオラを担当している。 ①と②はスターンやパールマンのサポートをしている演奏ばかりで、ズーカーマンを語る上で必ずしもそれに相応しいサンプルとは言えないが、彼が美しい響きでアンサンブルの充実に重要な役割を果たしている事は誰の耳にも明らかであろう。 ③には1987年録音のベルリオーズ:交響曲『イタリアのハロルド』(デュトワ〜モントリオール響)が収められている。 ズーカーマンは此処ではヴィオラを担当しているが、私が所有するズーカーマンのディスクの中で、現在の所唯一主役を務めている演奏である。個人的にはズーカーマンの独奏は美しい響きでデュトワ〜モントリオール響の明晰かつ色彩感溢れるスタイルと違和感なく融け合っていると思う。この作品にはトスカニーニやミュンシュ、マルケヴィチやバーンスタイン、コリン・デイヴィスなど名盤が多いが、これも一度は聴いておいて損はない演奏だと言えるだろう。 ④には1976年にバレンボイム〜ロンドン・フィルと録音したエルガー:ヴァイオリン協奏曲、⑤には1988年から1992年にかけてスラットキンが録音したエルガー作品集に含まれる1992年録音のスラットキン:セントルイス響とのエルガー:ヴァイオリン協奏曲が収められている。ズーカーマンはこの後2006年にメータ〜イスラエル・フィルとのこの協奏曲をライヴ録音しているらしいが、未聴。何れにせよ、こうしてしばしば録音を行っているという事は、それだけズーカーマンがこの協奏曲を得意にし、高く評価されていたという事の証でもある。 因みに、私がこの協奏曲で他に持っているのは、EMIがボールトのエルガーの録音を纏めた19枚組に含まれるメニューイン独奏の演奏とイダ・ヘンデル独奏の演奏のみで、多くを語る事は出来ないが、ズーカーマンは④では20代の若々しい表現意欲が、⑤では40代と成ったズーカーマンの成熟ぶりが魅力と成っており、また繰り返しこの協奏曲を録音して来た様に、作品への愛情も感じさせるのが良い。指揮に関しては、古き佳き時代の英国紳士的なボールトが正調だと思うが、ロマン派的でズーカーマンに劣らず若々しい表現意欲を感じさせるバレンボイム、現代的機能性と透明な抒情性で聴かせるスラットキンも各々魅力的で、何れも作品を語る上で一度は聴いておいて損はない。 ミンツ 〜私の所有盤〜 ・(CD)パガニーニ:24のカプリース ユニヴァーサル UCCG-5141 此処には1981年録音のパガニーニ:24のカプリース全曲が収められている。 これは当時20代だったイスラエル出身のミンツの技巧の高さや美しい響きで話題と成った録音らしく、アッカルドの様なイタリア的な歌心は感じないが、若者とは思えない音楽的水準の高い名演であり、作品を語る上で一度は聴いておいて損はないと思う。 シャハム 〜私の所有盤〜 ・(CD)コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲 ロンドンSO他 Eloquence 4823438 これはプレヴィンがロンドン響とDGに録音したコルンゴルト作品を纏めた2枚組に含まれる演奏で、イスラエル生まれのギル・シャハムは1993年録音のヴァイオリン協奏曲の独奏を務めている。 この作品はハリウッドで映画音楽作曲家として活躍する様に成っていたコルンゴルトが、1945年にフーベルマンの勧めで書き上げたクラシック作品であり、1947年に不世出のカリスマ、ハイフェッツが世界初演、1953年にはウォーレンスタイン〜LAフィルと録音も行っている。しかし、後期ロマン派に属するその作風が時代錯誤とされた上、映画音楽の素材を幾つか用いている事で低俗と見なされ、ハイフェッツをもってしても、この協奏曲は一部の人を除き、あまり顧みられなかった。漸く1970年代に入り、コルンゴルトの映画音楽作曲家としての功績の大きさが見直される様に成り、更にケンペ〜ミュンヘン・フィルによる交響曲やラインスドルフ〜ミュンヘン放送管他による歌劇『死の都』の録音で、クラシック作品も注目される様に成り、ヴァイオリン協奏曲も評価される様に成って来て、録音も幾つか行われる様に成った。 そして、ヴァイオリン協奏曲に改めて光を当て、その普及に大きく貢献したとされるのが、このシャハム〜プレヴィン〜ロンドン響盤である。因みに、プレヴィンはコルンゴルト作品普及に尽力した演奏家の一人とされ、この演奏が収められている2枚組セットからもそれは窺い知れるが、ヴァイオリン協奏曲は他に1980年にパールマン独奏で録音したピッツバーグ響盤と2003年に当時妻だったムターの独奏で録音したロンドン響盤がある。ただ、前者はパールマンの演奏や録音にやや問題があるとされ、後者はムターの独奏がやや恣意的で濃厚過ぎるとされ、このシャハム盤をプレヴィンの3種類の録音の中でのベストは勿論、作品の決定盤に推す向きが少なくない。私はパールマン盤やムター盤は聴いていないので、何とも言えないが。 それはさておき、演奏について語ろう。私がこの録音を購入する前に所有していたのは、先述のハイフェッツ盤のみであった。これは如何にもハイフェッツらしく、きびきびとしたテンポで、一見サラリと進んで行くが、きちんと旋律美も堪能させてくれるし、バックを務めるウォーレンスタイン〜LAフィル共々同時代人的共感と古き佳きロマンを伝えてくれる流石の名演である。ただ、1953年の録音なので、当時としては悪く無い音質ではあるが、管弦楽を堪能するという意味では若干物足りない所がある。一方、このシャハム〜プレヴィン〜ロンドン響盤は音質、独奏と管弦楽のバランス、何れも優れており、プレヴィン〜ロンドン響の精緻にして豊潤な響きがこの協奏曲の後期ロマン派的側面と数々の映画音楽からの素材の魅力を充分に伝えてくれる。シャハムはそうした強力なサポートを得て、旋律群では慈しむ様にその美しさや感情の機微を引き出し、軽快な部分では技巧の確かさと華を感じさせる。録音当時、シャハムはまだ22歳という事を考えると、この内容は驚異的と言える。この盤とハイフェッツ盤以外、他にこの協奏曲の録音を聴いていないので、何とも言えない部分はあるが、これもハイフェッツ盤と共に必聴の名盤と言えるのではなかろうか。 |