





BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。
ヨハン・シュトラウスⅡ世
| ワルツ&ポルカ | 喜歌劇『蝙蝠』 |
| ① | |
 | A・喜歌劇『千一夜物語』間奏曲/ |
| B・『皇帝円舞曲』作品437 | |
| ドレスデン国立管弦楽団 | |
| 1938年(a)、1939年(b)、ドレスデン | |
| PALLADIO PD 4119/20 | |
| ② | |
 | A・『常動曲』作品257/ |
| B・ワルツ『南国の薔薇』作品388 | |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1943年、ウィーン | |
| VIBRATO VHL 36 | |
| ③ | |
 | A・ワルツ『南国の薔薇』作品388/ |
| B・ワルツ『朝刊』作品279/ | |
| C・ワルツ『天体の音楽』作品235(ヨーゼフ・シュトラウス) | |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1949年、ウィーン | |
| PREISER RECORDS MONO 90613 | |
| ④ | |
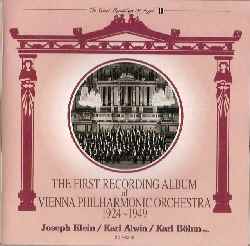 | 『ノイエ・ピツィカート・ポルカ』作品449 |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1949年3月17日、ウィーン | |
| EMI SGR-8243 | |
| ⑤ | |
 | A・『皇帝円舞曲』作品437/B・『ペルシャ行進曲』作品289/ |
| C・『ピツィカート・ポルカ』(ヨハン&ヨーゼフ・シュトラウス)/D・『常動曲』作品257/ | |
| E・ワルツ『トリッチ・トラッチ・ポルカ』作品214/F・ワルツ『美しく青きドナウ』/ | |
| G・『ラデツキー行進曲』(ヨハン・シュトラウスⅠ世) | |
| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1954年2月11日、ウィーン | |
| LANNE LHC-7128 | |
| ⑥ | |
 | A・ワルツ『美しく青きドナウ』作品314/B・『トリッチ・トラッチ・ポルカ』作品214/ |
| C・『皇帝円舞曲』作品437/D・ポルカ『雷鳴と電光』作品324/ | |
| E・ワルツ『南国の薔薇』作品388/F・『ピツィカート・ポルカ』(ヨハン&ヨーゼフ・シュトラウス)/ | |
| G・『アンネン・ポルカ』作品117/H・『常動曲』作品257 | |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1971年9月18日、1972年9月4〜5日、ウィーン | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) 3111-7 | |
| ⑦ | |
 | A・ワルツ『美しく青きドナウ』作品314/B・『トリッチ・トラッチ・ポルカ』作品214 |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1975年3月17日(a)、3月25日(b)、東京 | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCG-3118 | |
| ⑧ | |
 | A・ワルツ『美しく青きドナウ』作品314/B・ワルツ『南国の薔薇』作品388/ |
| C・『アンネン・ポルカ』作品117/D・『皇帝円舞曲』作品437/ | |
| E・『常動曲』作品257/F・『ピツィカート・ポルカ』(ヨハン&ヨーゼフ・シュトラウス) | |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1975年3月16日(a)、1975年3月25日(b〜f)、東京 | |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) POCG-90491/7 | |
| ⑨ | |
 | A・ワルツ『南国の薔薇』作品388/B・『アンネン・ポルカ』作品117/ |
| C・『ピツィカート・ポルカ』(ヨハン&ヨーゼフ・シュトラウス)/D・『常動曲』作品257/ | |
| E・ワルツ『美しく青きドナウ』作品314/F・『皇帝円舞曲』作品437 | |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | |
| 1975年6月15日、ウィーン | |
| Papageno様個人所有音源 RCDC 80578F-0T | |
| 欧州最高の名門ハプスブルク家が栄華を誇った”音楽の都”ウィーン。モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、ブルックナー、ブラームス、マーラー、R・シュトラウスら大作曲家達が連綿と栄光を築き上げ、リヒター、マーラー、R・シュトラウス、シャルク、ワインガルトナー、ワルター、フルトヴェングラー、クナッパーツブッシュ、クラウス、ベーム、カラヤン、バーンスタイン、ショルティ、アバド、ラトルら幾多の指揮者が活躍してきたウィーン・フィルを擁する世界に類を見ない都。 しかし、一般的に最もウィーンを象徴するイメージとして思い浮かべられる音楽はウィンナ・ワルツであり、中でも”ワルツ王”ヨハン・シュトラウスⅡ世の作品であろう。 それは芸術的に高いとか低いとか、好きとか嫌いといった事ではなく、もはや”ウィーン”そのものであるとさえ言える。だからこそ、ワルツ王の作品がズラリと並べられるウィーン・フィルのニューイヤー・コンサートが全世界の5億とも10億ともいわれる人々の耳目を集め続けているのである。 人々はウィンナ・ワルツによってドナウの流れやウィーンの森、庶民が集う屋外のカフェ、そして黄昏ゆくハプスブルク家の宮廷大舞踏会に思いを馳せる。その魅力は大衆だけでなく、同じ時代を生きた多くの作曲家に愛され、影響を与えた程だった。確かにウィンナ・ワルツは”絶対音楽””芸術音楽”の潮流からは外れた音楽かも知れない。しかし、単なる”大衆娯楽”として切り捨てるのは、”音楽の都・ウィーン”をも否定するに等しい。 但し、これも断っておかねばならないが、ウィーンのイメージを象徴するウィンナ・ワルツに欠かせぬと称されるウィーン・フィルだが、実はニューイヤー・コンサート以外でワルツ王の作品を演奏する事は殆どない。逆に言えば、普段演奏していなくても、この名門のメンバー一人一人にウィンナ・ワルツが染み付いているからこそ、”ウィーンの粋”を体現出来るのである。 大指揮者カール・ベームは生前ドイツ・オーストリア音楽の絶対的権威だった。その巨匠がワルツ王の作品を時折採り上げてきたのも、ウィーンを愛するが故であり、世間がどう思おうとも、彼にとって必要不可欠な作曲家だった。「日本ヨハン・シュトラウス協会」が設立されたのも、ベームが1975年の来日時に提唱したからであり、その事は同協会のHPにも明記してある。 此処でワルツ王の生涯について簡単に触れておこう。 ワルツ王は1825年に”ワルツの父”ヨハン・シュトラウスⅠ世の長男として生まれた。次男ヨーゼフ、三男エドゥワルトも音楽家として成功している事から、バッハ以来の音楽一家とされる。ワルツの父とも称されるⅠ世はヨーゼフ・ランナーと共にウィンナ・ワルツのスタイルを確立させ、当時絶大な人気を誇っていた。勿論、彼らの前にもワルツは存在した。ベートーヴェンやシューベルトも時折ワルツを書いている。楽聖の有名な『エリーゼの為に』もその一つである。これらはウィーン特有の舞曲、即ちレントラーから派生している。ワルツの父やランナーらは、これにウェーバーらの華麗さや軽快さを融合させ、独自のジャンルを確立させた。それがウィンナ・ワルツであり、大作曲家による大芸術とは無縁だった多くの庶民にとって、それは正に最高の娯楽だった。今では『ローレライ〜ラインの響き(調べ)』や『ラデッキー行進曲』が僅かに演奏される程度のⅠ世であるが、楽聖亡き後のウィーンで圧倒的な支持を得ていたのは疑い様も無くワルツの父であった。 中央ヨーロッパにおいて広大な領土を有する欧州最高の名門ハプスブルク家が栄華を誇った帝都ウィーン。ワルツの父は自ら設立したシュトラウス管弦楽団を率いて人々を虜にしていった。そのスタイルはヴァイオリンを弾きながら指揮をするというスタイルで、それがまた粋とされた。やがてワルツの父は宮廷舞踏会楽長に就任する。 ワルツ王や弟達は父の名声が高まるのを目の当たりにしながら成長していった。彼らが自然と音楽に馴染んでいくのは当然の流れであった。しかし、ワルツの父は息子達が音楽家になる事には大反対だった。彼らの味方となったのは母親アンナであり、ワルツ王達は母親から音楽の薫陶を受けたのである。そんなワルツ王に転機が訪れる。ワルツの父が浮気をし、愛人と共に家を出てしまったのである。「災い転じて福と為す」ではないが、ワルツ王は音楽家になる事を猛反対していた父がいなくなったお陰で、音楽に専念する事が出来る様になった。1844年には自らの楽団を設立。ワルツの父の楽団と対立する様になる。 それはこの親子の確執をより深めていった。庶民達がこの2人の対立に興味を示し、それをより煽っていった。そのピークとなったのがウィーン革命(3月革命)と呼ばれる歴史の教科書にも登場する有名な暴動である。この時ワルツの父は旧体制、即ち宮廷派とされ、ワルツ王は庶民派とされた。結果的に暴動は鎮圧されるが、ワルツ王が大衆から広く支持されるきっかけとなった。 革命の翌1849年、ワルツの父シュトラウスⅠ世は世を去る。既にウィーンでは有名な流行作曲家となっていたワルツ王だったが、後世にその名を残す名作が殆どこの後に書かれている事を考えると、或る意味父の死をもって彼の快進撃が始まったと見なす事も出来よう。 彼はワルツの父のシュトラウス管弦楽団を継承。ヴァイオリンを弾きつつ指揮をするスタイルもそのまま受け継ぎ、大量のワルツとポルカを作曲した。1863年には嘗て父が務めた宮廷舞踏会楽長に就任している。3月革命時、民衆派だった彼の楽長就任に、当初皇帝フランツ・ヨーゼフは当然難色を示したが、ワルツ王の粘り強さと音楽の魅力で渋々承諾したらしい。1870年、母アンナと弟ヨーゼフを相次いで亡くす。 ワルツ王の創作活動に一大転機が訪れたのは1871年。オッフェンバックの勧めでオペレッタ(喜歌劇)第一作『インディゴと40人の盗賊(千一夜物語)』を発表し、大成功を収めたワルツ王は、以後オペレッタを創作活動の中心に据え、死ぬ迄に20近い作品を遺している。1872年、アメリカ建国100年祭記念ビッグ・コンサートに招かれ、未曾有の成功を収める。結婚は3度している。3度目の妻となったアデーレこそ、ワルツ王初恋の女性であり、1887年、62歳にして漸くそれが成就したと言われている。1894年、デビュー50周年コンサートが盛大に行われる。そして、1899年。肺炎でワルツ王は世を去るのである。葬儀は音楽家としては類を見ない盛大さだったという。 クラシックの世界において、ワルツ王程生存中に圧倒的な成功を収めた音楽家は他にいない。現代の評論家の中には彼を単なる低俗な娯楽音楽作家と片付ける者がいるが、彼は当時の他のどの作曲家にもない物を持っていた。だからこそ、ワーグナーやブルックナー、ブラームスを始め、多くの作曲家が彼のワルツを愛好し、中にはチャイコフスキーやラヴェルの様にその影響を自らの作品に反映させる者も現れたのである。彼の音楽は正に時代を映す鏡であり、民族運動の高まりや庶民生活に深く根差していた。だからこそ、一過性の流行作品に終わらず普遍性を獲得出来たのである。そうした意味でワルツ王は、ロックやポップスの世界において一時大ヒットを生み出しても忘れ去られるアーティストや曲が多い中、”永遠”の地位を獲得しているエルヴィス・プレスリーやビートルズのクラシック版であると言えよう。ワルツ王の音楽は正に19世紀のウィーンに我々を誘う。だからこそ、”音楽の都”ウィーンを象徴する存在にすら成り得たのである。 それでは、先ず⑥の各作品と演奏について述べよう。 『美しく青きドナウ』はワルツ王の全作品中、最も世界的に有名な作品であり、”第二のオーストリア国歌”とも称される。TVCMや映画、ドラマやヴァラエティーでもしばしば流れているので、これを知らない人間は殆どいないのではないかと思われる程だ。そうした中では、映画『2001年宇宙の旅』が最も有名だろう。この名作ワルツは1867年に書かれた。当時オーストリアはプロイセンに敗れ、帝都・ウィーン市民達はその衝撃に打ちひしがれていた。何とかウィーン児達を励ます明るい希望の音楽が欲しいと考えたヨハン・ヘルベックはワルツ王に合唱付のワルツを依頼する。ワルツ王もヘルベックと思いは同じだったが、それ迄声楽入りのワルツなど書いた事がなかっただけに、大分迷ったらしい。因みにこの時期迄に書き上げたワルツの有名作としては『格言詩(記念の歌)』作品1、『加速度円舞曲』作品234、オッフェンバックの『夕刊』のパロディーとして作られた『朝刊』作品279、『ウィーンのボンボン』作品307等がある。さて、初の声楽入りワルツの構想が中々思い浮かばなかったワルツ王だが、或る日偶然目にしたカール・ベックの詩に強く惹かれ、漸く作曲を決意する。それがこの『美しく青きドナウ』である。初演は合唱付で行われ、圧倒的成功を収めた。しかし、今では管弦楽のみで演奏される事が多い。尤も、元来が歌う事をメインに作られているだけに、メロディー・ラインの歌謡性は充分に感じられる。ベームはこのワルツを何の小細工も施さぬ正攻法で指揮している。それ故、リズムの弾力性や、変化に富んだ”粋”な表現は此処では殆ど聴かれない。その代わり、全体が自然に連なり、大らかな流れを形成している。メロディー・ラインの美しさは流石ウィーン・フィルであり、そこにベームならではの堂々たる風格が加えられている。舞曲として聴いた場合は、もっと華麗で軽快な、そして洒落っ気のある演奏が多々あるが、交響詩を思わせる立派な仕上りを見せるベームの演奏には他からは感じられない独特の存在感がある。 『トリッチ・トラッチ・ポルカ』は運動会や体育祭等でしばしば用いられる軽快な作品である。此処でポルカについて簡単に触れておこう。1830年頃ボヘミアで流行した舞曲の形式がポルカであったとされる。これに独自の味を加え、ウィンナ・ポルカのスタイルを完成させたのがシュトラウスⅡ世なのである。そうした意味で彼は”ポルカ王”でもあった。彼のポルカは日常生活に根差した題材を用いている事が少なくない。それがより大衆的人気を獲得していった。ベーム盤に収録されているポルカは中でも超有名ナンバーと称されるものだが、他ではデビュー・コンサートでも演奏された『こころゆくまで(心からの楽しみ)』作品3、『爆発ポルカ』作品43、『シャンペン・ポルカ』作品211、『浮気心』作品317、『ハンガリー万歳』作品332、『クラップフェンの森で』作品336、『狩』作品373等が知られている。さて、この『トリッチ・トラッチ・ポルカ』はウィーンの主婦達のおしゃべりを表した物である。最初は小さかった話が段々大きくなっていく面白さが魅力と言われている。一般的には快速でカッ飛ばしていくスタイルが多いが、ベームは腰を据えて丹念に演奏している。粋やとびっきり楽しい演奏とは言えないが、ニュアンス豊かな表情はウィーン・フィルならではで、他からは感じられない独特の魅力がある。 『皇帝円舞曲』はワルツ王晩年の傑作である。彼は『美しく青きドナウ』以降も『芸術家の生涯』作品316、『ウィーンの森の物語』作品325、『酒、女、歌』作品333、『千一夜物語』作品346、『ウィーン気質』作品354、『春の声』作品410等を生み出してきた。因みにこの『皇帝円舞曲』の後には『もろびと手をとり』作品443等がある。これらの中で、『春の声』は『美しく青きドナウ』に次ぐ”歌入りワルツ”の傑作として知られている。一方、この『皇帝円舞曲』はチェロの独奏が導入されており、そうした意味でヴァイオリン独奏が挿入された『ウィーン気質』やツィターの音色が印象的な『ウィーンの森の物語』を思い出させる物がある。内容自体、そのタイトルに相応しい威容と華麗さを具えており、TVCMや映画でもしばしば用いられる。中では映画『ラスト・エンペラー』が有名だ。さて、ベームの演奏だが、その風格たっぷりの堂々たるシンフォニックなスタイルが、ワルツとは別種の交響詩的魅力をより高めており、矢張り現代流行のワルツ王のスタイルとは異なる存在感を示している。チェロ独奏を始め、メロディー・ラインの美しさは流石ウィーン・フィルであり、私はこの演奏を気に入っている。 『雷鳴と電光』は喜歌劇『蝙蝠』の劇中でも演奏される雷の音が印象的なポルカの名作。快速ではないが、適度な軽快さはあり、ウィーン・フィルならではの味わいは充分に感じられる。雷撃でやや強面になる所がベームらしい表現であると言える。 『南国の薔薇』は喜歌劇『女王のハンカチーフ』からの素材によって作られている。同様のケースとしては『千一夜物語』等がある。さて、オペレッタからの素材を用いているだけに、歌謡性に優れ、愛好者が少なくない。ベームは例によってワルツというよりは交響詩といった趣の演奏を繰り広げているが、それが逆に懐の深い感動を与えてくれる。冒頭の憧憬溢れる表現からして素晴らしい。中間、リズムが主導権を握る部分ではやや単調かと思わせる部分はあるが、自然に全体が連なっていきつつ、コーダへ向けて大らかに盛り上がっていく様は感銘深く、何物にも変え難い魅力がある。リズムの物足りなさを払拭して余りある名演というべきであり、個人的にはこのワルツで一番好きな演奏だ。 『ピツィカート・ポルカ』はワルツ王と弟ヨーゼフの共作とされるポルカの名曲である。弦のピツィカートだけで書かれているアイディアが独特の個性を感じさせる点が魅力だ。これはチャイコフスキーの第四の3楽章にも絶大な影響を与えている。ベームの演奏は殆どテンポを動かさない例によって”正攻法”のスタイルであるが、其処はパートナーがウィーン・フィルという事もあり、決して単調に陥らぬ様、微妙なニュアンスの変化がつけられている。思いっきりリズムが弾んでくる演奏ではないが、丹念に演奏されている事で逆に細かな息遣いが感じられる演奏であるといえる。 『アンネン・ポルカ』はワルツ王の青年時代の名作として知られている。優美で洒落っ気たっぷりのワルツ王の典型が示されており、様々な機会に用いられている。ベームは例によって洒落っ気たっぷりの変化に富んだスタイルとは異なり、素直に演奏している。勿論、ウィーン・フィルがパートナーだけに適度な優美さはあり、ややもすると”粋”から”大仰”な表現になりがちな演奏が少なくない中、逆にこうした素直な演奏に惹かれる聴き手がいたとしても不思議ではない。 『常動曲』はワルツ王らしい遊び心の詰まった作品として知られている。完全終止のコーダを置かず、エンドレスで繰り返せる様に書かれているのだ。その為、演奏会や録音において、指揮者が最後に「以下この様に続きます」と語るのが慣例となっている。日本でこの作品が親しまれるきっかけになったのは故・山本直純氏が司会を務め、人気を博した音楽ヴァラエティー、『オーケストラがやって来た』のメインテーマとして使用されてからであろう。ベームはウィーン・フィルを信じきった素直な演奏を繰り広げており、このオーケストラならではの魅力を存分に引き出している。最後の語りもベームなりに精一杯愛嬌を振りまいており、或る意味貴重な録音だ。 ワルツ王の名盤といえば、嘗てはクレメンス・クラウス〜ウィーン・フィルが極めつけとされてきた。ニューイヤー・コンサート創始者であり、”純粋培養のウィーン”を体現出来る彼の演奏は、今尚熱い支持を受けている。クラウスを引き継いだボスコフスキーは、元々ウィーン・フィルのコンサート・マスターだっただけに、ワルツ王ばりの”弾き振り”スタイルが人気を博した。管弦楽との一体感も当然優れており、これも高い評価を受けている。他ではニューイヤー・コンサートのライヴ物が世界的人気を博している。マゼール、メータ、ムーティ、アバド、小澤、アーノンクール、ヤンソンスらが毎年話題を提供してきた。そうした中伝説化しているのはカラヤンとカルロス・クライバーである。前者は響きの豪華さ、後者はリズムの天井知らずの躍動感と流麗なメロディーの完璧なバランスが魅力だ。尚、”ウィーン”を象徴するワルツ王の作品だけに、ウィーン・フィルに名盤が多いのは当然だが、それ以外ではベルリン・フィルを指揮したカラヤンや、ベルリン放送交響楽団を指揮したフリッチャイ、シカゴ響を指揮したライナーらが今尚懐かしむ者が少なくない名盤である。 ベームのワルツ王はどちらかと言えば本流から外れた余興と見なす者が少なくない。確かにワルツとして聴いた場合、舞曲としての側面より交響詩的な仕上がりに成っている為、異質の面を感じる聴き手がいる事は確かである。しかし、テンポやダイナミクスをいじくり回して”粋”なふりをしている演奏が多い中、虚飾を排して自然体で作品の構造やニュアンスを伝えてくれるベームに安心感を抱く向きもある。また、表現に違いはあるものの、ベームの演奏からは音楽的本質において、黄昏の時代、19世紀後半の帝都ウィーンの最後の姿が垣間見える。それは正にウィーンの自然に我々を誘い、庶民の息吹を伝え、宮廷の栄華を再現する。だからこそ、現代的”粋”なスタイルが持て囃される一方で、ベームの演奏を愛する者が存在し、再販が繰り返されているのだろう。身贔屓を差し引いたとしても、現代では得難い、外面的魅力よりは真摯に作品の姿を伝えようという姿勢や内面の魅力とウィーンへの愛着、そして同朋的一体感を感じさせる演奏であり、そうした意味においてはヨハン・シュトラウスⅡ世の一つの模範とも言って良いディスクだと思う。 さて、次は⑦の演奏についてである。これは日頃メールで遣り取りしているH.M.様より頂戴した物だ。⑥がスタジオ録音なのに対し、⑦は東京でのライヴである。その為、⑥とはまた別の魅力が感じられる。 『美しく青きドナウ』。これは1975年3月17日の演奏会のアンコールとして披露された。私はベートーヴェンの頁で「むやみにアンコールを行うものではない」と書いているが、それは『レオノーレ3番』の様な作品に関してであって、逆にヨハン・シュトラウスの様なカテゴリーの音楽はアンコールによく合っていると思う。オーケストラが真剣勝負ではなく、楽しみつつ演奏出来るからだ。⑦は⑥同様シンフォニックでスケールが大きいが、演奏会でのアンコールという事で、ベームなりにより楽しんで演奏している事が分かる。特に楽句の切り替わりで微妙な変化が試みられている為、より自由な空気が感じられる。若しかすると、この辺りはウィーン・フィルにかなり委ねていたのかも知れない。そして、ウィーン・フィルの響きも実に血がよく通っており、時折1950年代を思い出させるものがある。何れにせよ、これはベームのワルツ王を白眼視する人達にも是非聴いて欲しい演奏だ。 『トリッチ・トラッチ・ポルカ』。これも1975年の来日時、3月25日のアンコールとして演奏された物である。演奏時間は⑥と殆ど変わらないのだが、⑥がじっくりと落ち着いて細部のニュアンスの豊かさを抽出しているのに対し、⑦はよりベームもウィーン・フィルも張り切っている。その為、時折やたらと強音部が目立つが、それが演奏に熱気を齎している。⑥とは別の意味で楽しめる演奏だ。正にその場でアンコールを聴いている様な感覚が味わえる。「ブラヴォー!」だ。 この⑦のディスクを下さったH.M.様にひたすら感謝したい。 続く⑧もまたH.M.様より贈って頂いた物である。 『美しく青きドナウ』は⑥や⑦に比べてやや低調。随分元気がない。この後に演奏された『マイスタージンガー前奏曲』が悪くないだけに、時差ボケという訳ではなさそうだ。ウィーン・フィルも⑥や⑦に比べるとニュアンスに乏しい。勿論、ウィーン・フィルなりの魅力を感じさせる部分はある。それに何より日本の聴衆の為にわざわざ巨匠と世界最高の名門が披露してくれたアンコールだ。後からは何とでも言えるけれど、当日その場にいた人々はそれなりに楽しめたのではあるまいか。尚、コーダに拍手が被さるのはどうしたものかと思う。 『アンネン・ポルカ』は整然とした趣のある⑥に比べ、よりライヴならではの自由度の高さを感じさせる。この日のベーム〜ウィーン・フィルは割と好調だった様だ。 その事は次の『常動曲』でよりはっきりする。⑥に比べて推進力があり、生命力の強さを感じさせる。勿論、一本調子ではなく、随所にウィーン・フィルがニュアンス豊かな表現を聴かせてくれる。最後にベームが皺がれた声でおどけて「以下この様に続きます」と聴衆に語りかけると、爆笑と拍手が湧き起り、場内がパーッと明るい空気に包まれ、和ませてくれる。ライヴならではの臨場感を味わえる。 『ピツィカート・ポルカ』は⑥に勝るとも劣らない丁寧にしてニュアンス豊かな演奏だ。 しかし、矢張りベームならではの味わいという事になると、『南国の薔薇』と『皇帝円舞曲』を挙げたい。シンフォニックで貫禄充分。それをウィーン・フィルが表情豊かに味付けしている。軽快な舞曲とはスタイルが異なるけれど、内容的かつ感動的であり、これを生で聴いた人達が羨ましい。 因みに私にこのディスクを下さったH.M.様もこの歴史的公演に居合わせて大いに感動したと語って下さった。ベームの1975年のウィーン・フィルとの来日公演といえば、どうしてもシューベルトやブラームス、それにベートーヴェンやワーグナーに注目が集まり、それを語る人が少なくないが、巨匠が楽しみつつ”今尚息づくウィーン”を最も感じさせてくれたのは、この”ワルツの晩”であろう事は疑い様がない。 何れにせよ、H.M.様にはひたすら感謝するのみだ。 ③もまたH.M.様より贈って頂いた。 『南国の薔薇』はベームがワルツ王の作品中、特に好んで採り上げたと思われる物の一つだが、此処でもその愛情が明らかにされている。録音が今一つ拡がらないせいもあり、晩年の様な大きさは感じないが、小ぢんまりとした中で、ウィーン・フィルの何とも言えない表情は充分に明らかにされている。テンポが晩年より早いので、リズムの弾力性はこちらの方がある。しかし、流石に後半の盛り上がりはこの録音では辛い。 『朝刊』もリズムの心地好さは充分に感じられるし、メロディー・ラインもウィーン・フィルらしさがたっぷり出ているのは大きな魅力だが、強奏部には物足りなさを覚える。 『天体の音楽』はワルツ王の弟ヨーゼフの名作。冒頭はそこはかとなく宇宙の神秘的性格を感じさせるが、録音のせいで今一つ空間が拡がって来ないのが残念。主部はウィーン・フィルらしい表現が随所に感じられる。しかし、矢張り録音のせいで今一つ盛り上がりに欠ける事も確かだ。 という訳で、何れもこの時期のウィーン・フィルならではの古き佳き時代の香りを漂わせているのが魅力であるものの、録音への不満が絶えずつきまとう。特にベームは『朝刊』と『天体の音楽』を他に録音していないだけに、余計に悔やまれる。史料以上の価値がある事は確かなのだが。 何れにせよ、③を下さったH.M.様には本当に感謝、感謝である。 ②もまたまたH.M.様より贈って頂いた物である。 『常動曲』は速目のテンポでグイグイたたみかけて行く。壮年時代のベームらしい健康的な演奏と言えるが、録音は良くない。尤も、年代の割には悪くは無い録音であるという見方も出来る。ウィーン・フィルならではの魅力が感じられるからだ。 しかし、何と言っても『南国の薔薇』が素晴らしい。ベームが特に好んで採り上げたワルツ王の作品だけに、既に全体のフォーマットは⑥や⑧と遜色ない完成度の高さを示している。但し、細部の表情の転換が、幾分大きな呼吸を伴っており、一気に加速するコーダを含め、如何にも壮年時代のベームらしい。録音は決して良くないが、年代の割には上々の部類に属する。特に前半はウィーン・フィルならではの美感が何とも言えない。流石に伸びやかなスケールの大きい後半はもう少し録音が良ければ……と思わないではないが。 何れも表記はライヴとなっているが、音の状態の良さからすると、放送録音の可能性が高い。それにしても、戦時中である事を微塵も感じさせない、音楽を純粋に愛し、楽しんでいるこれらの演奏は、全人類の運命を背負っているかの様な戦時中のフルトヴェングラーと対極にある芸術のもう一つの存在意義を示した名演だと思う。言い換えるならば、フルトヴェングラーは現実の過酷さに真っ向から立ち向かい、人々を勇気付け、慰謝するが、ベームは戦争が行われている世界とは異なる一時の夢の世界に我々を誘ってくれるのだ。これを下さったH.M.様には本当に心の底から感謝を捧げたい。 ④もまたH.M.様より2008年12月に贈って頂いたCDである。 『ピツィカート・ポルカ』があまりに有名な為、ともすると忘れられがちな作品ではあるが、喜歌劇『ニネッタ公妃』の素材を用いた如何にもワルツ&ポルカ王ならではの魅力を具えており、そう大きくひけを取らない。 ベーム〜ウィーン・フィルは折り目正しく、気品の高さを漂わせつつ、生真面目一辺倒ではないチャーミングな味わいをも湛えており、流石という内容に仕上げている。録音は良いとは言えないが、ブルックナーやマーラーなどなら兎も角、この位の規模の作品なら、鑑賞するのに何の支障もない。これを下さったH.M.様にはひたすら感謝を捧げるのみである。 ①は2009年7月にH.M.様より贈って頂いたCDである。ドレスデン時代の録音という事もあって、ウィーン的味わいという点においてはウィーン・フィルを指揮した後年の演奏に及ばないが、此処にはまた別の魅力がある。 『千一夜物語』間奏曲はベームにとってこの曲の唯一の録音という事に価値がある。録音も時代を考えれば悪くなく、今でも充分に鑑賞に耐え得る。完成度が高い代わりに、やや遊び心に不足する感があり、オペレッタというよりはオペラの間奏曲を思わせる演奏と成っているのがベームらしい。 『皇帝円舞曲』は後年と比べて、時にぶっきら棒でせっかちな面が感じられるが、先へ先へとずんずん進んで行く若々しさ、勢いの良さを買いたい。尤も、SP時代の事なので、若しかすると収録時間上の制約があったのかも知れない。⑥や⑧の様にニュアンスの豊かさや堂々たる威容を感じさせるという演奏ではないし、録音も流石に⑥や⑧と比べるのは酷だが、此処で聴くべきは若きベームの元気一杯の姿である。録音も時代を考えれば充分に楽しめる。これを下さったH.M.様には何とお礼を述べて良いやら、言葉が見当たらない。 ⑨は2010年1月にPapageno様より贈って頂いたエア・チェックである。ウィーン・コンツェルトハウスの演奏会の記録をNHKが1975年10月27日に放送したものである。この年の春、ベームはウィーン・フィルを率いて来日し、日本のクラシック演奏史上、空前絶後のフィーバーを巻き起こした。その興奮冷めやらぬ時期の放送である。当時多くのファンがラジオに釘付けに成った事であろう。 各々の演奏について簡単に触れておくと、『南国の薔薇』は完成度という点ではスタジオ録音の⑥にやや譲るものの、序奏や後半のスケールの大きさはベームならではのものだし、ライヴならではの呼吸の入れ方が印象的な名演である。 『アンネン・ポルカ』は整然とした趣を持ちつつ、微妙な変化があり、ウィーン・フィルのニュアンスの豊かさもあって楽しめる。 『ピツィカート・ポルカ』はやや音声信号に乱れがあるが、演奏そのものは整然としつつ、ウィーン・フィルならではの微妙な表情の変化が聴かれる。 『常動曲』はベーム〜ウィーン・フィルらしい大きさとニュアンスの豊かさを備えている。 『美しく青きドナウ』と『皇帝円舞曲』はベームが『南国の薔薇』と共にしばしば採り上げたお気に入りのワルツだけに、堂々たる風格を具えつつ、ウィーン・フィルのニュアンスの豊かさを活かしたベームならではの内容と成っている。 何れも、これといった小細工は施さず、音楽の豊かさで聴かせる点はベームならではと言えるし、細部の表現を委ねられたウィーン・フィルの見事さも堪能出来る。これを下さったPapageno様には心の底から感謝を捧げたい。 ⑤は2011年1月にH.M.様より贈って頂いたCD−Rである。1954年2月、どういう理由か不明だが、ウィーンでベームがベルリン・フィルを指揮してヨハン・シュトラウス演奏会を開いた時の貴重な記録である。 壮年時代のベームがフルトヴェングラー時代のベルリン・フィルを指揮、という事で、1曲目に置かれた『皇帝円舞曲』からしていきなり剛毅なドイツ的演奏が繰り広げられている。旋律群は素朴。しかし、味わい深い。ハプスブルク家の皇帝ならぬホーエンツォレルン家の皇帝を想起させる演奏だ。コーダで猛烈にたたみかけて行くのも如何にもライヴのベームっぽい。 『ペルシャ行進曲』は勢いの良さが目立つ演奏であり、『ピツィカート・ポルカ』もニュアンスの豊かさよりはたたみかけて行く様な進行を身上とする。『常動曲』は録音に物足りなさを感じる部分があるが、親しみ易い。『トリッチ・トラッチ・ポルカ』は活力に溢れ、一直線に突き進む。 この後、『蝙蝠』序曲が入るが、それは他の頁で。『美しく青きドナウ』は録音状態と管弦楽がベルリン・フィルという事で、旋律群の色気にはやや欠けるが、素朴な味わい深さはあり、強奏部では俄然ベーム〜ベルリン・フィルならではの剛毅さがところどころに顔を覗かせる。コーダは『皇帝円舞曲』同様猛烈にたたみかけて行く。 『ラデツキー行進曲』はウィーン的情緒とは別の硬質な響きと推進力を身上とする演奏。如何にもドイツの軍楽隊の行進曲に成っている。 総じて壮年時代のベームとフルトヴェングラー時代のベルリン・フィルの姿が随所に感じられ、ウィーンの香りにはやや乏しいものの、ファンにとっては充分聴き応えがあり、これを下さったH.M.様には心の底から感謝するばかりである。 | |
| ワルツ&ポルカ | 喜歌劇『蝙蝠』 |