| 序曲 |
| ① |
 | A・歌劇『後宮からの誘拐』序曲K.384/ |
| B・歌劇『フィガロの結婚』序曲K.492 |
| ドレスデン国立管弦楽団 |
| 1939年、ドレスデン |
| ワーナー(旧EMI) 0190295886721 |
| ② |
 | 歌劇『劇場支配人』序曲K.486 |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1949年、ウィーン |
| EMI SGR-8001 |
| ③ |
 | A・歌劇『ドン・ジョヴァンニ』序曲K.527/ |
| B・歌劇『コシ・ファン・トゥッテ』序曲K.588/ |
| C・歌劇『フィガロの結婚』序曲K.492 |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1955年11月6日(A)、1966年4月2日(B)、1967年4月28日(C)、ウィーン |
| ポリドール(現ユニヴァーサル) DCI 1053 |
| ④ |
 | A・歌劇『フィガロの結婚』序曲K.492/B・歌劇『ドン・ジョヴァンニ』序曲K.527/ |
| C・歌劇『コシ・ファン・トゥッテ』序曲K.588/D・歌劇『魔笛』序曲K.620/ |
| E・歌劇『後宮からの誘拐』序曲K.384/F・歌劇『劇場支配人』序曲K.486/ |
| G・歌劇『クレタの王イドメネオ』序曲K.366/H・歌劇『皇帝ティートの慈悲』序曲K.621 |
| ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団(A) |
| プラハ国立歌劇場管弦楽団(B) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(C) |
| ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(D) |
| ドレスデン国立管弦楽団(E、F、G、H) |
| 1964年〜79年、ウィーン、ベルリン、プラハ、ドレスデン、ザルツブルク |
| ユニヴァーサル UCCG-4156 |
歌劇の序曲というと、ウェーバーの『オベロン』や『オイリアンテ』、ロッシーニの『ウィリアム・テル』の様に、序曲だけが飛び抜けて有名で、オペラ本編が演奏される機会の少ないものもあれば、ワーグナーの様に、オペラが愛される一方で、序曲・前奏曲集が盛んに作られる作曲家もいる。モーツァルトの歌劇の魅力は矢張りオペラ全体にあるが、天才の筆によるだけに、序曲も魅力に溢れており、現在でも世界中で愛されているものが少なくない。中には『劇場支配人』の様にオペラ本編が演奏される機会が殆どないものもあるが。
①は録音年代が古いが、既にベームのフォーマットが確立されていた事が窺い知れるし、作品の魅力は充分に感じ取れる演奏であるという事が出来るだろう。尚、2000年頃にTIMから出ていた10枚組ではこの録音の管弦楽がウィーン・フィルと成っていたが、2017年にワーナー(旧EMI)から出たBOXではドレスデン国立管と成っているので、これが正解だろう。尚、TIM盤、ワーナー盤の違いはそれ程感じられない。
④は何れも歌劇全曲盤からの抜粋だ。基本的には序曲だけを聴くよりも、全曲を聴いた方がより充実感を味わえる事は間違いないが、何れも魅力たっぷりの音楽ばかりなので、序曲ばかりとはいえ、軽視は出来ない。ベームの指揮も皆完成度が高く、こうした序曲においても、巨匠のモーツァルト演奏の素晴らしさは充分感じ取る事が出来る。初心者や、全曲盤を聴く時間がない時などに重宝なCDだといえよう。
③はH.M.様より頂戴したディスクである。元々これは1970年に国連食料農業機関の世界飢餓救済運動の為のチャリティー・レコードとしてドイツ・グラモフォンが発売した物で、ベームがウィーン国立歌劇場で指揮した公演の中から有名序曲を選び、20世紀を代表する画家ココシュカの画によるジャケットと、ココシュカとベームのサイン入りで『カール・ベーム〜ドイツ・オペラ序曲集』として発売された。これは未だに公式にCD化されておらず、1993年に出た『カール・ベームNHKライヴ1975』のおまけCDとして作成された非売品である。この内、『ドン・ジョヴァンニ』序曲はウィーン国立歌劇場再建記念公演の全曲盤の③と同一だが、レーベルが違う事によって、若干迫力が増している様に思われる。ウィーン・フィルの優美さは勿論健在だ。歴史的公演に我々を誘ってくれる録音である。『コシ・ファン・トゥッテ』序曲は今回初めて聴く音源だが、演奏は素晴らしい。音に張りがあるし、きびきびとした流れの中で、ウィーン・フィルが醸し出す豊かな表情は流石だ。如何にもライヴらしい臨場感たっぷりの名演だ。『フィガロ』序曲も推進力と美しさを併せ持ち、聴き応え充分。3曲何れもベームの男性的力強さとウィーン・フィルのえもいわれぬ表情が見事に融け合い、至福の刻を齎してくれる。これを下さったH.M.様には何時もの事ながら、ひたすら感謝するのみだ。
②もまたH.M.様より頂戴したディスクである。第二次世界大戦直後、ベームはドレスデン時代程録音環境に恵まれていた訳ではなかった。EMIはフルトヴェングラーの録音を柱に据え、更にフィルハーモニア管弦楽団創設後、クレンペラーやカラヤンとの録音が優先された事もあり、EMIにおけるベームの扱いはドレスデン時代とは比べるべくもなくなっていた。また、ベーム自身、ウィーン・フィルともっと録音を行いたかった為、1950年代に入るとデッカと契約する。しかし、デッカはクナッパーツブッシュを最優先しているところがあり、ベームはクレメンス・クラウスやエーリッヒ・クライバー、ヨーゼフ・クリップスらと仕事を分担させられている様な面があった(ベームがデッカに見切りをつけた頃、クラウスやクライバーは世を去り、シューリヒトが一連の録音を行う様になった他、やがてこのレーベルの支柱となるショルティが参入して来る)。そのせいか、一時的にフォンタナ(フィリップス)に一連の録音を行い、そして最終的にはカラヤンと同じドイツ・グラモフォンを選び、晩年の大量の録音を行った事は言う間でもない。この②は戦後、ベームがデッカと契約する迄の間、EMIとの間に行った僅かな録音の一つである。戦時中のEMIへの幾つかのウィーン・フィルとの演奏に比べ、録音はずっと良くなっている。現代の録音とは比べるべくもないとは言え、密度の濃さや力強さが感じられるし、美しさもある。如何にも壮年時代のベームらしい爽快感溢れる仕上がりだ。この序曲の魅力を充分に知らしめる名演と称して差し支えあるまい。これを下さったH.M.様にはひたすら感謝するばかりである。 |
| 歌劇『後宮からの誘拐』K.384より「どの様な責苦があろうとも」 |
 | エディタ・グルベローヴァ(ソプラノ) |
| ウィーン国立歌劇場管弦楽団 |
| 1979年6月15日、ウィーン |
| ORFEO C 857 112I |
2012年3月に発売されたこの演奏、グルベローヴァの1977年から2010年迄のウィーン国立歌劇場における公演から彼女の名唱を集めた2枚組ディスクに収録されている。1979年の公演からの記録という事なので、翌1980年にベームが指揮し、グルベローヴァがコンスタンツェを演じた、有名なバイエルン国立歌劇場でのライヴ映像と内容的には大きな差異は認められない。
しかし、このディスク、ベーシック音量が小さい。当然ヴォリュームを上げて聴いてみたが、それにも関わらず、グルベローヴァの歌唱を強調する為か、管弦楽はいささか抑え気味。その為、バイエルン国立歌劇場との映像程ベームならではの恰幅の大きさは味わえない。しかし、繊細な部分におけるウィーン国立歌劇場管の美しさは流石と言うべきで、また、グルベローヴァの歌唱がバイエルン同様素晴しい為、多少の録音への不満など消し飛んでしまう。とはいえ、ベームとグルベローヴァが組んだ『後宮』には先述の1980年のバイエルン国立歌劇場での全曲ライヴ映像があるので、『後宮』を味わいたいなら、そちらの方が断然良い。このディスクの魅力は様々な歌劇におけるグルベローヴァの「女王」振りを堪能する事にある。 |
| 歌劇『フィガロの結婚』K.492より「もう飛ぶまいぞこの蝶々」 |
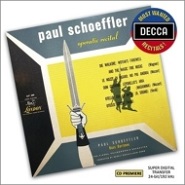 | パウル・シェフラー(バリトン) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1950年9月、ウィーン |
| Decca 4808176 |
これは2014年5月末にDeccaから出た”パウル・シェフラー〜オペラティック・リサイタル”に収録されている演奏である。シェフラーと言えば生地ドレスデンで活躍していた所、総監督として赴任して来たベームに気に入られ、ベームがウィーン国立歌劇場総監督就任すると、これに伴い拠点をウィーンに移し、文字通り”ベーム・ファミリー”の重鎮の一人として活躍した事はファンならばよく知っている。
此処では『フィガロ』の「もう飛ぶまいぞこの蝶々」が収録されているが、これが良い。シェフラーもベームも互いに知り尽くしているだけあって、コンビネーションには安定感があるし、万事ソツがない。プライのフィガロが好きな私にとって、シェフラーのフィガロ像は私の中のフィガロ像とは必ずしも重なり合わないが、それは色男というより親父臭い声質だからで、歌唱そのものは特に問題は無い。
ベーム〜ウィーン・フィルがこれまた素晴らしい。優美にして生気に溢れ、本当に惚れ惚れとする。これを聴くと、この時期のウィーン・フィルの響きを懐かしむ人が未だに後を絶たない事にも肯ける。正に歴史的名演と称するに相応しい出来栄えである。 |
| 歌劇『ドン・ジョヴァンニ』K.527より「カタローグの歌」 |
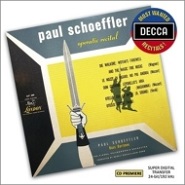 | パウル・シェフラー(バリトン) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1950年9月、ウィーン |
| Decca 4808176 |
これは2014年5月末にDeccaから出た”パウル・シェフラー〜オペラティック・リサイタル”に収録されている演奏である。シェフラーのドン・ジョヴァンニ役は残念ながらベームの棒による『ドン・ジョヴァンニ』全曲盤では複数存在する録音の内、一つも存在しないが、レオポルト・ルートヴィヒ指揮の1951年の放送用セッション録音で聴く事が出来る(私は未聴)。尤も、ベームのまだ陽の目を見ぬ『ドン・ジョヴァンニ』の中に若しかするとシェフラーをタイトル・ロールに据えた録音が存在するかも知れない。
シェフラーのドン・ジョヴァンニはシエピの様な一寸キザでダンディーな色男という感じでも無ければ、ディースカウの様に器楽的な完璧さとややインテリっぽい所がある感じでも無い。長い女性遍歴によって培われた老練さといった感じがする。従って人間的な懐の広さがある。1897年生まれのシェフラーは既にこの時期には歌手として大ヴェテランの域に達していただけに、歌唱の安定感も流石である。ベーム〜ウィーン・フィルは軽快かつ優美にシェフラーの歌唱と一体化。たった1曲のアリアながら、流石と言える歴史的名演だと思う。 |
| 歌劇『ドン・ジョヴァンニ』K.527より「彼女の幸せこそ私の願い」「私の愛する人を」 |
 | アントン・デルモータ(テノール) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1950年、ウィーン |
| Decca 4808169 |
| これは2014年5月末にDeccaより発売された”ユリウス・パツァーク・リサイタル”のボーナス・トラックとして収録されている演奏で、こちらは1950年代のウィーンを代表するテノールだったデルモータが独唱を担当している。録音当時はまだヴンダーリヒやシュライヤーが出現しておらず、デルモータは疑い様もなく最高のモーツァルト・テノールの一人だった。勿論、この2曲のアリアでも豊かな表現力を発揮している。声の鮮度も録音年代を考えれば上々。ベーム〜ウィーン・フィルの伴奏は若干録音の古さを感じるが、惚れ惚れする様な美しさがそれを補って余りある。上述の如く、私は歌劇は全曲盤で聴くべきと考えており、あまり抜粋等は好きではない事や、ベームには数多くの『ドン・ジョヴァンニ』の全曲盤が存在するだけでなく、デルモータ演じるドン・オッターヴィオもその中の2種類の録音で聴く事が出来る為(1955年のナポリ・サン・カルロ劇場ライヴとウィーン国立歌劇場再建記念祝祭ライヴ)、このディスクでの演奏にあまり関心が湧かず、購入して半年近く経ってから漸くこれを聴いた訳だが、アリアそのものの演奏としては、共に歴史的名演と称するに相応しいものだと思う。 |
| 歌劇『魔笛』(抜粋)K.620 |
 | ザラストロ……エマヌエル・リスト(バス) |
| タミーノ……リベロ・デ・ルカ(テノール) |
| 弁者……デリック・オルセン(バリトン) |
| 夜の女王……アドリーネ・ミグリエッティ(ソプラノ) |
| パミーナ……リーザ・デラ・カーザ(ソプラノ) |
| 侍女1……コレッテ・ローランド(ソプラノ) |
| 侍女2……マルグリット・フォン・シベン(メゾ・ソプラノ) |
| 侍女3……リーゼ・デ・モントモルリン(アルト) |
| パパゲーノ……フリッツ・オルレンドルフ(バリトン) |
| パパゲーナ……マルタ・ギャボリー(ソプラノ) |
| モノスタトス……ウィリアム・ワーニック(テノール) |
| スイス・ロマンド管弦楽団&合唱団 |
| 1949年9月25日、ジュネーヴ |
| CASCAVELLE RSR 6147 |
HMVのHPでこの盤を見かけた時、曲目と型番位しか書いていなかった為、私は購入する迄これを全曲盤だと思っていた。今は休止中のTOSCA様のサイトでも1949年のスイスでの『魔笛』は全曲盤だったと記憶していた。だから、同時に購入したベームのCD4点中、私はこれを聴くのを一番の楽しみにしていた。だが、しかし。帰宅後、開封してインデックスをチラリと見た私のテンションはガタ落ちとなった。全曲盤のほぼ半分の70分程しかない抜粋だったのである。楽しみはすっかり何処かへ消え去ってしまった。
私は基本的に歌劇の抜粋物は嫌いだ。確かにワーグナーの『指環』みたいな超大作は高価だし、取敢えず抜粋を……というのも或る意味仕方がないと思う。レコード会社としては全曲盤を聴くか躊躇している人の為に、聴き所満載の”入門編”を作りたいのかも知れないが、それはあくまで全曲盤が存在する事が前提となろう。全曲盤がないのに抜粋を売ろうというのは熱心なファンにとっては逆に生殺しだ。大体物語が寸断されるのだから、逆にこういうのを”入門編”にしてはいけないと思う。歌曲集ではないのだから、歌劇は矢張り全曲を収録して欲しい。尤も、これが幾つかの名作歌劇のアリア集とかになると、もう歌劇の面影は殆どないから、まあ許せるが、抜粋はその意味でも中途半端。それでも、例えばその作品中他に存在しないとか、その演奏家としてはそれが唯一の音源という付加価値があれば、或る意味仕方がないと思う。それなら尚更抜粋はまずいではないか、という人もいるだろうが。何れにせよ、ベームには既にウィーン・フィルとベルリン・フィルを指揮したスタジオ録音2種類が何れも名盤との評価を確立しており、今更こんな抜粋が出て来てもしらけてしまう。全曲盤の登場を是非望みたいところだ。
……愚痴はこの位にして演奏に移ろう。1949年なので、音はそんなに良くない。しかし、序曲からして壮年期のベームの颯爽として推進力に溢れる内容は充分に聴き応えがある。スイス・ロマンド管もアンセルメの薫陶がよく行き届き、音の古さを超えたアンサンブルを聴かせてくれる。歌手陣では何と言ってもリーザ・デラ・カーザのパミーナが素晴らしい。清純にして品格に溢れているだけでなく、内面もよく表現されている。他では特別に良いと感じた歌手はいないが、概ね悪くは無い。中には一寸音程のずれが生じている歌手もいるが、聴くに耐えないという程ではなく、まあ許せる範囲。第一幕終景は流石に音が劣悪過ぎて頂けない。コーラスが遠過ぎて全然よく聴こえないのだ。でも、第二幕終景は音が悪いなりにちゃんと盛り上がりを見せる。演出によるコーラスの配置場所が影響したのかも知れない。何れにせよ、これは仮に全曲盤が存在したとしても、この音質のままであれば、ファンの為の史料の域を出ない事は間違いない。 |
| 歌劇『魔笛』K.620より「この美しい絵姿」 |
 | アントン・デルモータ(テノール) |
| ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |
| 1950年、ウィーン |
| Decca 4808169 |
| これは2014年5月末にDeccaから出た”ユリウス・パツァーク・リサイタル”のボーナス・トラックに収録されている演奏の一つで、録音当時最高のモーツァルト・テノールと目されていたデルモータ演じるタミーノの表情豊かな歌唱を楽しめる。録音はデッカのスタジオ録音なので、年代を考えれば上々の部類。ベーム〜ウィーン・フィルに関しては若干音の古さを感じるものの、演奏の素晴らしさがそれを何時の間にか忘れさせてくれる。兎に角美しいの一言。このアリアの歴史的名演と称するにやぶさかでない。 |




