




BGM(フレーム表示)付で見たい方はこちら(既に表示されている方は関係ありません)。
私の所有盤
〜コルトー、シュナーベル、カサドシュ
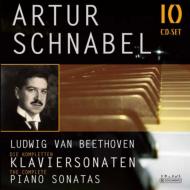
|
コルトー 〜私の所有盤〜 ①(CD)『ティボー&コルトー/フランス音楽作品集』 ティボー(Vn)他 Andromeda ANDRCD5138 ②(CD)『パブロ・カザルス/ポートレイト』 カザルス(Vc)他 Membran 232768 ③(CD)シューマン:ピアノ協奏曲他 RIASSO他 Audite AU95498 ①にはティボーのヴァイオリンで録音したフランク:ヴァイオリン・ソナタ(1929年)、ドビュッシー:ヴァイオリン・ソナタ(1929年)、フォーレ:ヴァイオリン・ソナタ第1番(1927年)、フォーレ:『ドリー』Op.56から『子守歌』(1944年)、 ショーソン:ヴァイオリン、ピアノ、弦楽四重奏のための協奏曲ニ長調Op.21(1931年、弦楽四重奏はVnがイスナール、ヴルフマン、Vaがブランパン、Vcがアイゼンベルク)が収められている。 20世紀前半を代表するフランスの大ピアニスト、アルフレッド・コルトーは、二人の姉の指導を受けた後、パリ音楽院で学び、ピアニストとしてデビューする一方、ワーグナーに傾倒し、1896年と1897年にはバイロイト祝祭の助手を務め、1902年頃から指揮者としても活動し、『神々の黄昏』のフランス初演も行っている。 1905年から第二次世界大戦直前迄ヴァイオリンのティボー、チェロのカザルスとカザルス・トリオを結成し、一時代を築く一方、教育者としても活躍。1919年にはパリ音楽院の方針に反発してエコール・ノルマル音楽院を創設し、ハスキルやリパッティ、ムスリン、ハイドシェック、遠山 慶子などを指導している。戦後はナチス主催の演奏会にしばしば出演した事の責任を問われ、フランス国内での演奏機会が失われ、国外で活動せざるを得なく成る。 コルトーのレパートリーは広くはなく、初期ロマン派とフランス近代音楽中心だったという。そして、①にはコルトーが盟友ティボーと録音したフランス物の数々が収められている。何れも録音は古いが、コルトーの詩情豊かなピアノとティボーの繊細で上品なヴァイオリンが織り成す演奏は、何処か古き佳き時代のフランスを感じさせ、独特の魅力がある。一度は聴いておいて損はない。 ②には1926年録音のシューベルト:ピアノ三重奏曲1番(ヴァイオリン:ティボー、チェロ:カザルス)が収められている。 1905年に結成され、一時代を築いたカザルス・トリオの記録である。トリオはコルトーがナチスに協力的としてカザルスが反発し、第二次世界大戦直前に脱退、代わりにフルニエが加わる事に成るが、カザルスあってのカザルス・トリオだけに、印象度がやや低く成ってしまった事は止むを得ない。 何れにせよ、カザルス・トリオは詩情豊かなコルトーのピアノ、繊細にして品格の高さを漂わせるティボーのヴァイオリン、骨太で深い精神性と熱く濃厚な感情表現、雄弁な語り口を誇るカザルスのチェロが各々の個性を存分に発揮しつつ、長年協演を重ねた事により獲得したチーム・ワークも感じさせ、その録音は古いSP時代の物ばかりであるにも関わらず、今尚決定盤に推す向きが少なからずある程の名演揃いであるという。即ち、大家三人が顔を揃えたから伝説的トリオと称されたのではなく、演奏が素晴らしいからこそ、伝説的トリオたりえたという事だ。 私が持っているのは、現在の所②のみで、あまり大きな事は言えないが、此処でも録音の古さを超えて、伝説的トリオが織り成す演奏の魅力は充分感じ取れる。勿論、一度は聴いておいて損はない。 ③にはフリッチャイ〜RIAS響と協演したシューマン:ピアノ協奏曲の1951年ライヴが収められている。 シューマンのピアノ協奏曲はコルトーにとって最重要レパートリーの一つで、SP時代に行われた録音は後の多くのピアニストにも影響を与えたという。SP時代の録音は私は持っていないので、何とも言えないが、此処でもコルトーならではの詩情の豊かさに今では得難い古き佳き時代の香りを感じる。ミスタッチや老齢による衰えを指摘する向きもあるが、元々技巧で聴かせるタイプではなく、内容で魅了するタイプなので、個人的には充分コルトーの存在感は発揮していると思う。 フリッチャイはシューベルトの『ザ・グレート』のライヴなどで聴かれる様に、1950年代半ば過ぎから徐々にフルトヴェングラーばりの深みや壮大さを感じさせる演奏が増えて行くが、此処では1951年の録音という事で、若々しい緊張感に溢れる一方、後年とは異なるものの、感情の豊かさも充分感じさせ、魅力一杯。記録としての貴重さは勿論、内容自体も一度は聴いておいて損はない名演と言うべきであろう。 シュナーベル 〜私の所有盤〜 ・(CD)ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集 Membran 223051 シュナーベルが1932年から1935年にかけて録音したこのベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集は、SP時代には聖典視される位有名な物だった。その後、バックハウスやケンプらが出現した事により、断然の存在ではなくなったが、それでもこの2人と並び、”20世紀3大ベートーヴェン弾き”と称されている。 シュナーベルは技巧より内容を重視、またピアニストの主情が前面に出て、大袈裟な表現に成る事を良しとせず、楽譜を拠り所として、客観的な演奏態度で造型と作品が内包する感情や精神の両立を目指したという。 しかし、より録音が良く、内容もモダンなバックハウスやケンプを既に聴いて来た私にとって、シュナーベルの演奏は録音が古く、やや量感や立体感に不足し、若干聴き劣りがする。一方で、ベートーヴェンをはみ出す程主情が濃厚に出ているという訳ではないが、テンポの設定や感情表現に19世紀的ロマンティシズムが感じられ、それがバックハウスやケンプと異なる魅力と成っている。その独特の味わいは今では得難いもので、一度聴いたら忘れられない存在感があり、伊達に”20世紀3大ベートーヴェン弾き”と称された訳ではないと納得出来る。 シュナーベルのファンは勿論、ベートーヴェン演奏を語る上で、必聴盤と言えるだろう。 カサドシュ 〜私の所有盤〜 ①(CD)モーツァルト:ピアノ協奏曲集 クリーヴランドO他 SONY SICC-482-4 ②(CD)モーツァルト:ピアノ協奏曲集 ケルン放送SO他 GOLDEN Melodram GM 4.0078 ③(CD)『シューリヒト/モーツァルト名演集』 ウィーンPO他 Memories MR2189 ④(CD)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲5番『皇帝』他 アムステルダム・コンセルトヘボウO他 ユニヴァーサル(タワーレコード限定) PROC-2117 ⑤(CD)『マルティノン/シカゴ響録音全集』 フランス国立放送O他 Sony 88843062752 ①にはセル〜コロンビア響と録音したモーツァルト:ピアノ協奏曲22番(1959年)、23番(1959年)、26番(1962年)、27番(1962年)、セル〜クリーヴランド管と録音した21番(1961年)、24番(1961年)、オーマンディ〜フィラデルフィア管と1960年に録音した2台のピアノの為の協奏曲(10番、2台目のピアノは夫人のギャビー・カサドシュ:1901〜1999)が収められている。 故・吉田秀和氏は『レコードのモーツァルト』で「カサドシュといえば、極め付きの美徳として知られていた、あの円くて、しっとりとした輝きがあって、粘っこさというものがなくて、しかもカサカサの無機的な感じを少しも与えない、軽くて、決して軽っぽくない所謂真珠の珠を列ねた様なレガートの美しさ、 (中略)しかし、カサドシュといえば、私など(中略)ラヴェルやドビュッシーといったフランス近代音楽のピアノの名作はいうまでもないが、それにも増して、彼のモーツァルトを高く評価していた。(中略)こういうモーツァルトは嘗ても無かったし、今後ももう出ないのではあるまいか。これは”モーツァルトの音”という事について、或一つの理想のイメージが定着していた、一つの時代の記念碑的な演奏なのである。 (中略)その音の音楽家はまた、自分のしている仕事について厳しい自己批判の精神に満ち、自己中心的でないのは勿論、作品即自分べったりという行き方でもなく、寧ろ作品の方から何処迄も自分を客観的に見つめながら仕事をするというタイプでなければ実現出来ない様な、そういう演奏でもあるのだ。 そういう点では20世紀のモーツァルト像の一つの礎石を置いたブルーノ・ワルターともまた一寸違う。ワルターのは自分と作品との幸福な一致を目指すという所があり、それがまた彼の場合、モーツァルトで奇蹟的な高さで達成出来た訳だったが、カサドシュの場合は、ワルター程それ程強力などうしても解決しなければ成らない問題を持った存在ではなかった。 寧ろ、その点ではカール・ベームに近いと言っても良い位だろう。ベームのモーツァルトがかけがえのない素晴らしさを持っているのは、ベーム自身に、モーツァルトと取り組む場合、その前に解決しておかねば成らない問題がなく、作品そのものに単刀直入に入って行かれるからだ。そうして、其処から彼特有の、まるで細密画家の厳しい良心のかけられた手仕事の様な精進が始まる。 カサドシュには、そういう精進的なものの匂いはあまり感じられなかった。しかし、彼のあの見事に粒の揃った音は彼自身の獲得した美質だったのであって、同じ近代フランスの名ピアニストの流れに属すると言っても、(中略)アルフレッド・コルトーやラザール・レヴィのもとでさえ、同じ高さでは見出し難いものだった。 (中略)指揮は(共に)ジョージ・セル。これがまた、引き締まった、実に良いモーツァルトを聴かせる。この顔合わせは嘗て絶品と謳われたものである。 (中略)これ位のピアニストに成ると、彼の芸術の総てが彼一人のものであると同時に、もっと大きな審美の生理学の一コマでもあるのだという事が解る。 改めて、惜しい大家を亡くしたという気がする訳である。現代はもうこういう人を生み出す地盤はなくなっている。それは芸術家一人一人の問題であるのと同じ位、それを超え、それを包んでいる、もっと大きなものの在り方の問題なのだ」と書いている。 これを読んで私はカサドシュの事を知り、興味を抱いたが、中々購入機会には恵まれず、21世紀を迎えて漸く彼の録音を入手した時には既に30年程の歳月が経過していた。尤も、何れもモーツァルトの、それも協奏曲のみで、彼が他に得意としたドビュッシーやラヴェル、或いはフランチェスカッティとのデュオといった所は未だに持っていない。 それはさておき、この協奏曲集を聴いた時、私の脳裏に浮かんだのは吉田氏の文章だった。私とて吉田氏ではないから、何時も彼の批評に同調している訳ではないし、それは他の評論家についても言える事だが、一方で、時に彼らと私の感想が一致する事もある。そして、此処でのカサドシュのピアノを聴いた私の感想は吉田氏とほぼ同じだった。従って、私の方でこれ以上付け加える言葉はない。 セル〜クリーヴランド管及びコロンビア響(恐らく実質はクリーヴランド管若しくはそれ主体だろう)もスマートで精緻な響き、整然たる様式感何れも流石で、今尚これらの協奏曲の代表的名盤の一つとして各々充分に存在を誇り得る。 夫婦協演による10番の協奏曲では、ギレリス親娘のスタジオ録音やライヴ同様アット・ホームな雰囲気を湛えつつ、フランス人らしい上品さやエスプリを感じさせる所が魅力だ。指揮者と管弦楽はベーム〜ウィーン・フィルと協演しているギレリス親娘の方が強力だが、オーマンディ〜フィラデルフィア管も協奏曲に関しては海千山千なだけに、決して悪くはない。 いずれにせよ、この協奏曲集はフランスきっての大ピアニスト、カサドシュの代表的録音として、ファンにとっては必聴盤だと思うし、モーツァルティアンにとっても一度は聴いておいて損はない録音ばかりだと思う。 ②にはセル〜ケルン放送響とのモーツァルト:ピアノ協奏曲24番の1960年ケルン・ライヴが収められている。他に1953年のケンプ〜ベーム〜ヘッセン(フランクフルト)放送響の22番、1953年のアンダ〜カイルベルト〜ケルン放送響の17番、1955年のフォルデス〜サヴァリッシュ〜ケルン放送響の25番が収められており、元々はケンプとベームとの協演を聴く為に購入したディスクだが、その他の演奏も各々貴重な記録というだけでなく、楽しめるものばかりであった。因みに、ケンプの22番はこれより後に発売されたベーム〜ヘッセン(フランクフルト)放送響のライヴ集にも収められている。 それはさておき、此処でのカサドシュの演奏だが、①に含まれるスタジオ録音の一年前の演奏で、しかも指揮が同じくセルという事で、比較的内容はよく似ている。録音がやや聴き劣りがする点は否めないが、内容そのものは①に含まれる演奏同様虚飾を排し、作品の素の魅力を引き出しており、一方で時折ライヴならではの感興の自由さも感じさせる。一度は聴いておいて損はない名演だと思う。 ③はシューリヒトのモーツァルトの交響曲や協奏曲のライヴを主に纏めたBOXで、カサドシュは1961年8月23日ザルツブルク祝祭におけるモーツァルト:ピアノ協奏曲27番(ウィーン・フィル)が収められている。 因みにこのBOXには他にハスキル(9番、19番)、アスケナーゼ(17番)、ゼーマン(19番)、ニコラーエワ(22番)のライヴが収められており、往年の名ピアニスト達の貴重な記録と成っている。 カサドシュのモーツァルト:ピアノ協奏曲27番と言えば、①に含まれるセルとのスタジオ録音が昔からこの協奏曲の代表的名盤の一つとして知られているが、この盤ではその前年のシューリヒト〜ウィーン・フィルとのザルツブルク祝祭における協演の記録を聴く事が出来る。因みに、ザルツブルク祝祭におけるモーツァルトのピアノ協奏曲27番と言えば、バックハウス〜ベーム〜ウィーン・フィルが当時最高の呼び物の一つで、録音も1956年と1960年の2種類のライヴが遺されている。また、バックハウス〜ベーム〜ウィーン・フィルには今尚決定盤の座を争っている1955年のスタジオ録音もある為、このカサドシュ〜シューリヒト〜ウィーン・フィルはいささか影が薄い。 しかし、演奏そのものは好き嫌いは別にして、かなり印象に残る。演奏時間はⅠ楽章とⅡ楽章が①より1分程速いが、バックハウス〜ベーム〜ウィーン・フィルと比べると特別に速いという訳ではなく、Ⅱ楽章は寧ろ遅い。尤も、時に凄い速さで駆け抜けて行く事で知られたシューリヒトが指揮をしているせいか、此処でも両端楽章で前がかりに成る位テンポが性急に成る。カサドシュは一見それにサラリと合わせている様に思われるが、いささか力みがあり、ミスタッチも聴かれる。一方で、ライヴならではの情熱の高まりが時に異様な迫力を生んでいる。Ⅱ楽章は先述の如く①より1分程速いが、他の名盤と比べればそれ程速いという訳ではなく、カサドシュは比較的落ち着いた雰囲気で持ち味の粒の揃った美音を聴かせるし、シューリヒト〜ウィーン・フィルは時折気儘にテンポを動かしつつ、美しい響きを奏でている。全体的にシューリヒトの個性が強く出た演奏という感があるが、シューリヒトに負けじと奮闘するカサドシュも①とは異なる存在感を発揮しているので、一度は聴いておいて損はない。 ④には1961年2月3日と4日にロスバウト〜アムステルダム(現ロイヤル)・コンセルトヘボウ管とフィリップスに録音したベートーヴェン:ピアノ協奏曲5番『皇帝』が収められている。 カサドシュには1955年のカンテルリ〜ニューヨーク・フィルとのライヴや同年のミトロプーロス〜ニューヨーク・フィルとのスタジオ録音もある様だが、未聴。この④でのカサドシュは全体的に速目のテンポによって、粒の揃った品格の高い響きと隙のない様式感を達成し、雄渾な響きやスケールの大きさを身上とする演奏とは異なる魅力を感じさせるし、ロスバウト〜コンセルトヘボウ管も端正な響きと引き締まった造型で聴き応え充分の演奏を繰り広げている。決定盤の座を争う様な演奏とは思わないが、一度聴いたら忘れられない魅力に溢れた歴史的名盤の一つだと思う。 ⑤はフランスの名匠マルティノンがシカゴ響首席時代にRCAに行った録音を纏めた10枚組BOXの10枚目におまけとして入っている演奏で、1969年6月にカサドシュがマルティノン〜フランス国立放送管とCBSに録音したカサドシュの自作、ピアノ協奏曲Op.37が収められている。 カサドシュは自作を幾つか録音している様だが、この⑤の演奏は初出らしい。何れにせよ、此処では作曲家としても演奏家としてもフランス人としてのカサドシュを聴く事が出来る。即ち、ドビュッシーやラヴェル、サティといった所や、6人組の影響が随所に感じられる。フランス音楽のスペシャリスト、マルティノンの指揮するフランス国立放送管がバックを務めているのも魅力で、明晰にして感興豊かな演奏を繰り広げている。作曲家としてのカサドシュの史料の一つとしてだけでなく、鑑賞度の高さも具えた録音として、一度は聴いておいて損はない。 |